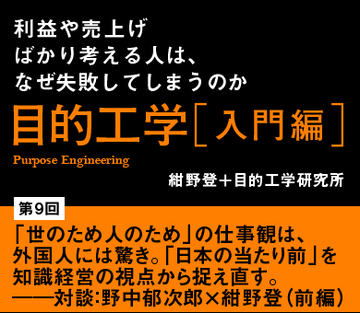野中郁次郎
第14回
この夏、ノルマンディーを再訪し、人工港の残骸やボカージュ、レジスタンスの功績を強調する博物館を見学して、アイゼンハワーや多くの兵士たちがつくった歴史の重みに接し、あらためて多くのことを感じた。また、フランス滞在中にフランス経済の凋落ぶりを目の当たりにして、歴史は繰り返す、という言葉を思い浮かべずにはいられなかった。

第13回
前回は設備や装備の話を中心に、ノルマンディー上陸戦でのイノベーションについて見た。次に、リーダーシップや創意工夫という点からも、革新性を見ていきたい。そのポイントは3つある。

第12回
前回は、米国海兵隊が生み出した「水陸両用作戦」が、太平洋戦域で日本軍を追い詰めていく様子を描いた。今回は、ノルマンディー上陸戦に至るまでに、欧州戦域において実行された初めての上陸作戦での手痛い失敗とノルマンディー上陸作戦以前に行われた2度の上陸経験を取り上げたい。

第11回
今回は、再び第2次世界大戦欧州戦域で行われた軍事作戦・戦術上のイノベーションについて取り上げ、、マネジメントの視点から見ていきたい。前回(連載第8回)はドイツ軍による電撃戦を取り上げたが、今回から前後2回に分けて、米軍と連合軍による水陸両用作戦を取り上げる。

第10回
『史上最大の決断』の発売から2ヵ月が過ぎた。この間、3回の増刷を重ねることができたのは、読者のみなさんのご支援があってのことと深く感謝している。69回目を迎えた8月15日終戦記念日にあたり、第2次世界大戦を振り返る「日本の敗戦から69年目に想う」後編は、アイゼンハワーのワイズ・リーダシップについて考えてみたい。
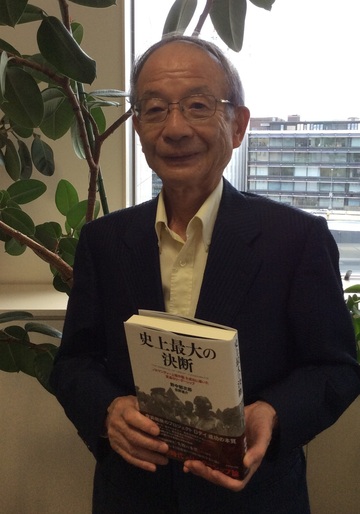
第9回
『史上最大の決断』の発売から2ヵ月が過ぎた。この間、3回の増刷を重ねることができたのは、読者のみなさんのご支援があってのことと深く感謝している。69回目を迎える8月15日の終戦記念日を前に、今回は第2次世界大戦について振り返ってみたい。
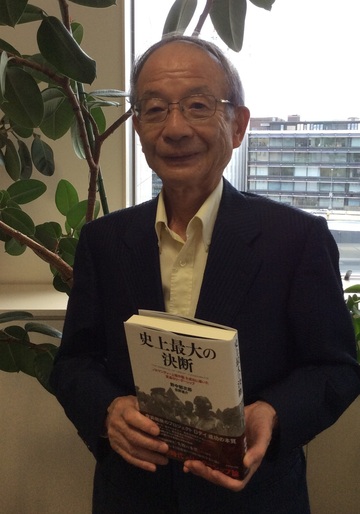
第8回
今回からは趣向を変えて、第2次世界大戦欧州戦域で行われた軍事作戦・戦術上のイノベーションについて、マネジメントの視点から見てみたい。まず取り上げるのが、ドイツ軍によって行われた「電撃戦」である。

第7回
前回は、アイゼンハワーが「実践知リーダー」となるまでの成長過程を描いた。今回は、アイゼンハワーのリーダーシップの能力とはどのようなものだったのか、フロネシスの視点から眺めてみたい。前々回で触れたチャーチルのそれと、何が同じで何が異なるのか。合わせてお読みいただければと思う。

第6回
『史上最大の決断』を書くにあたって、「実践知リーダー」として、私がまず想定したのが、前回取り上げたイギリス首相チャーチルだった。しかし、ノルマンディー上陸に至る物語りを綴るうちに、それにふさわしい人物がもう1人浮上してきた。中佐から元帥まで、史上最速の昇進を重ねた米国軍人にして、上陸作戦の最高司令官を務め、戦後は第34代アメリカ合衆国大統領となるアイゼンハワーがその人である。

第5回
私が『史上最大の決断』を書いた目的の1つは、国を統率する政治家のリーダーシップのあり方を描くことにあった。特に、戦時下という危機の時代にどのようにして国家を率いていくのかに着目した。そのための評価基準が、アリストテレスの唱えた「フロネシス」の能力である。これは賢慮とも実践知とも訳される言葉だ。今回は、このフロネシスの能力を備えた「実践知リーダー」の1人として、英国首相チャーチルを取り上げる。

第4回
ノルマンディー上陸作戦を題材に「歴史のif(もし)」を考えることによって、未来創造のための教訓を得ることができる。今回は、この作戦における革新的な戦術である消耗戦と機動戦の止揚について考えてみたい。これもまた、連合軍の勝利を決定づけた分岐点の1つである。

第3回
「歴史にif(もし)はない」と言われるが、実はifを考えることによって、われわれは当時の人々が下した決断のプロセスをより深く理解し未来創造のための教訓を得ることができる。そこで今回は、ノルマンディー上陸作戦における3つのifを検討してみたい。

第2回
6月6日は「Dデイ」と呼ばれる。人類史上最大の上陸作戦が行われたこの日から今年は70年の節目にあたる。当日フランスで開催される記念式典で旧連合国(米英仏)の首脳が一堂に会するのも、Dデイがナチス・ドイツを打倒するうえで決定的な転機になったからである。

第1回
今からちょうど70年前の1944年6月6日、人類史上最大規模の軍事作戦であるフランス・ノルマンディー海岸への上陸作戦が敢行された。この巨大なプロジェクトを遂行したリーダーたちは、いかにして極限の修羅場でリーダーシップを発揮したのか――1992年、私はその地を訪れた。

日本企業が忘れてしまった強みとは何か?アジアの世紀に再び返り咲くための資本主義――野中郁次郎
私たちは「アジアの時代」にふさわしい経営ができているだろうか。アメリカ型の経営モデルが資本主義の最終進化形と盲信し、それがグローバル・スタンダード経営と考えていないだろうか。はたして、それで勝てるだろうか。
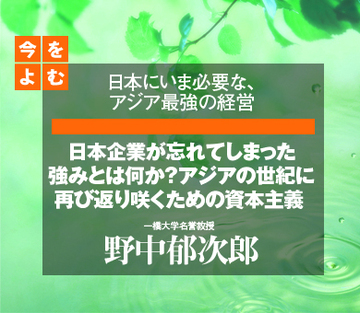
第10回
最先端の経営学は、理論と実践をどう捉えるのか?目的と手段が、JALの再生に果たした役割を考える。――対談:野中郁次郎×紺野登(後編)
知識創造経営のコンセプトの生みの親である世界的経営学者の野中郁次郎氏と、野中氏の研究パートナーで目的工学研究所所長の紺野登氏との対談の後編では、目的に近づいていくための実践的リーダーシップについて語る。
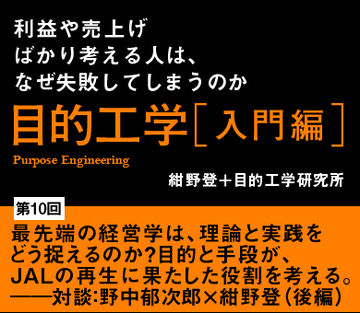
第9回
「世のため人のため」の仕事観は、外国人には驚き。「日本の当たり前」を知識経営の視点から捉え直す。――対談:野中郁次郎×紺野登(前編)
知識創造経営のコンセプトの生みの親である世界的経営学者の野中郁次郎氏と、野中氏の研究パートナーで『利益や売上げばかり考える人は、なぜ失敗してしまうのか』の著者、目的工学研究所所長の紺野登氏との対談前編。