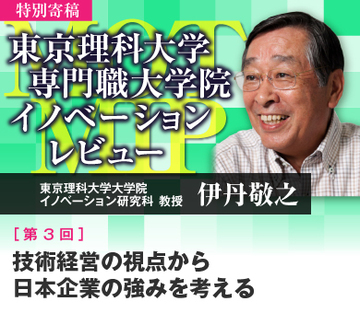アジアの時代と呼ばれて久しいが、私たちはその名にふさわしい経営ができているだろうか。アメリカ型の経営モデルが資本主義の最終進化形と盲信し、それがグローバル・スタンダード経営と考えていないだろうか。はたして、それで勝てるだろうか。日本、中国、韓国を代表する経営学者である野中郁次郎、徐方啓、金顕哲著『アジア最強の経営を考える――世界を席巻する日中韓企業の戦い方』から、野中郁次郎教授によるあとがきを一部編集してお届けする。
産官の知が消滅した日本
このままでは勝てない
日の丸企業の象徴だった日本の家電エレクトロニクス業界はかつての輝きを失った。名門、ソニーやパナソニックには昔日の面影がなく、相次ぐ工場閉鎖やリストラ、事業撤退の後始末に追われている。逆に、この10年ほどで急速に存在感を増したのが、本書で取り上げた中国や韓国の企業だ。それらが市場に投じた、人々のニーズをよく捉えた安価な製品が、高価で過剰品質の日本製品を駆逐した結果といえるだろう。
もっとも、中国および韓国企業の強さは、それ単体で論じられるべきではない。それぞれの背景に、産官が強固に連携する国家資本主義というシステムが存在することは、本書で詳細に述べている。
中国企業の強さの原動力は、その中でも触れたように、華僑の強固なつながりに象徴される「ネットワーク・キャピタリズム」にある。これは人と人との関係(グアンシ)を基礎にしたボトムアップ型のシステムだが、中国人はこれに、トップダウンの資本主義をうまく接ぎ木させ、中国独自の資本主義システムをつくりあげた。
一方の韓国にとって奇貨となったのは、1997年、タイの通貨、バーツの下落をきっかけに起きたアジア経済危機だった。企業淘汰が劇的に進行し、いわば各産業の無駄が削ぎ落とされた。自動車メーカーは1社まで絞られた。それに対して日本は、主要なところだけで8社もある。携帯電話メーカーも韓国は2社しかないが、日本は6社もある。電力会社にいたっては、日本10社に対して韓国は1社しかない。
こうなると国内での無駄な競争が起こらない。資金や税制面などで政府が強固なバックアップを欠かさないので、国際競争力は増すばかりだ。さらに、原発設備に代表されるように、大統領自ら新興国へのトップセールスを展開する産官一体の体制が構築されている。
日本にも「通産モデル」のように、かつては産官が密接に連携し、知を総動員させる体制があったが、現在は消滅している。
 野中郁次郎(のなか・いくじろう) 一橋大学名誉教授
野中郁次郎(のなか・いくじろう) 一橋大学名誉教授早稲田大学政治経済学部卒業。富士電機製造(株)勤務ののち、カリフォルニア大学経営大学院(バークレー校)にて博士号(Ph.D)を取得。南山大学経営学部教授、防衛大学校教授、一橋大学産業経済研究所教授、北陸先端科学技術大学院大学教授、一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授を経て現職。カリフォルニア大学経営大学院(バークレー校)ゼロックス知識学名誉ファカルティースカラー、クレアモント大学大学院ドラッカー・スクール名誉スカラー、早稲田大学特命教授を併任。知識創造理論を世界に広め、ナレッジ・マネジメントの権威として、海外での講演も多数。論文、著書多数。写真は、共著者の徐方啓(右)、金顕哲(左)とともに。
結局、日本人は企業と政府を対立概念で捉えることに馴れすぎたのではないか。それでも企業が勝てた時代はよかったが、グローバル競争はますます激化している。企業に稼いでもらわないと国富は増えない。両者の連携を強化していくことの重要性を、われわれは中国や韓国から学ぶべきだろう。
かといって、日本企業に未来がないかといえば、そんなことはない。日本企業にはこれまで培ってきた「創造モデル」があるからだ。