
河村小百合
日本銀行は今年7月の金融政策決定会合で、政策金利の0.25%への追加利上げと国債買い入れの減額計画を決定した。これにより金融政策運営の正常化と、資産縮小に向けた最初の一歩を踏み出したといえる。だが日銀の対応と、海外の主要中央銀行が軒並み展開してきた政策運営との間には、相当な落差がある。

日本銀行は7月に、イールドカーブ・コントロール(YCC)の実質的な上限を1%まで拡大するなど、徐々に金融政策の正常化へ向けた道筋を探っている。その一方で、足元では物価上昇が賃金上昇を大幅に上回るなか、その状況を打開するような具体的な対策に乗り出せないままでいる。日本総合研究所の河村小百合主席研究員は、こうした金融政策や財政政策に携わる日銀や政府の政策運営姿勢が無責任だと批判する。

岸田政権で2度目の骨太方針では、異次元の少子化対策などの重要政策の財源は曖昧で、「財政再建」は目標年度も示されず素通りだ。債務上限問題を決着させた米国などに比べて財政規律についての緊張感のなさは際立つ。

日銀のYCCによる長期金利抑制が限界に近づくなかで国債管理政策と財政運営は正念場だ。国債費軽減を狙って自民党内で上がる国債の「60年償還ルール」見直しは市場の不信を強め一段の金利急騰を招きかねない悪手だ。

大規模減税で国債が暴落、政権が崩壊した英国と国債市場が無風の日本との“明暗”は、中央銀行が市場の価格発見機能を最大限に尊重しているかどうかの差だ。日銀が国債金利を抑える日本の財政はいずれ厳しい暗転の局面を迎えるだろう。

マイナス金利や長短金利操作についての世界の中央銀行の評価は必ずしも良くはない。貸出金利低下の効果がはっきりしないことや、財政ファイナンス政策に陥る懸念があるからだ。日銀の「緩和維持」で日本経済が好転するかは疑問だ。

インフレ圧力の高まりで欧米の中央銀行が超緩和政策からの「正常化」にかじを切ったが、取り残された日本銀行は円安加速やウクライナ問題による資源価格高騰のほかにも「緩和維持リスク」を抱える。

インフレ懸念の強まりからFedが金融政策正常化に動くなかで日本銀行は「出口戦略」を封印した状況だ。だが内外金利差拡大で円安が加速すれば隠れていた深刻なリスクが一気に表面化する。

テーパリング開始を決めたFedだが、2%物価目標を超えた後も一定期間、緩和を続けるとしており、インフレ加速の対応が手遅れになる懸念もある。手綱さばき次第では日本の政策運営も試練を迎える。

世界をコロナ禍が覆って1年が経つ。繰り返す危機に、国としていかに対応するか。その際、政府と中央銀行はどのような役割分担で危機対応を行うべきか。欧米各国とわが国との間では、この考え方に大きな違いがある。その違いが何をもたらすのかをみてみよう。
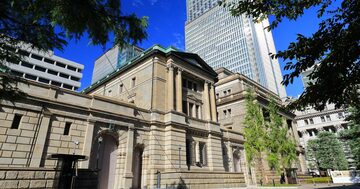
FedやECB、イングランド銀行などの姿勢や金融政策運営は、実際のところ、日銀とはかなり違う。日銀による“事実上の財政ファイナンス”に乗じて、世界最悪の財政事情にある日本がこのまま放漫財政を継続すれば、いかなる事態に陥ることになるのか。徹底分析する。

ECBは各国政府から独立した立場を守りつつ、どのような金融政策運営を行って、ギリシャを除くユーロ圏の重債務国の財政破綻を回避し、欧州債務危機を切り抜けたのか。その背後では、いかなる意思決定の枠組みがあったのか。日銀との違いを検証してみよう。

第3回
黒田日銀総裁はこれまで、出口戦略について何度問われても「時期尚早」の一点張りだった。一方英国では、大規模な量的緩和を行う際に中央銀行が債務超過に陥ることを最初から見通し、国としての対応をしっかり講じている。日本と英国の違いとは、何だろうか。

第2回
リーマン・ショック後に「ゼロ金利制約」に直面したFed(米連邦準備制度)は、どのような姿勢で未知の金融政策運営に取り組んでいったのか。それは、日銀の政策運営とはかなり異なるものだった。その違いが、米国と日本の経済・財政に及ぼす影響とは何だろうか。

第1回
日銀は異次元緩和を続け、現在に至るまで“出口”に関する説明を公に行ったことがない。ここにきてマイナス金利まで導入し、国債やETFを大量に買い続けている。そうした状況は、欧米の主要中央銀行も同様だ。彼らの金融政策運営は、いつから様変わりしてしまったのか。そのことは、わが国を含む各国経済の今後のありように、どのような影響やリスクを及ぼすのか。

第5回
安倍政権2年間の財政運営を評価すると、日銀による巨額の国債買入れで財政規律は緩み、歳出改革は行われず、政府債務残高は増加。消費増税の先送りと日銀頼みの財政運営が続くとすれば、将来世代へのツケ回しの規模は大きくなるばかりだろう。

第405回
わが国が国債残高の増加を止めるには、40兆円規模の財政収支改善を実現する必要がある。今回は、この「気が遠くなるような規模」の財政構造改革を実現するための選択肢として、いかなる方向性があり得るのかを考えたい。
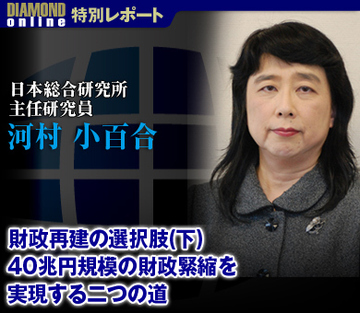
第403回
安倍政権は国民の「痛み」を伴う構造問題への取り組みが遅れている。その最たるものが財政問題だ。すでに、国際機関は厳しい財政緊縮が必要だと診断しているにもかかわらず、財政運営はいまだ拡張路線を採っている。
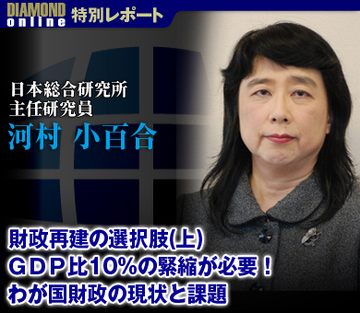
第363回
日本の政府債務が1000兆円を超えた。「日本は国債をほとんど国内で消化しているのだから大丈夫」という議論もあるが、本当だろうか。実は第二次世界大戦終戦直後にわが国は国内デフォルトを実施した。その実態をつぶさにみる。

第8回
異次元金融緩和がスタートして2ヵ月が経つ。足もと、国債市場、株式市場も乱高下しているが、これは何を意味しているのか。これからわが国に求められる財政・金融政策運営について考えたい。
