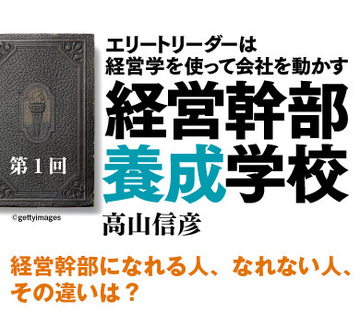高山信彦
第6回
ポーターの経営学を使える武器にする
ポーターの理論は、他社と差別化するための有益な示唆を与えてくれる。特に『競争優位の戦略』第7章は業界細分化と競争優位について書かれていてとても重要だ。ポーターは、業界セグメントごとに5つの競争要因の力関係は異なるという。つまり、「業界を細分化したあとの状態」を「業界」と読み替えて、初めて『競争優位の戦略』は実践の書になるのだ。
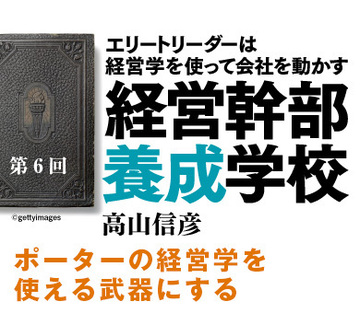
第5回
経営学には「4つ」の種類がある(後篇)
経営学には基本となる4つの戦略論の学派がある。ポジショニングアプローチ、資源アプローチ、ゲームアプローチ、学習アプローチの4つだ。ゲームアプローチは、競争相手との打ち手の応酬に重きを置く考え方で、学習アプローチは、事業活動を通じて蓄積される自社の経営資源を将来の事業活動に活かす考え方である。
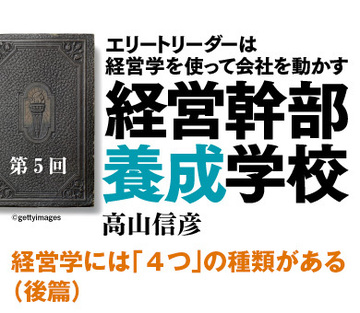
第4回
経営学には「4つ」の種類がある(前篇)
経営学には基本となる4つの戦略論の学派がある。ポジショニングアプローチ、資源アプローチ、学習アプローチ、ゲームアプローチの4つである。ただ、実際のビジネスで応用するときには、この4つのどれかを選ぶというよりも、4つの視点から総合的に考えて自社や自部門を見つめ、バランスで戦略を考えていくべきである。

第3回
リーダーには「抽象化・概念化」の能力が必須
会社や組織では階層が上に行けば行くほど、より概念化・抽象化して考える能力が求められる。それはリーダーや経営幹部になるための必要条件ともいえる。概念化・抽象化の意義を理解すると、経営学を実務に適用できるようになるだけでなく、他産業の事例からも有益なヒントが得られるようになる。
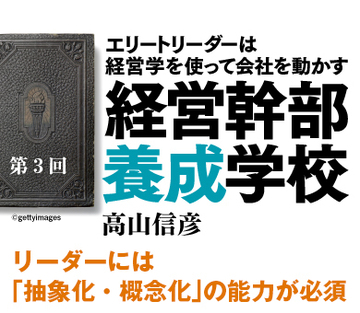
第2回
経営の全体像を頭にインプットする
東レ、JR西日本、みずほフィナンシャルグループなど、人材育成と事業変革を同時に達成する「伝説の研修」で多くの幹部人材を輩出してきたカリスマ講師が、次世代の幹部人材になるための要諦を説く連載。経営学を学ぶうえで、これだけは欠かせないという要点とは何か?
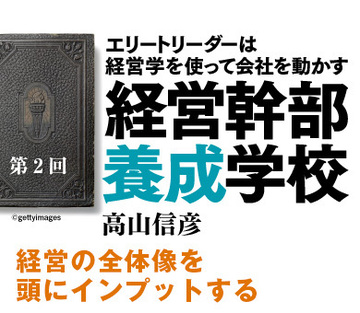
第1回
経営幹部になれる人、なれない人、その違いは?
もっと昇進昇格したい、経営幹部になりたいと思うビジネスパーソンは多い。しかし現実には、経営幹部になれる人と、なれない人がいるのも事実。では、その2つを分けるものとは何か? 「伝説の研修」で数多くの幹部人材を輩出してきたカリスマ講師の高山氏は、「戦略策定力」と「戦略実行力」の2つがカギだという――。