榎本博明
勉強ができる子どもはどのように学んでいるのか? 前回は「アウトプットする」ことで理解が深まることを紹介しました。今回は、理解を促進する学習方法に加え、算数・理科・国語・社会などあらゆる学科の内容を理解するために欠かせない「抽象的な概念」を、子どもが順を追って身に付けるステップについて説明します。
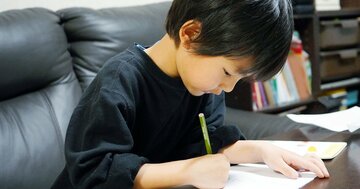
同じ時間机に向かっていても、しっかり学習内容を理解できる子と、そうでない子がいます。勉強ができる子どもはどんな風に学んでいるのか、気になったことはありませんか?勉強できる子、理解が早い子は無意識に「アウトプット」を行っています。アウトプットできる勉強法とはどのようなものなのか。大人にも有効な“学び方“とは?
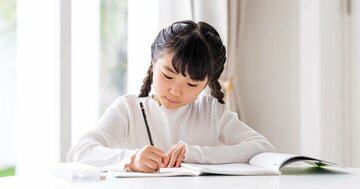
何があっても常に前向きに受け止め、力強く苦境を切り拓いていく人がいる。その一方で、そこまで悲惨な目に遭ったわけでもないのに、後ろ向きなことばかり言って、状況を好転させようといった動きが見られない人もいる。そこに「生きづらさ」から解放されるためのヒントがある。

帰宅したら机に向かって勉強する。本を読む。毎日ピアノの練習をする……頑張れる子、努力ができる子というのも一種の才能です。日々の努力を続けられない人は「意思が弱いからだ」と思いがちですが、実は、努力を継続するためには、意思の力よりももっと大切なものがあるのです。

ダイエットのために、甘いモノを控えて運動をする。毎日予習復習をすれば成績は上がる……「こうすればうまくいく」と頭では分かっていても、なかなか実行に移せないのはなぜなのでしょうか。目標達成のために必要な行動ができる大人は、子どもの頃にある感覚を身に付けているといいます。

社会に出てうまくやっていくには、子どもの頃のIQが鍵を握ると考えている人は多いと思います。しかしIQは遺伝によって決定されている部分が多いため、教育や本人の努力ではどうにもならない面が強いのです。実際には、社会に適応し活躍するために、IQよりももっと大切な能力があり、しかもそれは訓練で十分高められるといいます。その能力とは……?

気分が沈みがちでうつ傾向の強い人は、仕事でも人間関係でもミスやトラブルを生じがちだと言われる。「うつで仕事がうまくいかない」と嘆く声もよく聞く。なぜ、うつ傾向になると仕事がうまくいかなくなるのだろうか? 実は、うつ傾向と問題解決能力との間には密接な関係があることが分かっているのだ。

愚痴の多い人は、けっして嫌なことばかりを経験しているのではなく、良いことも経験しているのに、嫌なことばかり思い出してしまう心のクセを身につけている。そのことは前回説明したが、これは落ち込みやすい人にもあてはまる。落ち込みやすい自分を変えたい。そう思う人は、記憶とのつき合い方を変える必要がある。そこを変えるだけで、落ち込みにくい自分に生まれ変わることができるのだ。

スマートフォンに依存している人たちが、特にハマっているのがSNSだ。友人がどこで何をしているのかを常に知りたくなり、転職・結婚・出産といった自分のライフステージの変化も欠かさず投稿したくなる。自分の投稿に「いいね!」が少なかったり、友人からの返信が遅かったりすると不安になり、頻繁にスマホを見てしまう。友人と自分を比べて落ち込んだり、逆に優越感に浸ったりすることもある。そんな心理状態は、どのようにして作り出されるのか。どうすればSNS依存から脱却できるのか。心理学博士の筆者が詳しく解説する。

何かと気分が沈みがちで、仕事へのモチベーションも上がらない。いつも前向きに頑張っている同僚と話すと、うらやましいと同時に、なぜあんなふうに気分良くしていられるのか不思議でならない。そんな疑問を口にする人がいる。実は、そこには記憶が深く関係しているのである。

子どもの読書習慣は、単に学力だけでなく、社会性や意欲・関心などさまざまな能力に関係があり、成人後まで影響することが分かっています。しかし親が子どもに「本を読みなさい」と口で言っても、それで素直に言うことを聞く子どもはあまりいないもの。読書をする子どもに育てるために、「親が言う」より効果的な方法とは?

「血は争えない」とはよく言われる言葉です。わが子の成績を見て「自分の子だからなぁ」と思うこともあるでしょう。しかし、子どもの成績は本当に遺伝だけで決まるのでしょうか?世代間伝達には、遺伝のほかにもう一つ重要な要因があり、それは親の工夫次第でどうにでもなるものです。
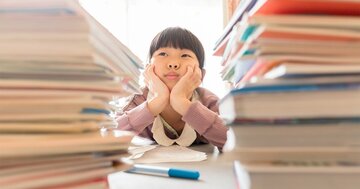
子どもの成績は、常に親の心配事であり、悩みのタネになります。とはいえ、「勉強しなさい」といって、素直に勉強する子どもはめったにいないのが現実です。ならば、親はどうすればいいのでしょうか?

人生のどの時点において教育にお金をかけるのが効果的か?親ならきっと知りたいことなのではないでしょうか。幼児教育に力を入れると、成長したあとでどれくらい有効なのか。また、幼児期に読書習慣を身に付けた子どもは、成長したあと人生において「成功」できるのか?そんな実験の結果を紹介します。

自己肯定感の低さに悩みがちな人は、いかにも自己肯定感が高そうな人を見ると、圧倒され、「それに比べて自分は……」と落ち込んでしまいがちだ。しかし、見た目で自信満々に見える人の中には、実は自己肯定感の低い人や実力の乏しい人も結構いるものだ。本当に自己肯定感が高い人とはどんな人なのか。そして自己肯定感を高めるためにはどうしたらよいのだろうか?

読書は子どもの成長に良い影響を与えるもの。本を読む子になってほしい……親はそう願っているのに、当の子どもはゲームや動画は見るけれど、本なんてまったく読まない……そういう家庭は多いのではないでしょうか。なぜ「本を読みなさい」と言っても言うことを聞かないのか、どうやったら子どもが本を読むようになるのかについて考えてみましょう。

自己肯定感が低いことを悩んでいる人は非常に多く、「こうすれば自己肯定感が高まる」と説く本が人気だ。なかには、一瞬で自己肯定感が高まる方法があるとして、自己暗示のかけ方を教えるものまである。しかし、本当にそれで自己肯定感が高まるのだろうか。今回は、自己肯定感とはどのようにして高まっていくのかについて考えてみたい。

人事の重要な仕事として、従業員が持つ潜在的な能力を最大限に発揮できるようにサポートするということがある。いわゆる人材育成・能力開発である。昨今はポジティブな心構えを推奨する風潮があるが、今回はその危うさについて見ていきたい。

人事部門の重要な仕事の一つに、モチベーションマネジメントがある。同じ能力でも、モチベーションによって成果が大きく違ってくる。成果を出せる組織にしていくには、社員のモチベーションマネジメントが欠かせない。モチベーションというのは、心の問題であり、まさに心理学の守備範囲といえる。今回は人事心理学の視点から、社員のモチベーションを高める職務特性について考えてみたい。

自己肯定感の低さに悩む人が非常に多くなっているようだ。欧米人の自己肯定感の高さと比べて日本人の自己肯定感の低さが際立っているという国際比較データがあり、「日本人も欧米人を見習ってもっと自己肯定感を高めないといけない」と言われたりするからだろう。しかし、私たち日本人の自己肯定感は本当に低いのだろうか。そこを検討してみる必要がある。
