榎本博明
定年後の趣味が見つからない…焦って「趣味偽装」に走る人が見落としていること
数年後に迫る定年を意識する年齢になると、定年後はどうやって過ごそうかと、あれこれ思いをめぐらすようになる。その際、何をやろうかとワクワク感に浸る人よりも、何をしたらいいんだろうと悩んでしまう人の方が多いようだ。そんな人たちの心の内を覗いてみよう。何かヒントが見つかるかもしれない。

定年後「仕事ができる人」ほど途方に暮れるワケ…心理学博士が幸せな老後の過ごし方を提案
長年勤めてきた会社生活から引退するとなると、誰でも感傷的な気分になりがちだ。通う場がなくなることに戸惑いを感じる人も少なくないだろう。しかし、毎日職場に通わなければならなかったこれまでの人生で、「いつか自由な身になりたい」と思うこともあったのではないか。それが現実になるのである。手に入る自由をどう楽しむか、そんな前向きの気持ちで、定年後の過ごし方を考えておくべきではないだろうか。

「本を読む子は頭がいい」「家にたくさん本がある子は頭がいい」は本当?
「読書好きな子どもは学校の成績もいい」とはよく言われることだが、そもそもなぜ、読書をすることが成績向上につながるのだろうか。また、「本は読んでいないけど、毎日チャットやSNSでスマホの文字をたくさん読んでいる」という人は多いが、スマホでたくさんの文字を読むことは、読書の代替にはならないという。それはなぜなのだろうか?

なぜテストの点数が悪い子に限って「自己採点は自信満々」なのか?
テストが終わったあと、「バッチリできたよ!」と自信満々な子どもよりも、「良くできなかったかも……」と落ち込む子どものほうが成績が良い、ということがある。不思議だと思うかもしれないが、これは珍しいことではない。成績がなかなか上がらない子どもの特徴の一つに「自分の理解度や成績を過大評価する」という傾向がある。このバイアスを改善するにはどうしたら良いのだろうか?
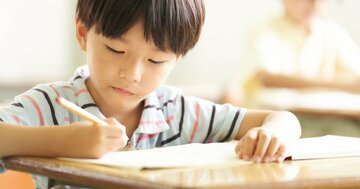
定年で肩書・所属がなくなり「自分を見失う人」と「生き生きできる人」は何が違う?
定年が数年後に近づいてくると、多くの人は不安に駆られる。これまでは毎日やることがあったし、通う場所があったけれど、それがなくなったらどんな生活になるのだろうと考え込んでしまう。毎日会社に行って仕事をするというのは、ある意味“思考停止状態”でも生きて行かれるということだからだ。「定年後、どうやって生きていこう?」という不安は、どうやったら乗り越えることができるのだろうか。

「待てたらお菓子をもう1個」で我慢できずに食べてしまった保育園児の末路
「勉強ができるようになりたい」と願う人は多いだろう。持って生まれた知能が素晴らしくても、それだけでは勉強ができるようにはならない。知能の発達に加え、非認知能力を高めることが必要になる。非認知能力の中核である「自己コントロール力」とは、具体的にはどのような能力なのだろうか。

親は頭がいいのに「子どもは勉強ができない」そんな親子が珍しくない当然の理由
「勉強ができるようになりたい」~学生の頃、一度はそう思ったことがあるのではないだろうか。どうやったら勉強ができるようになるのか。親ゆずりの知能が高ければいいのか?しかし、知能が高くても「学ぶ力」がなければ勉強ができるようにはならないのだ。学ぶ力とは何か、三つの側面から考えてみたい。

仕事ができない人ほど「なぜか自己評価が高い」納得の理由とは?
仕事ができるようになりたいというのは、だれもが思うことであろう。だが、漠然とそう思うだけでは、いつまでたってもできるようにならない。仕事ができる人は、あるコツを身に付けているのだ。仕事ができる人が身に付けているコツとは? そして、仕事ができない人をできるように育てるには、どうしたらよいのだろうか?

定年後の第2の人生、どうしたら…博士の言葉に「退職不安」が吹き飛んだ
定年退職を意識する年齢になると、気になってくるのが「第二の人生」という言葉だ。これまでは他人事だったため、「定年後は第二の人生になる」と言われても「そんなものか」と軽く考えていた人も、いざ自分自身が定年退職を意識するようになると、そうはいかない。第二の人生がどんな感じなのか、イメージがまったく湧かない。そこで焦り始める……そんな人が多いようだ。
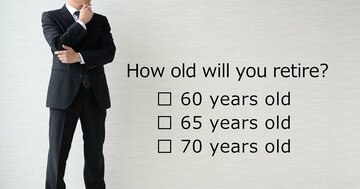
「健康寿命は思ったより短い」と焦る人に考えてほしい“定年退職”の後のこと
人間、50代くらいになると、人生の残り時間が気になるようになってくる。仕事をするのはあと何年、平均寿命まであと何年……。平均寿命が長い日本では、定年退職をした後もまだまだ人生は続く、と考えている人は多いだろう。しかし、元気に自由に動き回れる「健康寿命」を考えると、実は残された時間はそれほど多くないことに気付くはずだ。

定年後に「後悔する人」と「イキイキする人」は何が違うのか?
定年を意識する50代、そして定年延長や再雇用でひとまず退職は先延ばしになったものの、遠からず訪れる退職時のことを思い、不安に苛まれる60代……「人生100年時代」などと言われ、歳を取っても働くのが当たり前とされるようになった昨今、私たちはこうした退職不安とどう向き合えばいいのか。その受け止め方によって、60代以降の新たな人生にイキイキと前向きに踏み出す人と、諦めや後悔の日々を過ごす人に分かれる。

あらゆる業界でマニュアル化が積極的に進められている。業務効率化やミスの防止のため、今や企業にとっては必須の武器となっている。メリットが大きい半面、マニュアルに頼ることには大きな落とし穴があることを知っておく必要がある。今回は、マニュアル化に伴うリスクについて考えてみたい。

ビジネスをスムーズに進めるには、交渉力を高める必要がある。自分は交渉力が弱点になっているという人と話すと、無意識のうちの働く心理がその弱点につながっていることが少なくない。そこを意識することで、交渉力は格段にアップする。今回は、無意識のうちに働く心理への気付きを促すことにしたい。

「周りに比べて、自分はダメだ」「常に他人の目や評価が気になって自信が持てない」こうした気持ちにさいなまれがちで、自己肯定感の低さに悩む人は少なくありません。自己肯定感を高めるにはどうしたらいいのか。その鍵となるのが「自己効力感」です。

「自己肯定感」という言葉が世の中に広まり、それを高めることが大事だなどと言われるため、「自分は自己肯定感が低い」と悩む人が非常に多い。そんな人たちをターゲットにして、自己肯定感を高めるための処方せんが出回るようになった。しかし、そのようなものに安易に頼ると、見せかけの自己肯定感は高まっても、成長が止まってしまう恐れがある。今回は、自己肯定感と成長の関係について解き明かしてみたい。

“傷つきやすい上司”は厄介なものだ。すぐに不機嫌になったり、「どうせ自分は……」といった感じでいじけたりしてしまう。部下としては「上司にはもっと堂々としていてほしい」と思うものだが、実は、上司というのはとても傷つきやすい立場なのだ。今回は、傷付きやすい上司の心理メカニズムを踏まえて、上手に対応する方法を考えてみよう。

近頃はちょっとしたことで傷つきやすい若者がいて扱いにくくて困るといった声を多くの職場で耳にするようになった。しかしその一方で、これでは部下が傷つくのも当然と思わざるを得ない、横暴な上司が多くの職場にいるのもまた事実である。今回は、横暴な上司にメンタルをやられないための対処法について考えてみたい。

終身雇用制度が大きく変化して転職が容易になったこともあり、自分らしいキャリアづくりに熱心な最近の若者たち。しかし熱心になればなるほど、迷いや焦りも強くなるようだ。読者の中には、そんな若手社員たちの相談に乗る立場にある人も多いと思う。もし若手社員の相談に乗る際には、ぜひ青年期の出口でもがいている心理について分かっておいてほしい。

仕事生活でもプライベートでも、ストレスを感じることがあるものだ。そうした精神状態を放置していると、モチベーションが低下して仕事面で停滞したり、プライベートな人間関係を悪化させたりしやすい。そこで大切なのは日頃からの心のセルフケアだ。今回は、その方法の一つとして、懐かしい記憶との触れ合いの効果について解説したい。
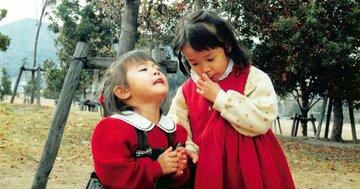
過去に縛られて、後ろ向きの人生から抜け出せない……そういう人には、過去の記憶を書き換えることをおすすめします。「記憶の書き換えなんてできるわけがない」そう思うかもしれませんが、心理学的手法を用いることでそれが可能になるのです。「消してしまいたい過去」を抱える人は、ぜひこの方法を試してみてください。
