榎本博明
読書をしない子どもが増えている。その結果として、文章を正しく読めず、知識を身につけられない、成長しても学力が伸びない学生が増えている。『読書をする子は○○がすごい』(日経プレミアシリーズ)の著者・榎本博明氏は、子どもが本を読む習慣を身につけることの重要性と、国語教育の変化に警鐘を鳴らす。

第47回
規則を順守するのは大切なことではあるが、大局的に見たらどうでもいいようなことにこだわる人物がいる。「急がないと商機を逃す」というような場合ですら、例外を認めず、通常の手順を踏むことを求めてくる。どうにも融通が利かない。「どうしてもっと柔軟に判断できないんだ!」とイライラするが、相手の言っていることは間違ってはいない。こうした人物を動かすにはどうしたらよいのだろうか。

第46回
近頃、健全な組織にするために、何でも会議にかけて、みんなで検討して決めようとする組織運営者が多いようだ。しかし、そこには大きな落とし穴がある。実際、不祥事が発覚したり、方針転換を誤ったりしたとき、それは誰かの独断で行われたというのでなく、多くの場合は会議にかけられ正式な手順を踏んで決定されているのだ。なぜ「みんなで話し合って決める」のが危ういのか。

第45回
科学的であることを標榜(ひょうぼう)し、数字をもとにした人事評価がもてはやされている。だが、数値化すれば科学的になるというのは幻想だ。そこには大きな落とし穴がある。厳しい数値目標が不祥事を引き起こすといった事例には事欠かないが、そのような意味でなくとも、数字にとらわれ、数字を信奉することが組織の不利益につながることは多い。

第44回
会議で慎重に決めたはずなのに判断を誤ってしまい、それが組織にとって致命的なものになることがある。なぜ慎重に判断したはずなのに誤ってしまうのか。そのようなケースで問題となるのが属人思考だ。組織としての判断ミスをなくすには、この属人思考について知っておく必要がある。

勘違いや早とちりが多く、ミスを繰り返すようなコミュニケーションがあまりうまくいかない人には「聴く力」に問題があるかもしれない。だが、そういう人にイライラする側にも、周囲の人たちに同じような思いをさせている可能性もある。そこで、今回は聴いてるつもりの病理傾向について考えたい。

第42回
いろいろ工夫して仕上げ、「これなら大丈夫」と自信をもって提出した企画書が通らない、というのはよくあることだ。その一方で、提出した企画書はほとんど採用されるという人もいる。発想力の違いと言ってしまえばそれまでだが、どうもそこにはちょっとしたコツがあるようだ。

経営者や管理職は、従業員みんなに全力でやる気を出してほしいと願うものだが、実際には最低限の義務を果たすような働き方をしたり、惰性に任せて働いたりする者もいて、ヤキモキする。では、どうしたらやる気がみなぎる職場にできるのか。その鍵を握るのが人事評価システムである。

第40回
じっくり人材を育てる余裕のない時代になった。そこで威力を発揮しているのが仕事のマニュアル化だ。マニュアルがあることで、だれがやっても一定の仕事の質が保たれる。だが、そうした便利さがある半面、マニュアル化には意外な落とし穴があるのだ。
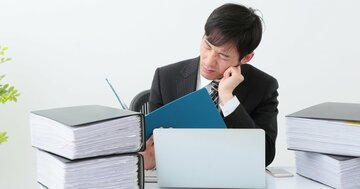
第39回
リーダーシップの取り方をずっと変えない管理職や経営者がいる。昔はうまくリーダーシップが取れていたのに、なぜか最近メンバーとうまくいかないという人は、方法を昔から変えていないということが問題かもしれない。組織をうまく機能させるには、リーダーシップの取り方を適宜切り替えていく必要がある。

どの組織でも、誰をリーダーに選ぶか頭を悩ますものである。仕事ができる人物が必ずしもリーダーにふさわしい行動を取れるとは限らないからだ。そうかといって、リーダー候補が複数いるとして、仕事能力で明らかに劣る人物の方をリーダーに指名しても、仕事ができる方の人物のモチベーションが下がれば組織として大きな損失だし、不満が出てきてややこしいことにもなりかねない。望ましいのは仕事能力で優る人物にリーダーにふさわしい行動を身につけてもらうことである。今回は、リーダーとして力を発揮している人たちが身につけている心理機能について見ていきたい。

今、教育の現場では、あらゆる学習において、社会に出てからの実用性を重視する実学志向が強まっている。だが、基礎知識や教養、物事を深く考える習慣を身につけさせないのであれば、先の読めない変化の激しい時代を柔軟に生きることは困難だ。『教育現場は困ってる――薄っぺらな大人をつくる実学志向』(平凡社新書)の著者・榎本博明氏は、学校教育の在り方に警鐘を鳴らす。今回はシリーズ5回目で、「実学重視に走る教育の危うさ」について問題提起する。

えこひいきする上司に苦しめられたという人は少なくない。「だから自分はそんなことはしたくない」と言っていた人が、いつの間にか「えこひいき上司」になっていることがある。なぜそんなことになってしまうのか。そこには上司自身にもわからない無意識の心理過程が働いている。それを自覚することが、人事評価のえこひいきをなくすための第一歩となる。

今、教育の現場では、あらゆる学習において、社会に出てからの実用性を重視する実学志向が強まっている。だが、基礎知識や教養、物事を深く考える習慣を身につけさせないのであれば、先の読めない変化の激しい時代を柔軟に生きることは困難だ。『教育現場は困ってる――薄っぺらな大人をつくる実学志向』(平凡社新書)の著者・榎本博明氏は、学校教育の在り方に警鐘を鳴らす。今回はシリーズ4回目で、「欧米に追従する対話的学習」について問題提起する。

今、教育の現場では、あらゆる学習において、社会に出てからの実用性を重視する実学志向が強まっている。だが、基礎知識や教養、物事を深く考える習慣を身につけさせないのであれば、先の読めない変化の激しい時代を柔軟に生きることは困難だ。『教育現場は困ってる――薄っぺらな大人をつくる実学志向』(平凡社新書)の著者・榎本博明氏は、学校教育の在り方に警鐘を鳴らす。今回はシリーズ3回目で、「主体的に学習に取り組む態度」の評価について問題提起する。

2
今、教育の現場では、あらゆる学習において、社会に出てからの実用性を重視する実学志向が強まっている。だが、基礎知識や教養、物事を深く考える習慣を身につけさせないのであれば、先の読めない変化の激しい時代を柔軟に生きることは困難だ。『教育現場は困ってる――薄っぺらな大人をつくる実学志向』(平凡社新書)の著者・榎本博明氏は、学校教育の在り方に警鐘を鳴らす。今回はシリーズ2回目で、日本の教育界が推奨してきた「アクティブ・ラーニング」について問題提起する。

今、教育の現場では、あらゆる学習において、社会に出てからの実用性を重視する実学志向が強まっている。だが、基礎知識や教養、物事を深く考える習慣を身につけさせないのであれば、先の読めない変化の激しい時代を柔軟に生きることは困難だ。『教育現場は困ってる――薄っぺらな大人をつくる実学志向』(平凡社新書)の著者・榎本博明氏は、学校教育の在り方に警鐘を鳴らす。

「ポジティブなことは良いが、どうもポジティブすぎる人は仕事ができないような気がする。むしろ心配性の人の方が、ミスが少ないと感じる。一体どうしてだろう?」。そのような疑問を口にする経営者がいる。実は、そこには非常に鋭い洞察が含まれている。意外かもしれないが、その不安のなさが成長の妨げになっているのだ。

多くの人が在宅勤務を強いられるようになって約2カ月がたつ。この間、心身の不調や家族間のいさかいによるストレスを訴える人たちが目立ち、「コロナうつ」という言葉も生まれた。緊急事態宣言がようやく解除されたものの、在宅勤務がいきなりなくなるわけではないし、在宅勤務を部分的に取り入れようとする企業も出てきている。在宅勤務を快適に続けるためにはどうすればいいのか。
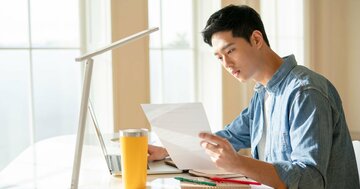
第34回
これまで当たり前のように毎日通勤していたのに、新型コロナにより在宅勤務を強いられ、心身の不調を自覚する人たちが増えている。こうした中で、「コロナうつ」という言葉も使われるようになった。新型コロナの感染はいまだ終息する気配はなく、在宅勤務はまだまだ続く可能性が高い。心身の不調を防ぐためにはどうすればいいのか。
