榎本博明
第18回
経営者たちの会で講演をしていると、「従業員の質が落ちている」「モチベーションが上がらなくて困っている」といった声を耳にすることが少なくない。そこで今回は、どうすれば従業員たちのやる気を引き出せる職場になるのか、事例を交えて紹介したい。

第17回
皆さんの職場でも経営者に限らず、その部署の中心人物の暴走によって組織を牛耳られてしまい、仕事の進め方、意思決定の誤りなどで悩まされているビジネスパーソンも少なくないだろう。そこで今回はそんな上司の暴走を止めるために、どんな方法がリスクを回避できるのかについて考えてみたい。

第16回
「感情的な言葉を連発し、敵対勢力を徹底的にこき下ろす」トランプ型の手法が世の中に広がりつつある。そこで今回はトランプ型の手法に左右されやすい人はどんなタイプなのかにスポットをあててみた。これが実は職場と共通する面もあるので、その心理を説き明かしていくことにしよう。

第3回
SNS時代を迎え、ブログ等から自身の出来事や情報を発信しやすくなりました。あるブログの内容が良かったので祝福コメントを入れようとした時、好意的にとらえていない人の書き込みを見て、嫌な気持ちになったことはありませんか?今回はネット社会が生み出す心のひずみについて『ビジネス心理学100本ノック』の著者・榎本博明氏が解説します。

第15回
不祥事報道を見ていると、現場では高品質、低コスト、納期厳守と言われつつも、経営者からの利益追求のプレッシャーもあり、品質が軽視されているようだ。その結果、誠実かつ丁寧な仕事にこだわるといった日本人の働き方が壊されてしまったのである。そこで今回は、日本の組織特有の「みんなで話し合って決める」議決方式について考えてみたい。

第2回
今どきの若い社員を見ていると、「自分の時間を大切にしたい」というドライな人が多いのか、それとも意外にも上司と触れ合いたいという人が多いのか、上司の皆さんは気になるのではないでしょうか。そこで今回は今どきの若者が上司とのかかわりを嫌っているのかどうかについて、『ビジネス心理学100本ノック』の著者・榎本博明氏が解説します。

第1回
職場の慣習、規則などでおかしいと思うと黙っていられない人、チームでやった業績も自分1人でやったかのようにアピールする人…など、「ややこしい人」に悩まされていませんか?心理学博士・榎本博明氏の著書『ビジネス心理学100本ノック』からそうした人たちの心理を分析し、どう対処していけばいいのかを明かします。

第14回
どんな職場にも文句が多い攻撃的な上司(特に中間管理職)はいて、理不尽に叱られたり、難癖を付けられて企画のNGを連発されたりした経験を持つ人は少なくないだろう。そこで、今回は文句が多く攻撃的な上司を3タイプに分け、その特徴と対処法を紹介しよう。

第13回
厳しく叱られることなく、褒められて育った若い世代が新人として入ってくるようになり、厳しいことを言うと、すぐに辞めてしまう。そんな若手の離職を食い止めようと「褒めて育てる」方式を取り入れる企業も出てきている。ところが、この方式を取り入れたものの、特に改善が見られないため、疑問に感じる経営者や管理職も少なくない。

第12回
ちょっと注意しただけで、すぐに辞めてしまう――。若者の育て方について悩んでいる経営者や管理職は少なくない。そこで若者の離職を防ぐために、褒め方の研修を取り入れたところ、今度は管理職から不満の声が…。どう対処するのがいいのだろうか?

第11回
近頃、攻撃的な人に頭を悩ませている方が少なくない。親切心から口にした言葉でさえも反発される。こちらは何も思い当たることがないのに、悪い噂を流される。そんな攻撃的な人が多くの職場にもいる。どう対処すればいいのだろうか。

第10回
このところ、注意したり叱ったりすると傷つきやすい部下に手を焼いて困っているという管理職の悩みが少なくない。「最近の若手はミスを注意しただけで傷つきやすくて困るんだよなあ」といったグチをよく耳にする。みなさんの職場でも、傷つきやすい部下がいて手を焼いていないだろうか。
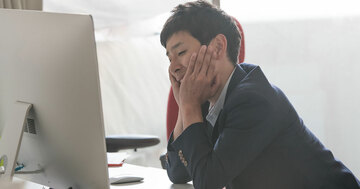
第5回
これまで、会社によくいる「面倒くさい人」のパターンや背後にある心理メカニズムについて紹介してきました。最終回はどんな人を「面倒くさい」と感じるかについて、著者・榎本博明氏が解き明かします。

第4回
皆さんの職場で、持ち上げないと拗ねる人はいませんか?見え見えのお世辞を言う部下ばかりえこひいきする管理職、いちいち褒めてあげないとふてくされる若手社員……。そんな人たちと関わりたくないと思う人は少なくないでしょう。『かかわると面倒くさい人』の著者・榎本博明氏がそうした人たちの心理背景に迫ります。

第3回
いつも謙虚で遠慮がちなのに、接しているとなぜかイライラしてしまう人、「自分はダメだ」と無能さをアピールする人、何をするにも自信がなく躊躇するために勇気づけてフォローしなければならない人……。あなたはこんな人に悩まされていませんか?『かかわると面倒くさい人』の著者・榎本博明氏がそうした人たちの心理構造を説き明かします。

第2回
会議でやたらと好戦的な人はいませんか?意見を述べたり、提案をしたりする時、相手はスイッチが入って戦闘モードになり、「それはどういう意味ですか?」から始まり、うんざりするほど攻撃的な反論が返ってくる――そんなタイプの人です。『かかわると面倒くさい人』の著者・榎本博明氏はそうした人たちの心理を解き明かします。

第9回
管理職の人たちと話すと、部下に対する不満の話には枚挙にいとまがない。だが上司も、自分たちが部下からどのように見られているかを振り返る時があるだろうか。そこで今回は、部下が上司に対してどんな不満を持っているのか、部下がついていきたくなる上司はそうでない上司と一体どこが違うのかについて考えてみたい。

第1回
経費精算の書類を持って行くと、締切時間に1分でも遅れたら受け付けないという経理担当者。取引先から好感触を得て話を進めると、手順を踏まないと認めないという上司。皆さんはこんな細かな規則にこだわる人に悩まされていませんか?『かかわると面倒くさい人』の著者・榎本博明氏がそうした人たちの心理構造を解剖します。

第8回
「最近の若手は不満が多くて、どう対処したらいいのかわからない」と頭を悩ませている経営者や管理職の方々が少なくない。だが当の若手自身も、不満をどう解消したらいいのかわからず、悩み苦しんでいる。今年も新人を職場に迎える時期になったが、迎える側も迎えられる側も、ぜひ「やりたい仕事」病について知ってほしい。
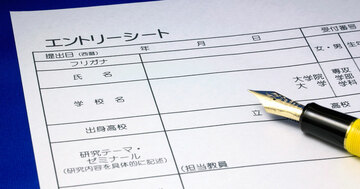
2020年東京オリンピックでの「おもてなし」に向けて、“英語ファースト”の時代が訪れている。「いまの時代、英会話ぐらいできないと」、「英語は早いうちから学んだ方がいい」と言われるが、『その「英語」が子どもをダメにする』(青春出版社)の著者・榎本博明氏は、そんな思い込みが蔓延する英語“偏重”な教育現場に警鐘を鳴らす。
