
河野龍太郎
シリコンバレー銀行破綻に端を発した金融不安は中央銀行による流動性大量供給などで落ち着きつつある。しかし、流動性の供給はインフレ抑制に逆行する。こうした齟齬がなぜ起きたのか、これから何をもたらすのかを検証する。

日本銀行の次期総裁に、経済学者の植田和男氏を起用する人事案が固まった。だが、実は新体制発足前の3月にも、日銀が政策修正に動く可能性は決して否定できない。「植田新総裁」誕生前後のシナリオを大展望した。

次期日本銀行総裁を雨宮正佳副総裁に打診と報道された。2月中には正式な人事案が国会に提示される。次期総裁の下で、13年1月に結ばれた政府・日銀の共同声明が見直される公算は十分にある。金融政策の柔軟化が進み、異次元緩和の修正が進むだろう。しかし、それは金融政策の正常化を意味するものではない。

日本経済の長期停滞をもたらした最大の要因は、企業がもうかってもため込んで、人的資本投資や無形資産投資を怠り、賃上げに消極的だったことにある。では、企業にそうさせた要因は何だったのか。分析・検証する。

欧米主要国ほどではないが、日本国民も物価高に苦しんでいる。しかし、物価の番人たる日本銀行は、安定的な2%インフレ目標の達成が見通せないとして異次元緩和を続ける。黒田東彦日本銀行総裁の最後の賭けともいえるこの金融政策が、財政インフレの引き金を引くことはないのか、検証した。

先進国は自国の国債を安全資産として供給できる。それゆえ、危機の際に中央銀行によるファイナンスで拡張財政を実施できる。長期停滞にあえぐ日本が新興国へと転落していくとき、財政健全化が進んでいないと何が起きるのか。

実質的に9年近くにわたって継続されたアベノミクスには功罪両面がある。功は景気回復の長期化と完全雇用の達成だ。では、罪の部分は何か。それは、超金融緩和と拡張的な財政政策の継続によってもたらされた二つの弊害である。

実は値上げは比較的スムーズに進んでいる。ただ、黒田日本銀行総裁の発言が問題視されたように、家計は値上げを望んでいるわけではない。その原因の一つである円安をもたらす超金融緩和の固定化は、それ以外にもさまざまな弊害をもたらす。

コロナ禍からの回復、ロシアのウクライナ侵攻で世界的にインフレ圧力が高まり、人々の関心が金融政策に向かいつつある。大衆心理の変化がこれまでの金融政策の在り方の見直しを迫ることになるだろう。
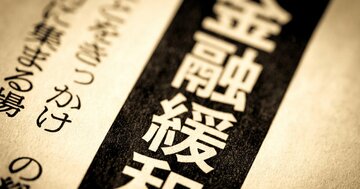
米国もユーロ圏も既に実質GDPはコロナ禍前のピークを上回った。しかし、日本は2022年中も消費増税前に付けたピークを上回れそうにない。そこには大きな構造的問題がある。何が日本経済を停滞させているのか、検証する。

2000年以前は、景気刺激策として財政政策を積極的に活用すべきではないとされていた。民間の資金需要を抑制する恐れがあり、また、長期金利が名目成長率を上回っていたことも背景にあった。しかし、今や名目成長率が長期金利を上回ることが常態となり、主流派経済学の財政政策への評価は一転した。ただ、それは国債バブルの存在ゆえである。
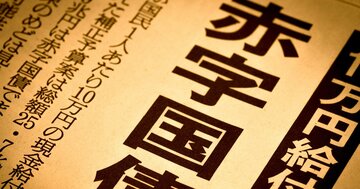
インフレ加速が日本と中国以外では懸念され始めた。米連邦準備制度理事会(FRB)の超金融緩和がもたらした商品相場の高騰が加わり、コロナ禍によるインフレが一時的といえなくなったことが背景だ。ゼロ金利解除、そしてテーパリング(量的緩和縮小)終了のタイミングが早まるリスクが高まるが、大きなジレンマにFRBは直面する。

誰が次期首相でもスタートは高支持率。ただ、コロナ対応の医療体制強化ができなければ短命政権に終わるリスクがある。また、有力候補はいずれもアベノミクスから距離を置く。

巨大テック企業や教育産業への規制を強化したことで中国への投資継続を疑問視する声が上がっている。しかし、テック企業で進む寡占や独占、経済格差が教育格差を通じて固定化する構造などは、先進国でも懸念される現象だ。その是正に切り込む中国の方が長期的成長を実現する公算が大きいかもしれない。

前年の水準がコロナ禍の影響で低かったこともあり、米国の足元の物価上昇率は急上昇している。しかし、長期金利は逆に低下している。それはなぜなのか。物価上昇が一時的なものにとどまると思われること以外にもさまざまな理由がある。その背景を解き明かしていく。

日本企業は2000年代に入り、過剰ストック・債務問題が解決された後もコスト削減を続け、賃金、人的投資を抑制した。その結果、消費は停滞し、国内市場は縮小する連鎖に陥った。旧来のビジネスモデルが通用する海外への依存を高め、利益を上げているものの、生産性は向上していない。この先に見えてくるのは生産性の高さではなく、コストの低さで競争力を維持するしかないジリ貧の姿である。

バイデン政権は1.9兆ドルの米国救済プランを成立させた。大規模な財政出動は一時的には効果を持つが長続きせず、インフレ上昇も一時的なものに終わる。富裕層への所得の偏在は変わらず、所得が増えない低中所得者層は借り入れで消費をまかなうため、大幅な金利上昇には耐えられないだろう。

コロナ禍対策の財政出動の財源はほぼ国債で賄われた。膨らんだ国債の償還財源をいかに賄うべきか。2000年代以降の法人税減税と被用者の社会保険料の引き上げ、アベノミクス下での法人税減税と消費税増税で日本は労働所得への課税を重くしてきた。これが消費低迷の一因ともなった。それゆえ、労働所得への課税を軽減する社会保険料の引き下げと消費税増税の組み合わせで財源を調達すべきと考える。それは事実上の資本課税ともなる。

日本は第3次産業革命といえる、経済社会のデジタル化、グリーン化で世界の中で取り残されている。長期低迷からの魔法のつえはないが、デジタル化、グリーン化に政府、企業が投資をしていくことで、新たな需要を生み出すことはできるはずだ。それは自然利子率や潜在成長率の回復にも寄与する。

主流派の経済学においては、中央銀行が国債を購入し、政府の財政赤字拡大を支える状態が続くと高率のインフレが起きるとされ、それが中央銀行の国債引き受けを禁止する理由だった。しかし、現時点で大幅な財政赤字は高インフレをもたらしてはいない。だからといって弊害がないわけではない。潜在成長率が低下し、金融システムの不安定化への懸念が高まっている。
