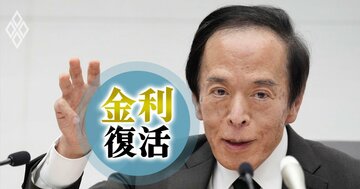Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
日本銀行は基調的な消費者物価上昇率が2026年度までには目標とする2%に達すると見通している。自然利子率をマイナス0.5%とみて利上げの着地点を1.5%と予想する。ただ、利上げをしても日銀による国債購入を減額し、長期金利が市場機能を取り戻さなければ円安傾向に歯止めがかからない恐れがある。(BNPパリバ証券経済調査本部長チーフエコノミスト 河野龍太郎)
利上げの最終着地点は
1.5%か、それ以上
金融政策の見通しを再検討した。従来、筆者は、経済を均衡させる日本の実質中立金利(自然利子率)がマイナス0.5%程度であり、インフレ期待が2%程度に達した際の名目中立金利を1.5%程度だと想定してきた。
今後、政策金利が1.0%まで引き上げられるのは2025年度末ごろ、1.5%程度まで引き上げられるのは26年度末ごろと考えているが、リスクは前倒しかつ上振れである。
日本銀行は、4月展望レポートで、消費者物価の基調的な上昇率は、「(26年度までの)見通し期間後半には『物価安定の目標』と整合的な水準で推移すると考えられる」とした。そうした状況になれば、通常、中央銀行は政策金利を中立水準まで引き上げる。
この点に関し、決定会合後の記者会見で、植田和男総裁がどう発言するのか筆者は注視していたが、「特に(26年度までの)見通し期間の後半について、この通りの姿になっていくということであれば、そこでは私どもの政策金利もほぼ中立金利の近辺にあるという状態にあるんだろうなという展望は持っています」と明確に論じている。
もっとも、「中立金利の水準について、かなりの不確定性があるので、そこは今後分析を深めつつ、最終的といっていいか、到達するところがどの辺かということについて、もう少し知見を深めていきたい」とも述べている。
23年12月の多角的レビューのカンファレンスの際、日銀の企画局は、自然利子率を「マイナス1.0~0.5%程度」としていたが、それを前提にすれば、名目中立金利は1~2.5%ということになり、26年度中には、その範囲内のいずれかの水準まで政策金利が引き上げられることがあり得るということである。
ただ、過去30年間、日本では、事実上のゼロ金利政策が続けられてきた。また、中立金利の推計自体に大きな不確実性を伴う。
こうしたことから、現実の政策運営では、その時々のデータを基に、例えば政策金利を推計値の下限である1%程度まで徐々に引き上げ、その後、大きな悪影響が観測されなければ、中央値近辺まで引き上げるといった戦略が取られるとみられる。
過去30年間の政策金利の上限が0.5%であったことを踏まえると、いったん、0.5%程度まで引き上げ、その後、様子見を行うこともあり得るが、半年に一度のペースなら、点検の余地は十分といえるだろう。