千本木啓文
#45
新型コロナウイルスの感染拡大と米中対立は、東芝の半導体事業などを直撃し、同社は追加のリストラを迫られた。車谷暢昭・東芝社長は、構造改革にめどを付け、「デジタル化」と「環境」で稼ぐ考えを示した。

#44
日立製作所の東原敏昭社長兼CEOは、「2022年までには2桁の営業利益率が見えてくる」と述べ、コロナ禍からの業績回復に自信を見せた。世界的な環境規制の厳格化による自動車のさらなる電動化などが追い風になるという。

東日本大震災後、新型コロナウイルス感染拡大――。危機が日本を襲うたびに使用が停止される製品がある。トイレで手を乾かすハンドドライヤーだ。最大手の三菱電機の販売量は約半分まで低迷している。感染拡大を引き起こす証拠がないため、使用再開を求めたいのがメーカーの本音だが、自粛ムードの中で声を上げられない状況が続く。
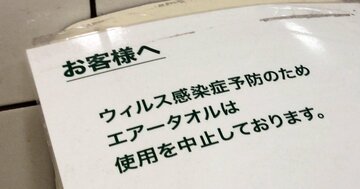
2021年、日立製作所の次期社長レースが大詰めを迎える。経団連会長を務める中西宏明会長が敷き、東原敏昭社長が完成させた改革路線を走るのは、新たな「本流」となった日本人のデジタル人材か、初の外国人トップか――。日立は改革の本気度が試される岐路に立つ。

日立製作所が低迷していた海外の家電事業の株式の6割をトルコの家電メーカー、アルチェリクに売却し、両社で設立する合弁会社で欧州市場などの開拓を目指す。日立は「成長のための前向きな売却だ」と強調するが、収益を改善できるかどうかは新会社のかじを取るアルチェリク次第。日立にとっては視界不良の中での船出になる。

#17
NTTグループの「逆襲」の成否を決める鍵の一つが「技術力」だ。特集『デジタル貧国の覇者 NTT』(全18回)の#17では、基礎研究に強いとされるNTTの実力を、日立製作所やGAFAなどと比較しながら明らかにする。

#13
電話やインターネットといった通信インフラを整備し、日本の経済活動を支えてきたNTT――。その通信網の心臓部が都内某所の地下50メートルにある。最重要の通信インフラ、「とう道」に潜入した。

#12
NTTグループの主要5社(NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ、NTTドコモ、NTTデータ)には、固定電話が強かった時代から続く「序列」が存在する。だが、澤田純・NTT社長が大胆なグループ再編に着手したことで、グループ企業序列が崩れる激変期に差しかかっている。主要各社はいかにして存在意義を発揮していくのか。グループの三男坊であるNTTコミュニケーションズの丸岡亨社長と“外様”であるNTTデータの本間洋社長に聞いた。

#11
NTTグループの主要5社(NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズ、NTTドコモ、NTTデータ)には、固定電話が強かった時代から続いている「序列」が存在する。だが、澤田純・NTT社長が大胆なグループ再編に着手したことで、グループ企業序列が崩れる激変期に差しかかっている。主要各社はいかにして存在意義を発揮していくのか。グループの長男坊であるNTT東の井上福造社長、次男坊であるNTT西の小林充佳社長に聞いた。

#9
NTTによるNTTドコモ完全子会社化を機にドコモ社長に抜てきされた井伊基之氏は、社内の反発も覚悟の上で、旧来のドコモの問題点をずばり指摘した。井伊社長の豪腕ぶりが際立つインタビューをお届けする。

#5
澤田純・NTT社長からの申し出を引き受ける形で、NECがNTTから644億円の出資を受け入れた。NECは旧・電電ファミリーの「長男」的存在である。かつてのように、NTTの“手足”となって生きる決断をしたのか。新野隆・NEC社長を直撃した。
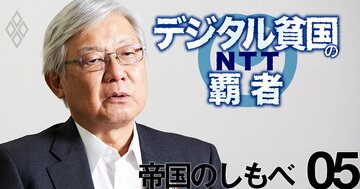
#4
かつて日本には「電電ファミリー」という強固な企業集団があった。国内の通信を独占していた日本電信電話公社(電電公社、現NTT)を“親”、その下請け企業を“子供”とする家族的な企業グループのことだ。
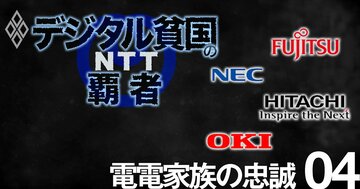
#14
企業の成長のために借り入れをどう活用するかには、経営者の哲学が如実に表れる。日立製作所とソフトバンクグループの財務戦略を比較して、両社が目指す「未来」を考えてみる。

農協が集めた預金を運用する農林中央金庫が、農協への運用益の還元に上限を設けると正式に発表した。現在実施中の「還元率」の引き下げに、「量」の制限を加えて農協への還元を減らす。ダイヤモンド編集部による試算では、全国の農協で総額約1100億円の減益要因となることが分かった。

コロナ禍の“巣ごもり需要”により、家電・ゲーム「バブル」が起きた。ソニーやパナソニックなどが恩恵を受けたが、各社の決算から、メーカー間の格差も浮き彫りになった。

日立製作所が日立建機を売却する方針を固めた。保有する約51%の持ち分の半分を売る方向だ。子会社の全株を譲渡することが多かった日立が、建機株式の4分の1を保有し続ける理由とは。

6年ぶりに米価が下落している。補助金でコメの生産を飼料用米に誘導することで米価を維持する政策の限界があらわになった。農協と自民党は、補助金依存の「重い代償」を払うことになりそうだ。

#6
菅政権がデジタル庁の立ち上げを看板政策に掲げ、バブルに沸き立つITベンダー業界――。しかし、喜んでばかりはいられない。非効率な政府のIT投資が合理化されれば、ベンダーの淘汰は避けられないからだ。

#3
菅政権の誕生でJAグループが戦々恐々としている。イチゴ農家出身で、農協の問題点を理解している菅義偉首相は、近年の農協改革を主導してきた。改革が後退しつつある農協の問題に菅政権がどう切り込むかに迫った。

#4
三菱商事やトヨタ自動車が、スマートシティなど新規事業のパートナーにしたいと秋波を送っている企業がある。NTTグループだ。かつては“お役所組織”の代表格だったNTTグループに提携依頼が殺到している理由に迫った。
