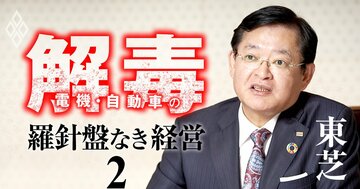千本木啓文
次期首相と目される菅義偉官房長官が推進してきたジビエ(野生鳥獣の食肉)の振興政策に暗雲が垂れ込めている。食肉を供給する鳥獣の捕獲の実績が、政府の目標に対して未達になりそうなのだ。てこ入れを図るには、狩猟を「趣味」から「ビジネス」に転換する必要がある。

コロナ禍で、東芝に唯一残る上場子会社、東芝テックに、分割と事業売却を求める圧力が高まっている。在宅勤務によるペーパーレス化により、プリンターやFAXなどの機能を持つ複合機の売上高が激減しているためだ。複合機の事業をどう整理するかは、東芝本体の成長戦略にも大きな影響を及ぼしそうだ。

JAグループの全国組織の会長選が終わった。JA京都中央会会長の中川泰宏氏は、JA共済連の会長に立候補したが選挙で敗れた。農協組織を私物化する傾向がある中川氏の落選に、農協界では安堵が広がったが、改革派のリーダーが生まれたわけではなく、安心するのは早そうだ。

#4
豊田章男・トヨタ自動車社長は執行役員を削減し、グループ従業員36万人を最高幹部わずか9人で統べる「超」中央集権体制を敷いた。一方、人材が枯渇しているグループ会社に幹部を送り込む「落下傘人事」でグループの統率を図る。トヨタの幹部人事が抱えるリスクに迫る。

#1
トヨタ自動車は7月1日、自動車販売台数で30分の1にすぎない米テスラに時価総額で抜かれた。レガシー企業のトヨタが真似できないテスラの強みとは何か──。トヨタはなぜ企業価値で逆転を許したのかを分析する。

全国584農協を束ねるJA全中の会長選挙で、現職で守旧派の中家徹氏が当選した。これによりJAグループは「組織の老衰」と「改革の時間切れ」という2つの致命的リスクを抱え込むことになった。

#8
農協が集めた預金を運用する農林中央金庫が、運用受託額に上限を設定する方針を固め、農協などと協議を始めたことがダイヤモンド編集部の調べで分かった。マイナス金利政策の長期化で、運用益を農協に還元するビジネスモデルが限界に来ている。農林中金の運用益に依存していた農協の経営はさらに厳しくなりそうだ。

#7
コロナ禍において農協が、保険の推進目標を変えず、職員に前年と同じ契約実績を求めていることが分かった。民間の大手保険会社が訪問営業を自粛し、営業目標を白紙にする中で、農協の保険営業の積極姿勢が際立っている。農協の保険事業は、職員による自爆営業が問題視されてきた。その大元締であるJA共済連による搾取構造を暴く。

#6
JA全農は、連結売上高6.2兆円を誇る国内最大の農業商社で、世界的にも名を知られる。だが一皮むけば、農協の老害リーダーの保身のために、資産を売却したり、農協の赤字事業を押し付けられたりするなど「田舎の論理」に振り回される存在だ。とりわけ長澤豊氏が全農会長になってからガバナンスに緩みが生じている。

#5
JA全中は国からヒト、モノ(法律)、カネ(土地)を与えられて生まれた農水省の“別動隊”だった。戦後は農水省、自民党と「農政トライアングル」を形成して隆盛を誇ったが、今では組織内外から存在意義を問われる事態になっている。全中が凋落した要因を、選挙戦略や幹部人事の失敗からつまびらかにする。

#4
全国の農協を牛耳ってきたJA全中が、JAグループ内で追及の矢面に立たされている。きっかけはITシステム開発の失敗だ。全中は10億円もの損失を穴埋めするための費用負担を農協などに求め、猛反発を受けているのだ。全中の内部資料を基に巨額損失を生んだ原因を追及するとともに、トラブル発生後の情報隠匿の事実にも迫る。

#3
全国584農協を束ねてきたJA全中の会長選挙に立候補したJA徳島中央会会長の中西庄次郎氏は、現職会長が決めた会長の定年延長について再検討する考えを示した。農業振興を最優先に組織を抜本改革するという。中西氏への独占インタビューをお届けする。

#2
京都農協界のドン、中川泰宏氏は、25年間JAグループ京都の頂点に君臨する独裁的リーダーだ。なぜ京都農協界は牛耳られてしまったのか。その秘密は、身内と側近で中枢を固める「鉄の結束」と、JAグループの職員を組織的に動員して行う選挙応援などで得た「政治力」にある。

#1
JAグループの病根は、腐敗した地方組織を制御できないガバナンスの欠如にある。有力者が組織を私物化し、利益誘導を図るのを上部団体が止めないどころか、お先棒を担いでしまうのだ。その象徴として、京都農協界のドン、中川泰宏氏の一族が JAバンク京都信連から2億円の融資を受けて、その資金で行った「地上げ」の実態を暴く。

予告
農協の「病根」を内部資料で暴露、トップ改選でJAグループ重大岐路
584農協を束ねるJA全国組織の会長選挙が幕を開けた。農政改革の後退、金融依存農協のジリ貧、老害リーダーの増殖――。山積する課題を解消できるリーダーが選ばれるのかどうか。JAグループは大きな「岐路」に立っている。農協をむしばむ闇をレポートする。
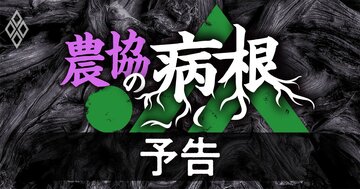
JAグループ選挙で「老害リスク」高まる、“京都のドン”が共済連会長出馬
JA(農協)グループで保険事業を行う、JA共済連の会長に京都農協界のドン、中川泰宏氏が立候補することがダイヤモンド編集部の調べでわかった。JA京都中央会のトップを25年間務める独裁的リーダーである中川氏は、JAグループを牛耳ってきた“政治組織”であるJA全中の中家徹会長に急接近している。両氏が実権を握れば、農協組織の「老衰危機」は決定的になりそうだ。

日立製作所がコロナショック揺れている。脱・ものづくりに向けて事業売却を進めてきたが、本体に残した自動車機器事業が新型コロナウイルスの感染拡大で大打撃を受けるからだ。ホンダ傘下のサプライヤーとの経営統合で売上高が倍増する同事業は、日立の新たなリスクになりそうだ。

羅針盤なき経営(3)
小林喜光・三菱ケミカルホールディングス取締役会長、経済同友会前代表幹事がダイヤモンド編集部の取材に応じ「日本の企業経営には“ファーストペンギン(挑戦する若者)”とアクティビストが必要」と述べ、ポストコロナの時代に改革を進める必要性を強調した。その発言の真意とは。技術に強く論客でも知られる産業界の重鎮が緊急提言する。

#09
日本の電機業界の優等生と見られてきた三菱電機が変調を来している。低収益事業を売却し、競争力の高い事業で安定的に収益を上げてきたが、この勝ちパターンが通用しなくなっているのだ。

羅針盤なき経営(2)
東芝の車谷暢昭社長は、新型コロナウイルスの経営への影響は限定的であり、むしろ東芝のデジタル事業にはチャンスになるとの認識を示した。オフィス面積を現在の半分にすることも視野に働き方改革を進めるという。