千本木啓文
#16
コロナ禍で農産物の産直アプリは急成長を遂げ、農協への不満は高まった。もっとも、食品流通に占めるECの比率はまだ1割に満たないのも事実。中規模以上の農家が稼ぐには、スーパーマーケットなど本丸の需要を攻略する必要がある。農家へのアンケート結果から、儲かる「農産物の買い手(売り先)」をあぶり出す。
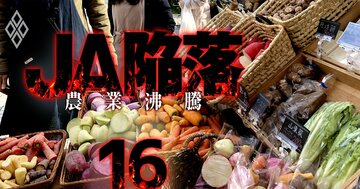
#15
大企業の農業参入が相次いでいるが、その実、有力農家は企業のことを「儲からなければすぐに農業事業から撤退する」と冷めた目で見ているものだ。そんな中、NTT東日本は農家の企業に対する不信感を払拭し、農家支援の事例を着々と増やしている。農業プラットフォーマーの覇権争いに名乗りを上げたNTTの野望とは何か。

#14
地方での農協のパワーはなお強く、大っぴらに批判はしにくいものだ。農家1763人から回答を得たアンケートで明らかになった農家の「地元JAへの不満と本音」を一挙公開する。

#13
大手コンサルや財閥系商社に勤める若者が一流企業というステータスを捨て、チームで農業に参入した。慶應義塾の高校・大学の同級生5人らが“超ハイスピード”で実行している輸出拡大・農業再生プロジェクトの全貌に迫る。

#12
有力農家の投票で決める「未来の農家ランキング」――。今年はコロナ禍でインターネット販売が増えた影響で、小規模・多品目栽培の農家が2位にランクインした。一方、7位の元祖・農業法人は、従来のハウス・露地栽培から植物工場などへと大胆に事業転換していた。農業の未来を見通す“赤丸急上昇ランキング”をお届けする。

#11
ダイヤモンド編集部が選定する大規模・高収益な農業法人「レジェンド農家」たちの進化が止まらない。NTT、三井不動産といった大企業と対等に渡り合い、一気に飛躍する“非連続の成長”を始めた有力農家の強さの秘密を明らかにする。

#10
国内農業の“成長ドライバー”と目される農産物輸出に、新星が現れた。海外における日本産食品の「価格破壊」によって輸出を増やすドン・キホーテだ。200億円の食品輸出額を10年後に3000億円に拡大するドンキの野望を詳報する。

#9
全国にある約580JAにおいて、金融事業の大幅減益への危機感が高まっている。実際に、農協界で絶大な力を持つJA京都中央会会長が「組合員の世代交代とテクノロジーの進化により、減収トレンドに拍車が掛かる」との見通しを語っている。JAグループの金融事業の弱体化を財務データからひもとく。
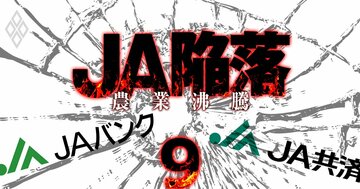
#8
鶏卵生産大手の元代表が農相などに現金を渡した汚職事件で、自民党や農林水産省に激震が走っている。農林族議員は大御所クラスが相次いで失脚、農水省でも序列トップの事務次官まで減給処分を受ける事態になっている。人材が枯渇した農政の惨状をレポートする。
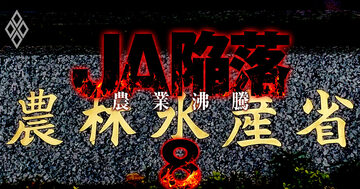
#7
有力農家から選ばれなければ、農協の未来はない。ダイヤモンド編集部が作成した「JA支持率ランキング」上位の農協は、過去の慣習にとらわれず、農家目線で改革を実行していた。農家から支持を得た農協と、農家に見放された農協の実力格差をデータで浮き彫りにする。

有力農家から選ばれなければ、農協の未来はない。ダイヤモンド編集部が作成した「JA支持率ランキング」上位の農協は、過去の慣習にとらわれず、農家目線で改革を実行していた。農家から支持を得た農協と、農家に見放された農協の実力格差をデータで浮き彫りにする。

#6
ダイヤモンド編集部の恒例企画となった「中小キラリ農家ベスト20」――。ずばぬけたビジネスモデルや独自の経営哲学を持つ中小農家をランキングしたものだ。今年の首位はバイオテクノロジーで国産のバナナやコーヒーの栽培を可能にし、その苗を1株3万円で売る「異次元」の農家だ。全国トップクラスの高収益農家に、儲かる秘訣を公開してもらった。

#5
農業の“門外漢”ともいえる三井不動産が農業事業への参入を果たした。収益力や成長性で定評のある農業法人、ワールドファームと資本提携し、日本最大級3000ヘクタールの農場を目指す。農業界のトップ農家とタッグを組めた背景や、三井不動産が目指す農業ビジネスの将来像に迫る。

#4
農産物の流通をはじめとした農業界のプレーヤーの間で、2020年ほど明暗がくっきりと分かれた年はない。優勝劣敗が鮮明となり負け組が脱落していく一方で、企業の農業への投資が活発化し「農業バブル」が到来しているのだ。有力農家をパートナーにして農業で稼ぐ企業の思惑を明らかにする。

#3
保険営業で全国トップ表彰を5回受けた農協職員が、2019年に長崎県下の海で死亡した。共済金の巨額不正流用が発覚した直後だった。不正は組織ぐるみだったとみられるが、JAグループの上部団体は地域農協に責任を押し付け「知らぬ存ぜぬ」で幕引きを図ろうとしている。

#2
日本最大の農業商社、JA全農に対抗する企業の包囲網が完成しつつある。農業の生産から販売までを支援するプラットフォーマーを目指す九つの企業グループへの農家の期待度、各陣営の強み・弱みを全解剖する。

#1
農協の経営悪化が止まらない。ダイヤモンド編集部による独自試算では、2022年度以降に調査対象の504JAのうち2割に当たる96JAが赤字になることが分かった。金融事業の減益と米価低迷が農協にもたらすインパクトを試算した。

#1-1
農協の経営悪化が止まらない。ダイヤモンド編集部による独自試算では、2022年度以降に調査対象の504JAのうち2割に当たる96JAが赤字になることが分かった。金融事業の減益と米価低迷が農協にもたらすインパクトを試算した。

#8
脱炭素への急激なシフトによる「グリーンバブル」は、日立製作所や東芝の命運を左右する転換点となる。両社の電力部門が「名門」復活に向けて描くシナリオに実現可能性があるのかに迫る。

#48
電機メーカーの「優等生」とされた三菱電機が変調を来している。従業員の自殺が相次ぎ、足元では米中対立などで業績が悪化。米テスラが空調に参入するなどゲームチェンジャーも現れた。杉山武史社長に軌道修正の考え方を聞いた。
