
木内登英
高市首相は衆院選公示直前、「消費税の食料品2年間ゼロ」「年度内実施を目指したい」と、消費減税に前のめりで動き出した。野党の多くが減税を掲げる中、選挙対策のにおいが濃厚だが、財源や減収分の社会保障費の穴をどうするかは不明な一方、GDP(国内総生産)押し上げ効果は少ない。国民生活への悪影響は大きく、消費減税は割に合わない政策だ。

日本銀行は12月の金融政策決定会合で政策金利を0.75%に引き上げたが、緩和維持を求める高市政権と物価上昇につながる円安回避で折り合った。今後も高市政権とのあつれきは続くが、日銀は26年9月におおむね中立金利水準の1%まで引き上げるとみられ、金利正常化は終盤戦を迎える。

物価高対策などを柱にした政府の総合経済対策は、減税を含め総額21.3兆円の大規模なものとなったが、財政環境悪化の予測から長期金利は上昇、円安が加速。物価高対策の効果の約半分は円安で相殺される。対策規模を大きくするほど効果が弱まりかねないが、一方、円安進行で日銀の12月追加利上げが現実味を帯びる。

日本銀行が高市政権発足後、最初となった10月金融政策決定会合で政策金利据え置きを決めた。積極財政・緩和維持を主張する政権との対立を回避したとみられるが、利上げをけん制する“政治介入”は、円安・輸入物価上昇を加速させる一方、ドル安志向のトランプ政権への配慮から今後、弱まる可能性があり、次回12月会合では追加利上げが予想される。

米FRBが9月FOMCで6会合ぶりの政策金利0.25%引き下げを決めた。雇用悪化に備え年内のあと2回の利下げを想定するが、トランプ大統領に指名されたばかりのミラン理事は今回0.5%の引き下げを求めるなど、政権の利下げ圧力は続き、市場ではFOMC参加者の見通しを上回るペースで緩和が進むとの見方だ。
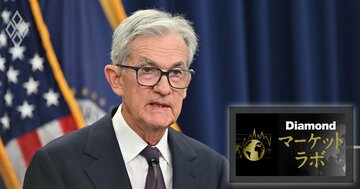
7月米雇用統計の大幅下方修正を受け注目されたジャクソンホール会議での講演でパウエルFRB議長は「9月利下げ」を示唆したが、重要なメッセージは、利下げは経済データを基にFOMCメンバーが独自に判断するということだ。トランプ政権による圧力で金融政策が影響を受けるとの印象は是が非でも避けたい思いがあると考えられる。
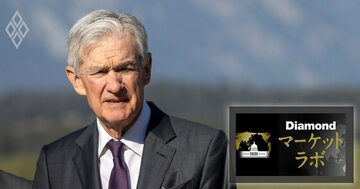
米ドルと価値が連動する「ステーブルコイン」の発行や監視のルールを定めその普及を目指すGENIUS法は米国がデジタル通貨で世界の主導権を取るとともにドルの基軸通貨の地位を維持する狙いだ。だが匿名性が高いため国際決済に使われるほど、ドル覇権の弱体化を招きかねない面がある。

日本銀行は6月の金融政策決定会合でもトランプ関税を念頭に経済や物価動向を巡る「不確実性が極めて高い」として政策金利を据え置いた。不確実性の払拭はトランプ関税の影響が見極められる年後半になると考えられ、利上げ再開は早くても今年12月になる可能性が高い。

トランプ関税政策は米国内でも経済や金融市場への影響が懸念され、行き詰まり感が出ているが、トランプ大統領は貿易などの対外赤字縮小に強い執念を持つ。ドル安政策や安全保障の負担増など、二の矢三の矢を放つ可能性があり、日本には関税見直し交渉の先にも難題が残る。

関税引き上げ政策が金融市場の混乱や各国の強い反発を生む中でトランプ政権は貿易赤字削減の次の一手で「ドル安構想」を抱いていると考えられる。日米財務相会談では言及はなかったというが、今後、米国から日本に円買い介入や利上げを求める圧力が高まる可能性は払拭できない。
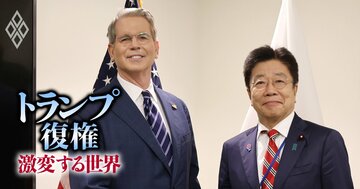
日本銀行は政策金利を据え置いたが、1月の利上げ以降、トランプ関税政策などによる経済減速懸念や野菜、コメなどの価格高騰、実質賃金伸び悩みなど内外環境が大きく変わり、早期の利上げは見通せない状況だ。次の利上げは9月、前倒しされても7月になるだろう。

個人消費の低迷が続くが、高賃上げが予想される今春闘の下でも実質賃金の伸びは2021~23年の▲3.5%の下落を取り戻せずゼロ%程度の状態が続く可能性がある。消費回復にはまずは輸入物価上昇の一因である円安を修正する必要がある。

日本銀行は1月利上げの後、年内に1回、さらに来年半ばごろまでに利上げをして政策金利を1%まで引き上げると予想される。だが懸念は、石破政権が利上げに慎重姿勢の上、米トランプ政権のFRBへの“介入”や関税政策などで対米輸出減少やドル安円高となり利上げ継続の障害となることだ。

日本銀行が12月金融政策決定会合での利上げを、来年春闘に向けた賃上げの持続を確認する必要やトランプ新政権の経済政策の不確実性が強いことを理由に見送った。次回来年1月会合では追加利上げをするとみられるが、気になるのは植田総裁のこのところの発言の振れが大きいことだ。

トランプ第2期政権ではイーロン・マスク氏が「政府効率化省」のトップとして、規制撤廃や公務員のリストラなど政府機関の再構築にあたるという。だがマスク氏がCEOを務める企業経営との利益相反問題の浮上や大幅な政府支出削減となれば米経済や金融市場への影響が懸念される。

総選挙で過半数割れとなった石破政権は野党との政策協力を模索するが、各党が掲げた物価高対策などでの給付金や減税などの公約は一時的な消費刺激効果しか見込めない。政策協力は財政バラマキに陥り、財政悪化で中長期的な成長が阻害される懸念がある。

次の首相となる石破自民党新総裁の経済政策は、賃上げ促進や労働市場改革など岸田政権の政策継続を基本に財政健全化や金融政策の正常化を後押ししてアベノミクス離れを図ると見られる。成長戦略は「地方創生」で地域活性化と少子化対策、東京一極集中是正をパッケージで進める構想だ。

「新しい資本主義」などを掲げた3年間の岸田政権の経済政策は、当初の分配重視から子育て支援や新NISA導入など成長重視に軌道修正したが道半ばであり、一方で財政健全化は進まなかった。功罪入り混じる遺産をどう引き継ぎ、何を変えるか、自民党総裁選では議論が必要だ。

米大統領選でトランプ氏再選となれば、関税引き上げや財政拡張政策などが予想され、「ドル安・株安」が進む可能性が高い。米経済や金融市場は第1期政権時より保護主義的政策への傾倒や財政悪化への脆弱性、不安定要因が強まっており「トランプノミクス2.0」はそのリスクを増幅する懸念がある。

日本人の出生者数や出生率が2023年も過去最低水準を更新することになった原因は、少子化対策が既婚者を対象にした給付の増額が中心になっていることがある。婚姻率も低下し続けており、女性が子育てと仕事を両立できるよう企業や配偶者の意識変革も含めた幅広い取り組みが必要だ。
