
木内登英
円安が加速する中、政府が行った円買い介入は日本の単独介入であり円買いは外貨準備の制約があるため効果は限定的だ。米国が景気減速で利上げを縮小するまでの時間稼ぎの要素が強い。

「歴史的物価高」は、ウクライナ戦争長期化でコストプッシュインフレに対して主要国が利上げや通貨引き上げを競っている状況を考えると、景気減速という犠牲を払う形で収束するシナリオが現実的だ。
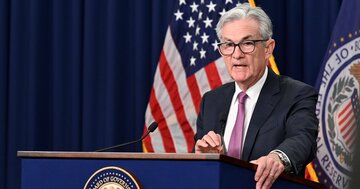
FRBの利上げや「テラUSD」の暴落を引き金に暗号資産の時価総額はピークの3分の1に縮小している。市場参加者が多様化する中で今回の調整局面は金融システムへ波及するリスクもはらむ。

参院選で各党が掲げる物価高対策は「バラマキ」の色彩が強く財源も不明だ。金融政策を修正し円安を抑制する一方で、成長戦略強化で生産性を高め物価高に対する耐性を強めることが正攻法だ。

ウクライナ戦争による成長減速が顕在化し始めたが、今後、対ロ制裁が強化されればロシアは資源大国の地位を失う可能性がある一方で、世界経済もエネルギー価格高止まりなどによる「両刃の剣」のリスクを覚悟する必要がある。

約20年ぶりの円安は内外金利差の拡大が底流にあるが、日銀は「円安は日本経済にプラス」として緩和政策を維持する。だが貿易構造の変化やコロナ禍で内需産業の打撃の大きいことを考えれば円安加速のリスクに目を向けるべきだ。

利上げ開始で金融政策正常化に踏み出したFRBだが、今後の利上げを急速なペースで進めるとの予想が強い。だが短めのタームのイールドカーブを重視するやり方は景気を冷やし過ぎるリスクがある。
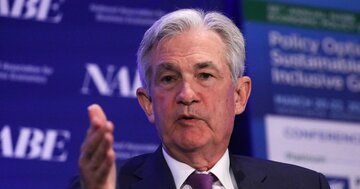
岸田首相の「新しい資本主義」は株主重視から「ステークホルダー資本主義」への移行と賃金低迷問題の解決をセットで目指しているようだ。だが企業統治の問題に政府が関与するのは注意が必要だ。

インフレ圧力が強まる欧米に比べ日本の消費者物価が落ち着いているのは、日本企業が値上げや雇用・賃金政策に慎重なことがある。だが物価安定が日本の「弱み」に転じる可能性がある。

2022年の世界経済の安定した回復の鍵を握るのは物価と金融政策正常化の動きだが、懸念されるのは、物価高騰が予想以上に長引きFRBが景気を犠牲にして利上げを進めざるを得ない状況になることだ。

賃金引き上げ策で重要なのは、日本経済の成長力や労働生産性を高め、企業が自ら賃金を引き上げる環境を作ることだ。無理に強いれば潜在成長率が損なわれ、結局、賃金上昇が妨げられる。

FRBが11月にも量的緩和の縮小を始めると予想されるが、市場が準備すべきはその先の利上げ開始だ。長い緩和でバブル化した金融資産市場の急落や新興国からの資金流出が懸念される。

岸田新政権の経済政策は財政・金融総動員の「安倍カラー」が薄れ、潜在成長力引き上げが最優先課題になる。「成長と分配の好循環」を掲げるが、まずは「成長」を実現する戦略が重要だ。

菅義偉首相の自民党総裁選不出馬表明を受けて、市場は円安・株高となった。来る衆議院議員選挙で自民党大敗のリスク低下を好感したと思われる。現在、立候補を表明、または検討している候補者の経済政策について予測、分析してみた。

日本銀行が始める「グリーンオペ」は気候変動問題対応の世界の潮流に合わせたものだが、やれる手段は限られており、下手をすれば本来の責務の物価目標の達成には矛盾することもあり得る。

10年近く議論が続いてきた多国籍企業の課税逃れ対策でデジタル課税導入などが大筋合意されたのは、新型コロナウイルス感染問題と米バイデン政権誕生という2つの想定外の要因が後押しした。

ビットコイン値下がりの直接の引き金は代金として受け入れを表明した米テスラ社の方針撤回だが、経済再開によるコロナ相場の終焉や環境負荷の問題でコロナ後、逆風は一段と強まりそうだ。

超金融緩和が長引き米金融市場は過熱の兆候が多く見られる。ノンバンクへの規制強化の動きがあるがいたちごっこだ。FRBは行き過ぎた感のある緩和の正常化の検討を始める時だ。

バイデン米大統領と菅首相は4月16日に首脳会談に臨み、その後、共同声明が発表された。バイデン政権は中国への対抗を強く意識して、安全保障、経済、地球温暖化対策、人権問題など幅広い分野で同盟国が一枚岩となって結束し、中国包囲網を形成することを目指している。これに対して日本政府は、尖閣諸島問題を中心に安全保障面での日米の強い結束を望む一方、日中間での経済関係の悪化を避けたいと考え、そのために人権問題などで中国を過度に刺激したくない、というのが本音である。

金融市場が注目してきた日銀の「金融緩和の点検」結果が、先日の金融政策決定会合で発表された。日銀は、従来の政策の枠組みが妥当であることを会見で強くアピールした上で、いくつかの政策措置の修正に言及した。しかし、彼らの本当の狙いは別にありそうだ。
