福島宏之
メンタルダウンした管理職に、企業はどう向き合い、本人はどうすればよいか
50代の「働かないおじさん」問題が取りざたされているなか、30代・40代の「働く管理職」のメンタルダウンが増えている。待遇に見合わない“責任の重さ”や同僚・若手社員の離職による“過重労働”など、その要因はさまざまだ。企業経営者や人事担当者は中間管理職のメンタルをどうケアし、心の病(やまい)にいかに対応していけばよいか――メンタルダウンの当事者であり、自らの経験から「心の病気に向き合うメソッド」を提唱する人事コンサルタントの佐々木貴則さん(ハートフルデイズ 代表)に話を聞いた。

“暗黙知の形式知化”が、人材・組織・企業をぐんぐん育てて強くする
経験などによって蓄積された“言語化されていない知見やノウハウ”を「暗黙知」という。 “職人技”のように、言葉での説明が難しいものもあるが、ビジネスシーンにおける「暗黙知」は、何らかの手段で「形式知」に変えられるものがほとんどだ。しかし、実際は、個人だけの“知”が職場にあふれ、それが時間とともに失われていくケースが多いのではないか? “暗黙知の形式知化”を20年以上前から研究し、独自に編み出したメソドロジーで組織開発・人材育成の支援を行う田原祐子さん(株式会社ベーシック 代表取締役)に話を聞いた。

生活時間と心のゆとりを創るために、「ゆとりうむ」が発信していること
コロナ禍で、私たちの生活や働き方のスタイルは大きく変わった。たとえば、テレワークによって通勤時間がなくなり、空いた時間を有効的に使い始めた人もいるだろう。一方、在宅時間が増えたことで、家事や育児にいっそう多くの時間を費やす人もいる。日常の中で“時間をうむ”ために行えるさまざまなこと――PR会社として知られるビルコム株式会社が立ち上げた「ゆとりうむプロジェクト」はそれを提案し続けている。プロジェクトの発起人である長沢美香さん(ビルコム株式会社 メディア局長)に話を聞いた。

有名企業の“コミュニケーションパーク”に見る、オフィス環境の大切さ
オーラルケアや健康食品などの消費者向け商品や金属加工部品、接着剤メーカーとして知られるサンスターグループが、2021年3月に開設したサンスターコミュニケーションパーク(大阪府高槻市)――広い敷地内にオフィスビルと芝生広場があり、社員の働きやすさの実現とともに地域住民との交流による共創を目指している。「CASBEE-ウェルネスオフィス認証」の最高評価を取得し、「2021年度グッドデザイン賞」を受賞した、そのパークの「素顔」を、関係者への取材とともに「HRオンライン」がレポートする。

障害のある人の雇用において、いま、企業にいちばん必要なことは何か?
前稿では、障害者の就労における雇用側の“専門スタッフ”の重要性などを、 “医療型就労支援モデル”の第一人者である清澤康伸さん(一般社団法人 精神・発達障害者就労支援専門職育成協会代表 医療法人社団欣助会 吉祥寺病院)に語っていただいた。コロナ禍で障害者雇用のあり方も変わりつつあるなか、企業経営者や人事担当者が心がけることは何か?

企業側の“専門スタッフ”の存在が、障害のある人の就労を定着させていく
法定雇用率のアップとともに、民間企業で働く障害者が増えている。障害当事者の就労のカギを握るのが、就労支援機関と企業における人事担当者の存在だが、昨今は、企業が配置する“専門スタッフ”も重要になっている――コロナ禍での採用から職場定着の方法まで、一般社団法人 精神・発達障害者就労支援専門職育成協会の代表であり、中小企業から大企業におよぶ3500社以上の障害者雇用を見てきた清澤康伸さん(医療法人社団欣助会 吉祥寺病院)に話を聞いた。

ドキュメンタリー映画「失われた時の中で」が教えてくれる、明日への希望
「SDGs」「ダイバーシティ&インクルージョン」という言葉がメディアをにぎわす一方で、「戦争」という言葉がいまだ過去のものにならない現代社会。そうしたなか、今年2022年の夏、生命と時間と愛の尊さを感じさせてくれるドキュメンタリー映画が公開される――『失われた時の中で』(監督・撮影:坂田雅子)。ベトナム戦争の枯葉剤被害者を丹念に見つめた作品だ。フォトジャーナリストとして活躍していた夫の死、50代半ばで始めた映画制作、そして、ベトナムで出会った多くの人たちとの触れ合い……坂田雅子監督が、過去と未来をつなぐ“いま”を語る。

ミレニアル世代の働きやすさのために、いま、企業は何をすればよいのか
女性活躍やダイバーシティマネジメント、仕事と生活の両立推進など……雇用環境の整備から経済社会発展への寄与を目的とする公益財団法人21世紀職業財団が、「子どものいるミレニアル世代夫婦のキャリア意識に関する調査研究」を今春に発表した。ミレニアル世代は、現在27~41歳(1980~1995年生まれ)の年齢層で、男女雇用均等法の第1回改正(1999年施行)後に就職した、法規上における“男女平等”で働き始めた世代だ。調査研究から見えた、 子どものいるミレニアル世代などの動向について、同財団の山谷真名さん(上席主任・主任研究員)に話を聞いた。
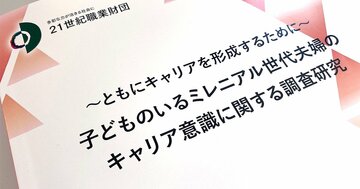
大学施設「のびやかスペース あーち」が目指す“共に生きるまちづくり”
新型コロナウイルス感染症の広がりは、リアルな空間に多様な人が集まり、関わり合う機会を大幅に減らした。神戸大学が運営する “のびやかスペース あーち”もその変化の波を受けた社会教育施設だ。地域コミュニティに寄り添い、「子育て支援をきっかけにした 共に生きるまちづくり」の理念を掲げる同施設の現在進行形はどうなっているのか? ダイバーシティ&インクルージョンメディア「オリイジン」が現地を訪れ、創設者の一人である神戸大学教授の津田英二さんに話を聞いた。

地方の“創業100年企業”で、なぜ、外国人が生き生きと働き続けるのか?
現在、日本では約170万人の外国人が働いている。街なかの店舗、建築現場、工場、企業のオフィス……外国人の就労がダイバーシティ社会をかたちづくり、企業経営者や管理職には、その適切なマネジメントが必要とされている。多人数の外国人の雇用で躍進している老舗企業が山形県の山形市内にある――スズキハイテック株式会社。「新・ダイバーシティ経営企業100選」(令和2年度・経済産業省)にも選ばれた同社は、どのように外国人の従業員に向き合っているのか。「HRオンライン」が現地を取材し、代表取締役の鈴木一徳さん(5代目社長)に話を聞いた。

多文化保育施設「はじめのいっぽ保育園」で、子どもたちが笑っている
日本の学校に通う外国人の児童生徒が増えている。しかし、文部科学省の調べでは、およそ2万人の外国人の子どもたちに不就学の可能性があるという。日本に居住する外国人がどう暮らし、その子どもたちがどのような学びの機会を得られるかは、ダイバーシティ社会の行く末を左右する大きな問題だ。そうしたなか、日系外国人の多い、茨城県常総市に“多文化保育”を実現している施設がある――はじめのいっぽ保育園。外国人と日本人の子どもたちの共生は? コロナ禍による状況の変化は? 運営者である、茨城NPOセンター・コモンズ代表理事の横田能洋さんに話を聞いた。

制作のプロフェッショナルが教えてくれた、「研修動画」に絶対欠かせないもの
コロナ禍で、オンラインによる研修やセミナーが増え続けている。テレワーク中の従業員が、eラーニングの「動画」をオンデマンドで提供されることも多いようだ。そうしたなか、創業から18年で、世界・日本を代表する2000社以上の、計5万本を超えるBtoB動画を制作し、配信支援を行っている企業がある――株式会社ヒューマンセントリックス。起業時のエピソードとともに、BtoB動画に特化する理由や動画制作のテクニックなどを代表取締役の中村寛治さんに語っていただいた。

“インクルージョン”が生まれるキャンパスで、学生たちが学ぶこと
ダイバーシティ&インクルージョンによって個と集団(チーム)が成長し、新しい価値が創造されることを大学のキャンパスで体感している若者たちがいる。桃山学院大学ビジネスデザイン学部――設置から3年の新しいキャンパスが、“学びとビジネスの交差点”として、学生に最大限の学びを与えているという。今回、「オリイジン」では、“交流と共創”を促す最新のフロア設計で創られた、そのキャンパス(あべのBDL)を訪れ、学生たちがどのような施設でどう学んでいるのかを取材した。

ブラック企業対応、管理職の利用……「退職代行」に人事部はどう向き合っているか
企業における従業員の「退職」の意思を、従業員本人に代わって企業側に伝える「退職代行」。近年、その請負業者とサービスの利用者が増えている。「退職代行」の背景にある労働環境は? 企業の人事担当者はどのように「退職代行」の通知に向き合っているのか? 現在の問題点は何か?――退職希望者のさまざまな相談を受け、「退職代行」の豊富な経験を持つ弁護士の竹内瑞穂さん(第一東京弁護士会)に話を聞いた。

なぜ、企業はダイバーシティ&インクルージョンを推進しているのか?
2010年代の半ばから、“ダイバーシティ推進室”を設置する企業が増えている。「ダイバーシティ&インクルージョン」「ダイバーシティ・マネジメント」……そもそも“ダイバーシティ”とは何か? なぜ、人事施策のキーワードになっているのか? 経済産業省が推し進める「ダイバーシティ経営」の実践は、誰がどう行うべきなのか? ダイバーシティ&インクルージョンやリーダーシップ開発をテーマに研究・教育活動を行っている酒井之子さん(桃山学院大学ビジネスデザイン学部ビジネスデザイン学科 特任准教授)に話を聞いた。
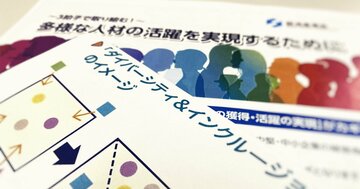
障がいのある人と障がいのない人を繋ぐ“懸け橋”としての人事部門
さまざまな人がそれぞれの働き方をするダイバーシティ社会で、障がいのある人は企業においてどのような活躍をしているのだろう――障がい者によるイノベーション創出の支援を行う一般社団法人 企業アクセシビリティ・コンソーシアム(ACE)が昨年2021年12月に「ACEフォーラム2021」をオンライン配信&リアル集客で開催し(*1)、“顕著な活躍を行う障がいのある社員をロールモデルとして表彰する”ACEアワード2021を発表した。フォーラムのテーマは、「共生社会が生み出す障がい者のパワーを企業の競争力に」。ACE事務局長の栗原進氏に、企業における障がい者就労の“いまとこれから”を聞いた。
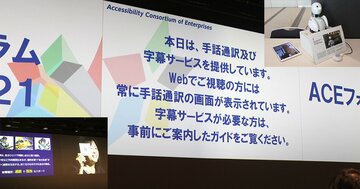
“やさしく、正しい情報”でコミュニケーションバリアをなくす医薬品とは?
新型コロナウイルス感染症に対する治療薬やワクチン、診断薬の開発でも注目されている塩野義製薬。そのグループ会社であるシオノギヘルスケア株式会社が発売する医薬品「セデス」シリーズが2021年度のグッドデザイン賞を受賞した。2020年6月に全面刷新したユニバーサルデザイン仕様のパッケージが、「店頭に置かれる薬のパッケージとしての集大成とも感じられる研ぎ澄まされたデザイン」と評価された結果だ。同社のビジネスコンセプトである「すべての人にやさしく、正しく、セルフケアを」の一環で刷新された、そのパッケージとは? シオノギヘルスケア株式会社 経営戦略部 プロダクトマーケティンググループ長 の吉田敏也さんに話を聞いた。

雇用の「不」を解決し、企業と一人ひとりの仕事をつないでいくために…
少子高齢化による労働力人口の減少、働き方改革によるワークライフバランスの推進、コロナ禍とVUCAの時代がもたらす若年層・就活生・求職者の就労観の変化……いま、日本の労働市場が大きな転換期を迎えている。企業が社会の中で存在する意味、さまざまな人がそれぞれの働き方を選択する価値を考えるうえで、企業と求職者を結びつける派遣会社の動向は見逃せない。設立40周年を迎えた、派遣業界大手の株式会社スタッフサービス・ホールディングス――その代表取締役社長・阪本耕治氏のスペシャルインタビューを「HRオンライン」がお届けする。

“いのち”に寄り添うドキュメンタリー映画『帆花』が公開されるまで
「東京ドキュメンタリー映画祭2021」では、コンペティション部門に過去最多の応募作品があり、今年10月にオンラインで開催された「YIDFF(山形国際ドキュメンタリー映画祭)」も盛況に終わった。デジタル機器の普及に加え、劇映画(フィクション)よりも低予算での製作も可能なドキュメンタリー映画が“動画の時代”に元気なようだ。そうした時世のなか、ドキュメンタリー映画の配給・宣伝を中心に行う会社がある――合同会社リガード。同社代表の西晶子さんを訪ね、西さん自身のキャリアと1月公開の『帆花』(監督・撮影/國友勇吾)の話を聞いた。

SDGs4「質の高い教育をみんなに」――真のグローバルとは何か?
「SDGs」は「2021ユーキャン新語・流行語大賞」にもノミネートされたほど、いまやすっかり人口に膾炙している。企業でも学校でも、その理解とゴールへの取り組みが進み、2030年の達成に向けて、社会が歩みを続けている。そうしたなか、早くからSDGsの普及に努め、こと、ゴール4「質の高い教育をみんなに」を考えるうえで注目すべき団体がある――一般社団法人 グローバル教育推進プロジェクト(GiFT)だ。その代表理事・辰野まどかさんに話を聞いた。
