原田 泰
「1%以下の金利でなければ採算が取れないような投資をいくらしても、経済は成長しない」という議論がある。だから、低金利政策はむしろ低成長をもたらすか、そうでなくても成長を回復させない、という意見である。例えば、小林慶一郎慶應大学教授は「低金利環境が経営層のリスク回避を過度に助長し、低成長をさらに固定化した」と述べている(「長期停滞、対症療法脱却を」経済教室 日本経済新聞、2022年10月12日朝刊)。また、プリンストン大学の清滝信宏教授も、2023年5月15日の経済財政諮問会議に提出した資料で、そう述べている。本当に、日本の企業は1%以下の金利でなければ採算の取れないような非効率な投資をしているのだろうか。経済全体として、投資と成長の関係を考えてみたい。

明治初期の松方財政は物価を2割近くも低下させるデフレ政策だったが、マルクス経済学者を含む多くの経済史家に高く評価されている。これに対して、故中村隆英東大教授は、異を唱えている。デフレ政策をどう評価するかは、現代の金融政策を巡る論点でもある。中村教授の説を確認しながら、松方財政を再評価したい。

ようやく議論されるようになってきたものの、依然として日本の賃金は上がっていない。どうして日本の賃金は主要国と比較して低下してしまったのだろうか。どうしたら、日本の賃金を上げることができるだろうか。

1990年までアメリカに追い付き追い抜く勢いのあった日本の経済成長率が低下し、現在では追い付くどころか差を広げられている。なぜこのようなことになったのか。戦前から現在までのアメリカ経済を含む世界経済の動向をひもとくと、その理由が見えてきた。

2022年2月24日に開始されたロシアによるウクライナへの侵攻から間もなく1年がたつ。侵攻当初のロシアは短期で終結すると予想していたと思われるが、その思惑は大きく外れ、約1年たった今も、激しい攻防が続いている。長期化が見込まれる上、ロシア側の明確な勝利が見えにくいにもかかわらず、なぜロシアはいまだに侵攻を続けるのか。ソ連時代のアフガン侵攻時との比較から考えたい。

2022年12月20日に日銀は大規模金融緩和政策の一部修正にかじを切った。だが、物価が上がっても金融緩和をやめるべきではないと筆者は考える。今回はその理由を解説したい。

9月6日に就任したばかりのイギリスのリズ・トラス前首相の在任期間はわずか50日だった。トラス前首相が辞任するハメとなったのは、公約で掲げていた大規模減税などを実施しようとしたところポンドが暴落し、さまざまな政策を撤回する事態に追い込まれたからだ。ポンド暴落はどれほど悪いことなのだろうか。

ウクライナ侵攻を続けるロシアのプーチン大統領には、オリガルヒと呼ばれる富豪の取り巻きがいる。プーチンとオリガルヒの関係、海外に散らばっているオリガルヒの実態についてさまざまな角度から分析した。

旧ソ連、東欧諸国には順調な経済発展を遂げている国が多いのだが、実はロシアは2010年前後からほとんど成長していない。それは何故だろうか。

経済発展の阻害要因として挙げられる「人口減少」だが、果たして本当にそうだろうか。ロシア侵攻前のウクライナは「破綻国家」と言われることがあるが、その要因には人口減少がある。だが、ウクライナを含めた東欧諸国の人口と経済発展の関係を見てみると必ずしもそう言い切れない点が浮かび上がってきた。今回はそれを考えてみたい。

ロシアのウクライナに侵攻に対して、西側諸国は経済制裁を課している。しかし、経済制裁が効果を上げていないのではないかという議論もある。IMF(国際通貨基金)をはじめとする各種データから、制裁の効果がどれだけあるかを考えてみたい。
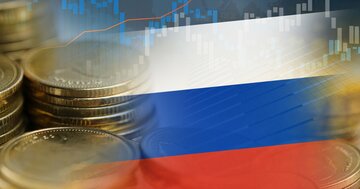
日本の実質GDPが伸びていないことは、今や誰もが知るところとなっている。なぜこんなことになってしまったのだろうか。さまざま原因が考えられるが、今回は、日本の資本ストックに焦点を当て、データから原因を探ってみたい。

ロシアのウクライナ侵略に対して、「早く降伏したほうが犠牲者が少なくて済むから、早く降伏したほうが良い」という議論があるようだ。この議論について、過去の事実を基に考察しよう。

ロシアによるウクライナ侵攻開始から7週間がたとうとしている。プーチン政権は、ロシア国内では情報統制を行い、国民に「うそ」をつき続けているようだ。かつて、旧ソ連圏の東ドイツでも、国民に経済の実態をひた隠しにしていたことが後に明らかになった。当時のデータを分析することで、現在のロシアのうそがいつまで維持できるのかを考えるヒントが見えてくる。

ロシアのウクライナへの非道な攻撃が続いている。ロシアによれば、ウクライナはロシアと一体であり、西側に走るのはけしからんというのだ。なぜウクライナが西を向くのか。旧ソ連圏のデータからその理由を考える。

格差が世界的に問題になっている。日本においても、岸田政権は「新しい資本主義」によって格差を縮小させるとしている。なぜ格差が拡大しているのか、格差をどのように解決するべきなのかを議論する前に、国際比較から事実を整理する。

日本の財政状況は危機的といわれており、このままでは、財政は破綻するとされている。国債の償還ができない、ハイパーインフレになる、金利が暴騰する、円が暴落するなどの危機が起きるというのだ。ところが、現在までのところ何も起きていない。何も起きない理屈ではなく、そもそも財政が危機的状況なのかという認識について、疑問を述べたい。

今回は、クラスター対策とPCR検査について分析する。過去の対応でPCR検査が遅れた理由は、感染症学者と厚労省が検査の拡大に反対したことにあるようだ。安倍首相(当時)と政治力を持つ医師会がPCR検査を拡大すべきだと言っていたにもかかわらず、現場では一向に改善が見られなかったようだ。その理由を分析するとともに、データを踏まえてPCR検査のあるべき姿を考える。

ワクチンの入手と接種について考える。3回目の接種では、「ワクチン敗戦」といわれた経験を生かし、世界に先駆けた接種ができると期待していたが、そうはなっていない。ワクチン敗戦は続いているようだ。

オミクロン株が日本経済に与える打撃をいかにして回避、あるいは最小化するか、各種データを用いて3回にわたり分析する。第1回は、病院の患者数などのデータから、水際対策と医療体制の拡充の問題について考える。
