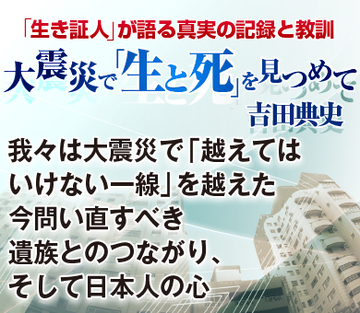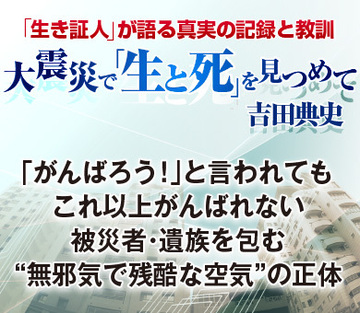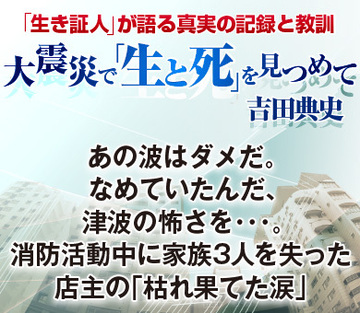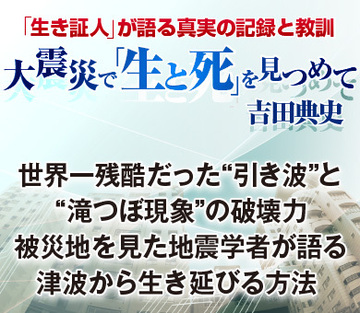3月11日午後2時46分。東北地方を中心に大規模な地震が起きた。その後、現地を襲った巨大津波や原発事故により、2万人近くの人が亡くなり、行方不明となっている。
この日以降、多くのメディアは被災地の人々の「生と死」について、溢れんばかりの情報を提供し続けてきた。こうした報道の数々が、被災者を勇気づけ、復興への前向きな思いを高める上で、大きな役割を担ってきたことは言うまでもない。
しかし「なぜこれだけ多くの人が亡くならなければいけなかったのか」という核心に迫った報道は、意外に少なかった気がする。報道には、時として慎重な姿勢が必要となることも確かだ。だが、震災から5ヵ月以上が経った今、私たちはそろそろ震災がもたらした「生と死の現実」について、真正面から向き合ってみてもよい頃ではないだろうか。
災害はいつかまた、必ずやって来る。だからこそ、その真相に目を向けなければ、新たな災害に備えるための教訓を得ることはできない。
私は3月から、防災学者、警察、消防、自衛隊、さらには被災地の自治体職員、医師、そして遺族など、多くの「震災の生き証人」たちに会い、取材を続けてきた。なかには、「亡くなった人たちは必ずしも『天災』だけが原因で命を奪われたとは言い切れない」と感じたケースもあった。
この連載では、そうした人々が実際に体験したこと、感じたことをベースにしながら、震災にまつわる「生と死の現実」について私なりに斟酌し、今後の防災で検証すべき点を提言していきたい。
検死医が目の当たりにした「津波の遺体」
“避難慣れ”も災いして被害が拡大?
 被災地に赴き検死に携わった杏林大学の高木徹也・准教授(筆者撮影)。
被災地に赴き検死に携わった杏林大学の高木徹也・准教授(筆者撮影)。
「検死した遺体の中には、多額のおカネを持っていた人がいた。多い人は、現金で2000万円ほど。ある人は有価証券、ある人は土地の権利書も抱え込んでいた。津波が来たときには、これらを持って避難しようと考えて、家の中の1ヵ所に集めておいたのではないか。地震の直後に急いで探し出して身に付けたという感じではなかった」
法医学を専攻する高木徹也准教授(杏林大学)は低く、通る声で話した。私は、この言葉を聞いたとき、ここ数ヵ月間、悶々としていた思いが少し消えていく気がした。