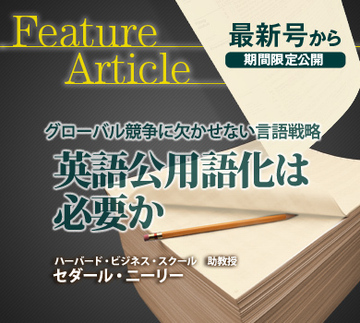経営史を振り返ると、社会機関も生み出した長寿企業を築き上げた実業家が多数存在する。たとえばホートン家は、コーニング・グラス・ワークス(そもそもは1851年にエイモリー・ホートンが創業したユニオン・グラス・カンパニーが始まり)とニューヨーク州コーニングという街をつくった。またタタ一族は、インドを代表するコングロマリットとジャールカンド州ジャムシェドプルという鉄鋼都市を生み出した。
経済の論理と株主資本主義が事業の前提条件となり、企業が特別の場所から引き離されるようになると、こうした「企業の社会責任」というスタイルは流行らなくなった。しかし、今日のグローバル化した世界では、その考え方を改めなければならない。
グローバル化によって変化のスピードは速くなる。つまり、世界の至るところでライバルが増え、驚異や衝撃が増える。競争の激しいグローバル経済では、イノベーションが重視されるが、それは、人間の想像力や動機、コラボレーションに左右される。グローバルM&Aはいっそう複雑化し、またその成功は、どれくらいうまく統合できるかに左右される。
さらに、企業の目標と社会の価値観を合致させ、正当性や人々の支持を確保することが、事業上の喫緊の課題になっている。国境を超えて事業展開する企業は、文化の調和や現地国への適応といった問題に直面する。どこで操業しようと、政府やオピニオン・リーダー、一般市民から支持されなければならない。社員は、社内では当事者でもあり、外に出ればその企業の顔でもある。
リーダーは、みずからが社会機関をつくることを考えて、初めて今日の変化や課題に対応できる。私が思うに、制度の論理には、経済の論理や財務の論理──研究、分析、教育、政策、そして経営の意思決定の指針である──と同じ地位を与えなければならない。
以下では、グレート・カンパニーが制度の論理を用いる際での6つの方法に加えて、それにどれほど強みがあるのか、リーダーシップや企業行動をどれほど根本的に変えるのかについて検討する(「『制度の論理』の利点」を参照)。