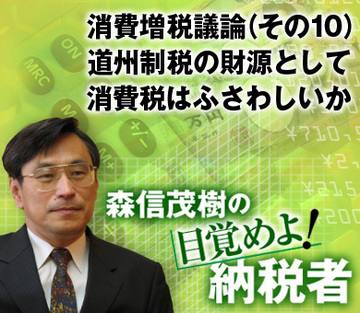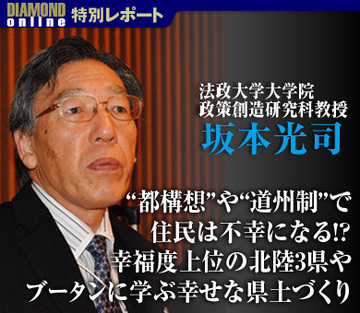「葉山先生のおっしゃる通りだ。我々のやろうとしていることは、中央政府の権限と規模を縮小し、地方の独立を促すことだ。中央官庁の官僚にとって不利益となることだ。我々国会議員にとってもね。大部分の官僚や議員からは支持されないだろう。それどころか、潰そうと大攻勢をかけてくることは分かっている。村津さんから、きみは省庁の利益を超えて、国民と国のために動ける人だと推薦を受けている。きみの論文を読んで私もそれを確信した。どうか、お力添え願いたい。そして今日のことは、しばらくは内密にお願いしたい」
殿塚は森嶋に向き直ると、深々と頭を下げた。
森嶋は、殿塚が村津から聞いたという言葉に驚いていた。自分が村津にそれほど評価されているとは、信じられなかったのだ。しかし殿塚と葉山たちの言葉は数時間前に六本木の事務所で見た都市模型と共に、ずっしりと心の奥に響いた。身体の中に熱いものが込み上げてくるのを感じていた。
送っていきましょう、という植田の言葉を断わって、森嶋は地下鉄の駅に向かって歩いた。これから役所に戻ろうかとも考えたが、時間を見てやめた。
冷たい風が吹きつけてくる。しかし、寒さは感じなかった。むしろコートのボタンを外し、その風を胸一杯に吸い込んだ。
脳裏には、道州制について語る殿塚、大野、葉山たちの顔が浮かんでいた。そして、六本木の長谷川の事務所で見た近代都市の模型と、そこに集まっていた人々。全く別の道を歩んでいた日本の未来がお互いに近付き、交差を始めた。いずれは交わり、太い一本の道となって未来へと続いていくのだろうか。いや、そうあらねばならない。その接着剤の役目を果たせたら。そして一緒に歩むことが出来たなら。時代の動きに大きな足跡を残すことが出来る。
そのとき、高脇の姿が頭を掠めた。彼はいまどこにいるのだ。無愛想な顔でぼそぼそと話す高脇の声が、なぜか無性に懐かしく思えた。携帯電話を出して、高脇のボタンを押した。やはり、帰ってくるのは電源が切られていることを告げる女性の声だ。
森嶋は携帯電話をポケットにしまい、地下鉄への歩みを速めた。