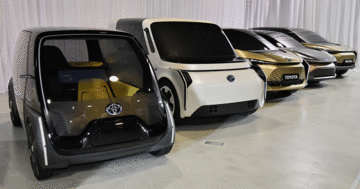市川市が公用車として導入した、テスラモデルX。市川市仮庁舎にて Photo by Kenji Momota
市川市が公用車として導入した、テスラモデルX。市川市仮庁舎にて Photo by Kenji Momota
異例会見でも市の真意伝わらず!?
市川市とメディアとの性格の不一致?
昨今、テレビやネットで千葉県市川市での「テスラ問題」が話題になっている。この話はなぜ、ここまで大きな騒動になってしまったのか?
本連載は今年で10年目となったが、その10年間でテスラを含めた世界各国のEV(電気自動車)事情、また各国政府や地方自治体が主体となるEV普及政策について深掘りしてきた。そうしたこれまでの取材経験をもとに市川市のテスラ問題について、筆者なりに検証してみたい。もちろん、市川市での現地取材も続行中だ。
まず、市川市テスラ問題の概略を紹介する。
市川市が公用車として新車価格1000万円超えの米国製EV「テスラ」2台を導入したことについて、「公用車としては高額過ぎる」「税金の無駄遣い」といった声が市民やメディアの間で噴出したというものだ。
騒動が大きくなったきっかけは、今年6月の市川市議会で、すでに導入が決まっている公用車テスラについて、その妥当性が議題となり決議した結果、賛成20:反対21となり、これがメディアで大きく取り上げられたことだ。この決議の結果は拘束力を持たないため、市としては公用車テスラ導入を進めた。
 市川市仮庁舎 Photo by K.M.
市川市仮庁舎 Photo by K.M.
7月2日午後には市川市役所(本庁舎は工事中のため仮庁舎)で、新しいまちづくり政策「いちかわ未来創造会議」の記者会見後、1台目の公用車テスラである「モデルX」の納車式をメディア向けに公開したところ、テスラ問題について市からの見解を聞きたいとキー局などテレビ取材が殺到。だが現場では、公用車テスラ導入に対して、メディアから「市川市からの説明が不十分だ」との指摘が続出した。