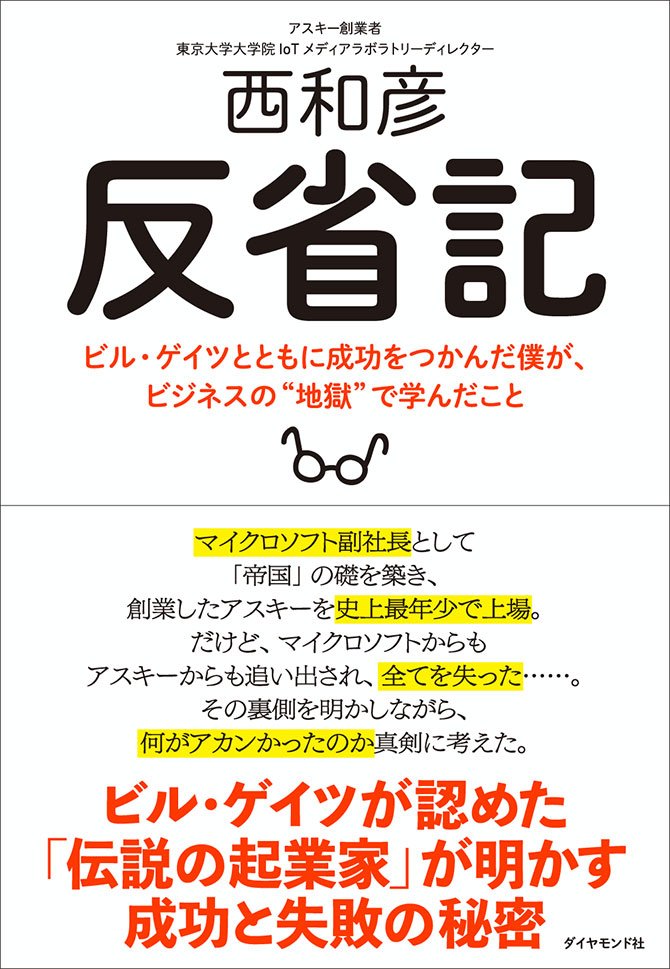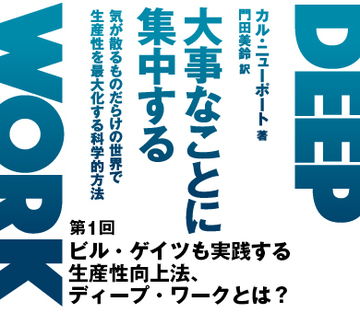『週刊プレイボーイ』がもたらした情熱
レコード・プレイヤーの次に作ったのはラジオだった。
そのきっかけは、雑誌『週刊プレイボーイ』だった。中学時代は、男子も女子も急激に心と身体が変化する時期だ。異性への興味も高まってくる。男子の友達と集まると、女性の話題で盛り上がることも珍しくなかった。
そんなときに誰かが、「『週刊プレイボーイ』という雑誌には、毎週女性のヌードが載っているらしい」と発言した。それを聞いて、その雑誌を見てみたいと思わない中学生は一人もいなかっただろう。今のようにインターネットのない時代である。もちろん、僕も何としても見たいと思った。
しかし、本屋で買うわけにはいかない。
買うのが恥ずかしいし、本屋のオヤジが父親に言いつけて、買ったのがバレたら大事だ。どうにかして、『週刊プレイボーイ』を見る方法はないかと思いを巡らせていたある日、新聞のラジオ欄を見て胸がときめいた。深夜12時ごろから放送している、「プレイボーイ・クラブ」という番組があるのを見つけたのだ。
僕は直感した。これは、あの『週刊プレイボーイ』がやっている番組だ。間違いない。きっと、ドキドキするような刺激的な話が聴けるはず……。ところが、深夜に部屋で聴くラジオがない。となれば、自分でラジオを作るしかない。早速、研究を開始した。
作ったのは鉱石ラジオと呼ばれるゲルマニウム検波式ラジオだった。
材料を買ってきて、本を見ながら組み立てていった。バリコンをつけて、検波器のゲルマニウム・ダイオードをつけて、クリスタル・イヤホンにつなぐとラジオの完成。思ったほどの時間はかからなかった。「これで、ついに……」と嬉しかったが、結局、僕は、その「プレイボーイ・クラブ」を聴くことはなかった。何度も聴こうとしたのだが、番組が始まる前にいつも寝てしまっていたのだ。
150万円の「電子レンジ」を壊して学んだこと
挫折も味わった。
僕は無線マニアでもあった。アマチュア無線に興味を持ち始めたのは小学校の低学年の頃で、9歳の時に、電話級アマチュア無線技士の資格を取った。その2年後には、50MHz帯で運用するアマチュア無線局を開局し、ブラジルと交信したりもした。その後も無線技術を学び続けたが、高校時代にこんな失敗をしたのだ。
あるとき、僕は、購読していた専門誌で、「地球月地球通信」という画期的な技術を知った。地球から電波を出して月に当てて、月から反射された電波を拾って行う通信で、月に電波を反射させると、地球の裏側のような遠い場所とも交信できるという壮大なアイデアだった。
これに、おおいに興味をそそられた僕は、早速、自分でもそれをやってみようと考えた。最大の問題は、「地球月地球通信」には、アマチュア無線で使われている1・2ギガの周波数の倍の2・4ギガの周波数が必要ということだった。これが、そう簡単なことではなかったのだ。
僕が目をつけたのが、我が家の電子レンジだった。
電子レンジの周波数は2・4ギガだから、これを分解して、クライストロンという真空管を取り出して、2・4ギガの周波数を作ろうと考えたのだ。しかし、結局、それはうまくいかなかった。2・4ギガの周波数が出ているのは間違いないのだが、どうしても「地球月地球通信」ができない。なぜだ? その原因を探し続けた僕は、物理学の書物に「答え」を見つけた。なんと、2・4ギガの周波数は大気中の水に吸収される性質があったのだ。
僕は打ちひしがれるような思いだった。当時の電子レンジは1台150万円もする高級家電だったから、それをバラバラにされた母親の怒りもこたえたが、何より、自分の知識不足に愕然とした。
自分の興味だけでものを作っても成功するとは限らない。無線についてはプロ級の知識があると思っていたが、物理学をはじめとする体系的な知識は何もなく、これを身につけなければ、これ以上先にはいけないと悟らされた。今になって考えてみると、これは、「学ぶ」ということの大切さを学んだ、僕にとっては大きな失敗であり転換点だった。
新しいものをつくる「組み合わせ発想法」
それ以外にも、少年時代の僕は、家中のほとんどありとあらゆるものを分解し、「こんなものが欲しい!」「こんなものがあればいいな!」と思うものを作りまくっていた。
居間に一台しかなかった電話の配線を変えて、二階の自室でも友達と電話ができるようにもした。普通は、二階の電話に切り替えても、一階の受話器を上げると会話が聞こえてしまうのだが、それができないような回路にした。真空管式のトランシーバーや真空管式のオシロスコープをはじめ、当時の僕が思いつく機械を、数え切れないほど自作した。それが、楽しくてならなかったのだ。
今思えば、目の前で動いている機械のアナロジーを新しいことに応用するのが好きな子どもだった。出発点は、「何かを実現したい」というパッションであり、「これは凄い」という感動だ。そして、その願望を実現するために、すでにあるモノや機械を応用しようとする。これが、僕の基本的な発想法だったと思う。
たとえば、テレビのチャンネルを自分では変えたくないという願望を満たすために、物干し竿を活用したり、ミシンのモーターを応用する。レコード針がなければ、紙を円錐形に丸めて、その先に裁縫針を仕込む。2・4ギガの周波数を得るために、電子レンジの真空管を使うといった具合だ。
そして、この発想法が、僕が大人になってからの仕事の土台になったと思う。
全くゼロからのクリエイティビティではなくて、すでにソリューションがあるものを新しい何かに組み合わせて応用する。自分がいままで築き上げてきたもののエレメント(要素)を組み合わせて、何か新しいものをつくる。それが、僕の得意なことだという感じがする。だから、少年時代の試行錯誤は、その後、ノート・パソコンやハンドヘルド・コンピュータなど、現在のパソコンの「原型」とも言えるマシンをつくった僕の仕事すべてに生きている。あるいは、「三つ子の魂百まで」と言うべきなのかもしれない。
 西 和彦(にし・かずひこ)
西 和彦(にし・かずひこ)株式会社アスキー創業者
東京大学大学院工学系研究科IOTメディアラボラトリー ディレクター
1956年神戸市生まれ。早稲田大学理工学部中退。在学中の1977年にアスキー出版を設立。ビル・ゲイツ氏と意気投合して草創期のマイクロソフトに参画し、ボードメンバー兼技術担当副社長としてパソコン開発に活躍。しかし、半導体開発の是非などをめぐってビル・ゲイツ氏と対立、マイクロソフトを退社。帰国してアスキーの資料室専任「窓際」副社長となる。1987年、アスキー社長に就任。当時、史上最年少でアスキーを上場させる。しかし、資金難などの問題に直面。CSK創業者大川功氏の知遇を得、CSK・セガの出資を仰ぐとともに、アスキーはCSKの関連会社となる。その後、アスキー社長を退任し、CSK・セガの会長・社長秘書役を務めた。2002年、大川氏死去後、すべてのCSK・セガの役職から退任する。その後、米国マサチューセッツ工科大学メディアラボ客員教授や国連大学高等研究所副所長、尚美学園大学芸術情報学部教授等を務め、現在、須磨学園学園長、東京大学大学院工学系研究科IOTメディアラボラトリー ディレクターを務める。工学院大学大学院情報学専攻 博士(情報学)。Photo by Kazutoshi Sumitomo