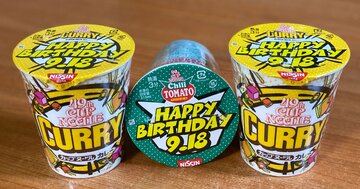写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
新横浜ラーメン博物館は昨秋、ラーメン発祥の店といわれる来々軒のラーメンを再現した。驚くことに、100年以上前に開業したその店のラーメンは、今どきの化学調味料を使わない無化調のしょうゆラーメンそっくりだった。では次の100年、ラーメンはどこへ向かうのか。新横浜博物館の名物館長の岩岡洋志氏をはじめとする、ラーメン界の識者たちに話を聞いた。(サイエンスライター 川口友万)
100年前のラーメンは
今どきのしょうゆ味
日本で最初のラーメンブームは1910年に開業した浅草来々軒から始まったとされる。新横浜ラーメン博物館では2020年10月に来々軒のオープン当時の味を再現することに成功した。
100年前のラーメンと聞き、なんとなく想像したのは、最近上陸してきた蘭州ラーメンだ。中国内陸部のラーメンで、確かにおいしいのだが、味が薄く、ダシの弱さをラー油や肉の脂で補っている。ダシ文化の日本人の舌には、物足りなさが残る。100年前のラーメンはそういった味なのだろうと勝手に思っていたら、実際に食べて予想を裏切られた。