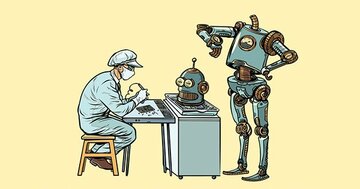70年以上愛されてきたフィクションに宿る芸術性
ある作品が正反対の主張に使われること自体は悪いことではない。多様な読み方ができるのはフィクションの大きな価値だし、もし「絶対唯一の模範的な読み方」を人から押し付けられたら、それこそ真のディストピアである。
それにしても、『一九八四年』がこれほどの汎用性と持続性を持ち得たのはなぜだろうか?
オーウェルは第2次世界大戦中、BBCでインド向けのプロパガンダ放送の制作に携わった。そこでは「戦略的な必要から事実を歪曲した放送を黙認することも一度ならずあった」(川端,前掲書)という。オーウェルはこうした経験にうんざりし「権力によって都合よくねじ曲げられる事実より、優れたフィクションの方が本質を伝える力がある」という思いを強めたのではないだろうか。
「全体主義の批判」という目的をベースに、政治権力と監視テクノロジーが結び付いた「もしも」の世界のあり得る未来像を構想する――。こうした構造を持つ『一九八四年』は、ある意味ではSFプロトタイピング的な作品ともいえる。しかし、本作の特色はそれだけでは語れない。
前掲書で川端は、「私がいちばんしたかったことは、政治的著作をひとつの芸術にすることだった」というオーウェル自身の言葉を引用した上で「オーウェルの美質は、この小説の細部に散りばめられて、光を放っている」と、その芸術性を高く評価している。筆者もこれに同意する。政治的な側面ばかり注目されがちな本作だが、芸術としての魅力があればこそ、ここまで強い影響力を持つに至ったと思うのだ。
『一九八四年』の独裁政党は、人民統治のために、せっせと本の廃棄や記録の改ざんに励む。さらには、英語に代わる言語体系として<新語法>を普及させようとする。単語を減らし、文法を単純化し、複雑な思考ができない言語に作り替えようというのだ。「言葉の剥脱」が支配に直結することを、丁寧に描いた本書からは、逆説的に「言葉の力」「フィクションの力」が強く伝わってくる。
『一九八四年』は、英国では「読んでないけど読んだふりをする本」の筆頭だそうだ。これだけ有名な作品になれば、読んでなくても粗筋や設定は知っているという人も多いだろう。しかし、緻密に作り込まれた世界観の迫力は、通読してこそ胸に迫る。世界観を丸ごと味わうことで新たな発見があることは間違いないし、グローバルなビジネスや政治状況を読み解く補助線として有用であることも保証する。未読の方には、ぜひ読んでいただきたい一冊だ。