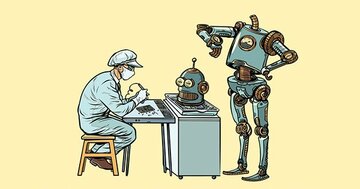敵にも味方にも「武器」として使われてきた物語
こうした『一九八四年』の影響力の大きさを考える上で、筆者は最近、英文学者の川端康雄の評論書『オーウェル「一九八四年」 :ディストピアを生き抜くために』(慶應義塾大学出版会)を興味深く読んだ。ここからは、同書を参考に、『一九八四年』の「使われ方」を考えてみたい。
『一九八四年』が出版されたのは、東西冷戦が深まりつつあった49年のことである(ちなみに「冷戦」という言葉を初めて使ったのもオーウェルである)。出版直後は、主に米国政府が、「反共プロパガンダ」として世界に広め、GHQ占領下の日本でも50年にいち早く翻訳出版されている。一方、共産圏ではほぼ禁書の扱いだった。
その後、何度かのブームを経て、再び『一九八四年』がベストセラーになったのは、ドナルド・トランプが米国大統領選挙で勝利した16年以降のことだ。そして、「ポストトゥルース」(客観的な事実より、感情や気分が重視される政治状況)や「フェイクニュース」が流行語になり、大統領の側近が事実に反する主張を「オルタナティブファクト(もう1つの真実)だ」と強弁するような政治状況の中、トランプをビッグ・ブラザーになぞらえて批判する言説が世にあふれた。
興味深いのは、21年にトランプが大統領選に敗れ、暴動を扇動したとしてTwitterアカウントが停止されると、今度はトランプの長男が『一九八四年』を持ち出して「米国にはもはや言論の自由が存在しない」と反論したことだ。(個人的には反トランプ側に肩入れしたいところだが、ここでは状況だけを俯瞰すると)トランプ側も反トランプ側も「相手こそがビッグ・ブラザーだ」と糾弾しているわけだ。
同書で引用されている藤田直哉の論考(『1984年』の汎用性――なぜイデオロギー的に対立する相手が、互いに互いを『一九八四年』の図式を使い批難しあう現象が起きるのか,「図書新聞」No.3366)では、米中対立においても、日本の左派と右派の対立においても、『一九八四年』を使って互いをののしり合ってきた状況が解説されている。
『一九八四年』は、社会主義にも資本主義にも、右にも左にも「活発に使われてきた」のである。