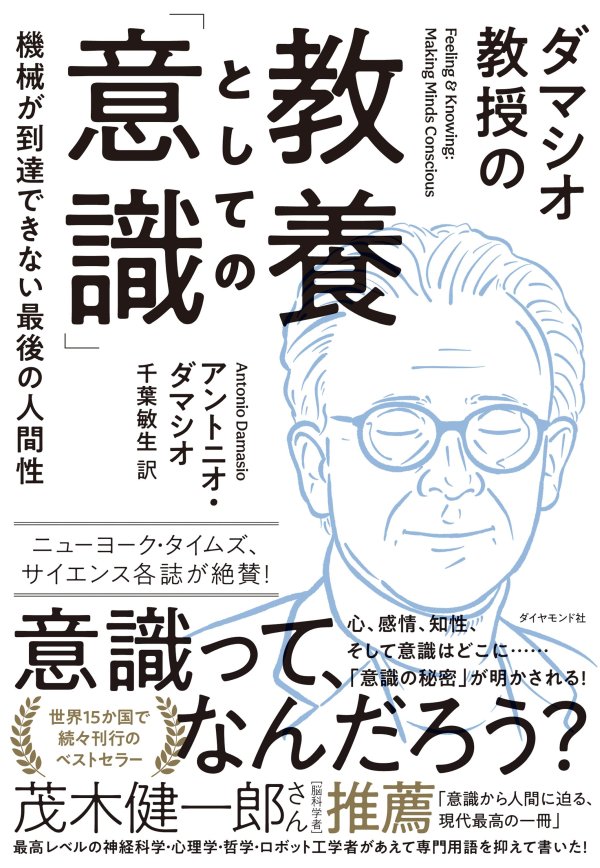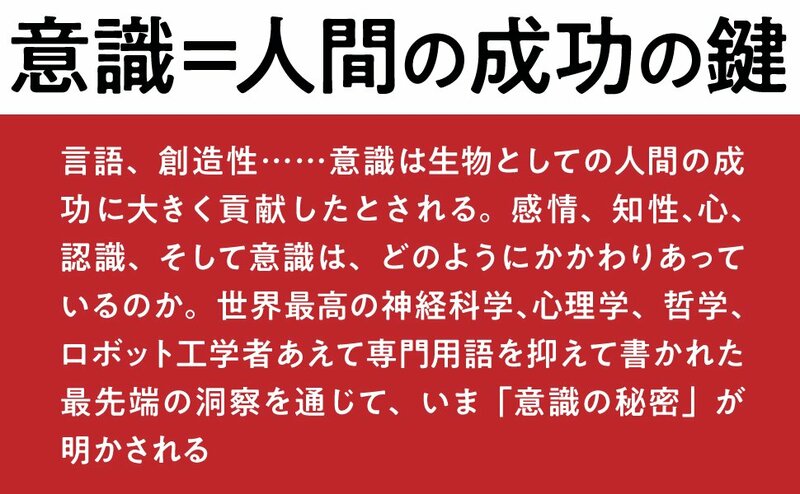言語や創造性をはじめとして、意識は生物としての人間らしさの根源にあり、種としての成功に大きく貢献したと言われてきた。なぜ意識=人間の成功の鍵なのか、それはどのように成り立っているのか? これまで数十年にわたって、多くの哲学者や認知科学者は「人間の意識の問題は解決不可能」と結論を棚上げしてきた。その謎に、世界で最も論文を引用されている科学者の一人である南カリフォルニア大学教授のアントニオ・ダマシオが、あえて専門用語を抑えて明快な解説を試みたのが『ダマシオ教授の教養としての「意識」――機械が到達できない最後の人間性』(ダイヤモンド社刊)だ。ダマシオ教授は、神経科学、心理学、哲学、ロボット工学分野に影響力が強く、感情、意思決定および意識の理解について、重要な貢献をしてきた。さまざまな角度の最先端の洞察を通じて、いま「意識の秘密」が明かされる。あなたの感情、知性、心、認識、そして意識は、どのようにかかわりあっているのだろうか。(訳:千葉敏生)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
人間は苦と快に操られている?
意識が人間に及ぼした特別な影響に関して、候補として挙げられるのが、一部の哺乳類が見せる他者の死への反応の仕方だ。このことは、たとえばゾウが行う葬儀の例を見ても明らかだ。間違いなく、仲間の苦痛や死といった結果を目の当たりにしたことで引き起こされる自分自身の苦しみの意識が、このような反応を形成するに至ったのだろう。
人間との違いは、創意工夫の規模や、反応の構築に見られる複雑度や有効度だけだ。こうした例外的な事例は、反応の違いが特定の種に見られる意識の性質ではなく、その種の知的能力と関連している、という説を概ね裏付けている。
意識が可能にする反応の有効性は、感情のネガティブな側面とポジティブな側面、つまり負の感情価(ヴェイレンス)と正の感情価の、どちらによって主に生じるのか? そう問うのは理にかなっている。
痛みや苦しみ、死の認識は、幸福や快よりもいっそう大きな原動力になる、と私は思っている。宗教などは、この認識に基づいて発展を遂げたと言えるのではないだろうか。アブラハムの宗教(キリスト教、ユダヤ教、イスラム教)や仏教は、その最たる例だ。
ある意味、歴史的な進化の観点から言えば、意識とは禁断の果実の一つであり、一度それを食べた者は痛みや苦しみを感じるようになり、やがては死との悲劇的な直面にさらされる。この見方は、進化の過程において、意識が感情、とりわけネガティブな感情の手によって生み出された、という考えと密接に符合する。
悲劇の源としての死は、聖書の物語やギリシャ演劇において十分に確立され、今なお芸術活動に息づいている。この考えを見事に捉えた詩を書いたのが、20世紀の詩人のW・H・オーデンだ。彼は人間を、残酷な皇帝に懇願する満身創痍の反抗的な剣闘士に見立て、「われわれ死すべき者が要求するのは奇跡だ」と述べている。
彼が「必要とする」とか「要望する」ではなく「要求する」と書いたのは、彼が追い詰められ、けっして避けられない人間の崩壊を絶望の中で眺めていたことの証(あかし)だろう。
オーデンは、「現実に起こりうるいかなることも、われわれを救えはしない」ことに気づいていた。この結論自体は目新しいものではない。実際、この結論は多くの宗教や哲学体系の創設の物語へと組み込まれているし、苦しみの中に生きる人々に手を差し伸べる教会の助言に従うよう、今でも世界中の人々を導いている。
それでも、世の中に「苦」しか存在しなければ、つまり「快」の見込みのないただの苦しか存在しなければ、いったいどうなっていただろう? 苦しみの回避が促されることはあっても、幸福の追求が促されることはなかっただろう。結局のところ私たちは、ときどき創造力から自由を得る、苦と快の両方の操り人形にすぎないのだ。