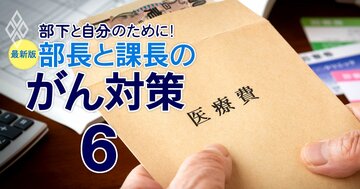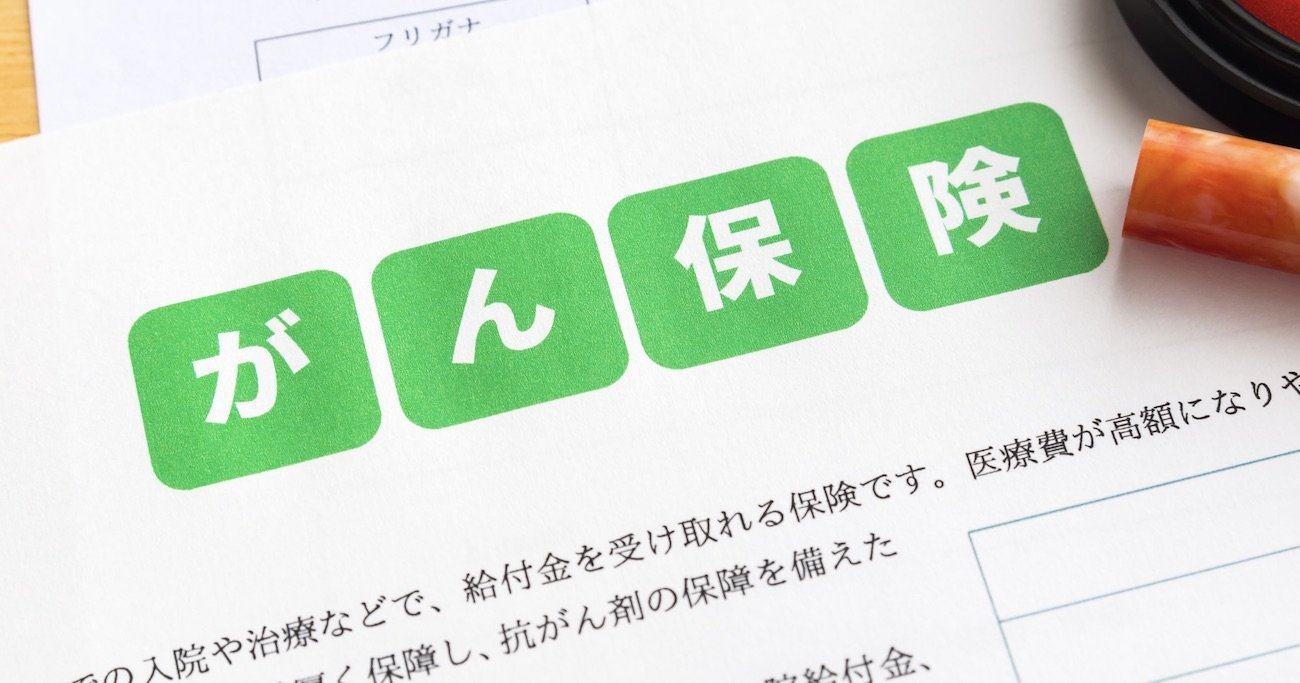 Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
「がん保険は要らない」と言っていた筆者が癌になった。それでも「がん保険は、やっぱり不要だ」と思った。これは筆者としての結論だが、その判断に影響を与えた要素が筆者と同様の方は少なくないはずだ。今回はその要素についてお伝えするので、読者は、ご自身としての結論を得てほしい。
私の癌と治療経過
冒頭から私事で恐縮だが、筆者は昨年不幸にして癌にかかった。ステージIIIの食道癌である。そして、幸いにして治療は順調であり、体力はかなり回復した。現在、再発防止目的で薬剤を投与しており、向こう一年ほど検査なども含めて1カ月に一度程度通院する予定だが、仕事を含めて日常生活に支障はない。
ただし、「不幸」と「幸い」の比較は、残念ながら「不幸」の勝ちだ。最大限に治っても病前の状態までは回復しない。端的に言って、以前と同じように飲んだり食べたりできるようにはならない。飲んだり、食べたりは、本当に楽しかった。ビジネスや人間関係の上でも大変有効だった。そして、何よりも再発のリスクを抱えている。食道癌は再発や転移が多い癌なのだ。読者は癌にかからない方がいい。
さて、癌になってみると、筆者の元にはがん保険に関する質問が多数寄せられた。「がん保険は要らない」と言っていた人物が、実際に癌になってどう感じたか興味を持たれたのだろう。
本稿では、筆者の癌とその治療経過を手掛かりに、がん保険の要否について考える。筆者と似た条件にある方は多いと思うが、読者と筆者とで意思決定のための条件が同じでない点はあるかもしれない。もとより自分一人の経験を一般化して押しつけるつもりはない。
読者は、ご自分の問題として改めて考え直してご自身の結論を得てほしい。