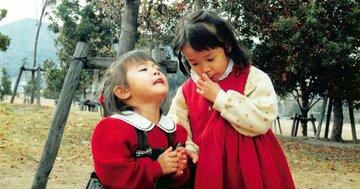すぐにできる
「未来語」のススメ
「強くなる」を「自分が望む状態に近づく」と考えるならば、「強くなった私」というのは、現在でも過去でもなく、未来に存在することになります。
今より体重が3キログラム減った私も、少しスペイン語を話せるようになった私も、子どもを行きたいところに連れて行っている私も「今、ここ」にはいないのです。今、ここにいるのは「それに向かう私」です。
だとすれば、使っている言葉を「未来に到着しやすい言葉=未来語」に変えてみるのはどうでしょう?私たちは言葉で思考しますから、未来語を手にすることで、アクティヴで現実的な思考が得られるはずです。早速AとBを比較してみましょう。
A:今回のテストは難しかった。
B:今回のテストは全く手の出ない問題が40%あった。
Aはテストを受けた感想です。テスト問題という外部刺激に対して、「どう感じたか」が述べられています。完結していますからAにつながる言葉は「そうだったのですね」「お疲れ様でした」になってしまいます。
Bは感想ではなく、事実の冷静なる分析です。60%には何らかの記述ができたわけですし、残り40%に関しては、強化しよう、わかっている人に習おう、本番まで時間がないので20%は捨てて残り20%をなんとかしようなどの行動につながりやすくなります。
A:私にはそれは無理だ。
B:今までの私にはそれは難しい。
何かを判断する時、人は「過去の記憶」と「現在の状況」を材料にしがちです。この2つに「未来の可能性」という3つ目が加わると、Bは「C:1年後にはそれができそうだ」「D:これとこれをクリアすればできるかも」などの可能性を導くでしょう。
A:どうやって実現しよう?
B:実現のために何をしよう?
Aは英語で言えばHowにあたります。ゴールまでの行き方を模索している状態ですから、この問いを考え出すと、「辿り着くまでの障害」もイメージしてしまうので、いつの間にかAが「E:障害に対してどうやって対応するか」にすり替わってしまうことがあります。そしてすり替わっていることに気づかず、「Eを考えることがAを考えることだ」と無自覚に捉えてしまうことも。順番としても「どうやって」が先にきてしまうので、脳内でも「どうやって」が先にインプットされてしまいます。
日本語文法の特性上、「アフリカゾウが歩いているところを想像しないでください」と言われても、必ず想象してしまう(おっと、想像でした)ように、「どうやって実現しよう?」は「実現」もちょっとゆらいでしまう感じがあります。
 『強さの磨き方』(アチーブメント出版)
『強さの磨き方』(アチーブメント出版)二重作拓也 著
それに対してBの問いはWhatですから、Aの手探り感を消去でき、Whatに具体的に答える形になります。本場のフランス料理を学びたい、ならば「フランスへ修行に行く」「語学を学ぶ」「航空券を調べる」「必要な経費を計算する」などの具体的な行動が導かれます。そしてゴールのみならず、ゴールから発想した過程をイメージできる、という嬉しい副反応もついてきます。
A:私が全て悪かった
B:私の○○○が間違っていた
何かに失敗した時、人から責められることがあります。もちろん明らかに悪意のある場合、取り返しのつかない結果を生む場合、無自覚でそれをやってはよくない場合など、全てを見つめ直さなければならない場合もあるでしょう。
一方で、そこまでではないことも結構あります。SNSが見事に可視化しているように世の中にはオール・オア・ナッシングの考え方の人、内容に関係なく非難する人、とにかく邪魔をしたい人、反対のための反対をする人も一定数います。ですから失敗した時には「お前が全て悪い」的に全否定されることがありますが、自分でも「私が全てが悪かった」と考えてしまうと「どこを、どのように、どの程度、修正すればいいのか」が、全くわからなくなってしまいます。
Bであれば、「私の○○○」の部分にフォーカスできます。それが「方法」であれば「タイミングを見直してみよう」「準備期間をしっかり設けよう」「チームの意思疎通をはかろう」となりますし、「動機」であれば「お金を得ることばかり考えていた」「虚勢を張ってばかりだった」という具合に修正、改善につながっていきます。
思考する言葉を変えるというのは、パソコンのOS(オペレーティングシステム)を更新するようなものです。「他人を変えるのは難しい、自分を変えるしかない」というのはたしかにその通りなのですが、「自分は変わりたくない、他人や周りを変えたい」と思ってしまうのも人間です。であるならば、「自分の使っている言葉」を「過去の私が使ってきた言葉」として、一度自分から完全に切り離し、OSを未来語にアップデートしてみるのはいかがでしょうか?