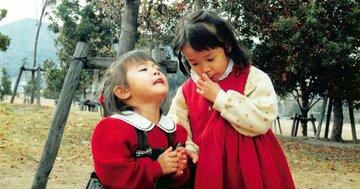写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
強くなるとは、理想の自分に近づくということ。苦手を克服する、関心のなかったジャンルに触れる、ネガティブな考え方を前向きにする…。これらはすべて強くなるためのステップですが、なかでも言葉を「未来語」に変える方法は、今すぐにできる強さの磨き方です。本稿は、格闘技実践者であり医師でもある二重作拓也氏の著書『強さの磨き方』(アチーブメント出版)の一部を抜粋・編集したものです。
意識共有のために
存在する言葉
強くなるための有力なギア、それが「言葉」です。私たちは生まれた時代も場所も境遇も遺伝子も変えることができません。環境、体重、筋力などは継続によって変えることができますが、変化させるのに時間がかかります。今すぐに確実にできること、それは「言葉を変える」です。
言葉を大きく2つに分けると「共有のための言葉」と「自分のための言葉」があると考えています。
共有のための言葉、それはシンプルに言えば「約束」です。たとえば、「心臓とは何ですか?」という問いに対して心臓外科医、オリンピック金メダリスト、小学生では、経験も立場も行動範囲もボキャブラリーも全て違いますから、「心臓」という言葉に対して出てくる答えは同一ではないはずです。
それでも全員にとって「心臓という言葉がどんなものを表しているか」の概念についてはおそらく同一です。なぜなら心臓という言葉が、共通の約束事として共有されているからです。
「アイスクリームのことを今日から心臓と呼ぶことにしました」とか「来年の4月1日よりスマートフォンは心臓と言い換えます」とかいうことは基本的にはないのです(サーティワン心臓でバイト中に、心臓が水没して動かなくなったので心臓ショップへ行く途中、お腹が空いたのでコンビニで6個入りの心臓、ピノを買うことになります。そんなの嫌です)。ですので、既に定着してしまっている共通の約束事としての言葉は簡単に変えられるものではありません。
同時に、とても興味深いのは、共通の約束事としての言葉も「新しい」の出現によってどんどん変異してしまうことです。コロナは王冠の意味であり、その名の付いた自動車も企業もビールもあります。しかし2019年末以降は、新型コロナウイルス感染症を想起させてしまいます。COVID-19という呼称のほうが各方面にとって「優しいアナウンス」なのは明らかですが、コロナのほうが言いやすいために、共有しやすく、広まりやすいのです。
PCRという検査も、ポリメラーゼ連鎖反応(Polymerase Chain Reaction)の略であり、DNAやその断片を複製して増殖させる方法(PCR法)として、生物の研究分野や医療現場において応用されてきたのですが、コロナ禍以降はCOVID-19の検査としてPCRの3文字が独り歩きし、それがスタンダードになった感もあります。
このように「共有のための言葉」も人間同様、変化を遂げます。ですから今、どんな言葉がどのような意味で使われているかを意識することは、時代の把握につながるのだと思います。
私たちには
「言葉を変える自由」がある
そして、自分のための言葉。これは共有が目的ではなく、認識や思考のためのパーソナルな色彩の強い言葉です。たとえば「趣味と仕事の違いは何ですか?」の質問に、唯一の正解はありません。別の見方をするならば、質問の答えには「その人の認識が表れる」ということでもありましょう。
私は20代の頃、「自分のやりたいこと」と「(飯を食うために稼ぐを含めた)自分がやらなければならないこと」について迷いの暗闇の中にいたのですが、ある言葉が光の方向を教えてくれました。
「好きなことをしてお金を払うのを趣味という。好きなことをしてお金をもらうのをプロという」
ジャーナリスト・田原総一朗氏の言葉でした。彼の短い二文の中に、私はみっつの大切なことを見つけました。
ひとつ目は「好きなことをやっていい」の肯定です。「嫌いなことでも歯を食いしばり、時には心をボロボロに擦り減らしてでもやれ!」という昭和的ファシズムもなく、「仕事が何よりも大切だ」という同調圧力も感じられない言葉に、「好きなことを追求していい」というパスポートを手にしたような気持ちになりました。
ふたつ目は同じ「好きなことをする」にも、ふたつのサイドがあるということです。本を読むだけなら、読書家のまま。音楽を聴くだけなら、音楽ファンのまま。お酒を飲むだけなら、愛飲家のまま。プロの側に立つには、好きなことに「価値」をもたせる必要があるのです。
有り難いことに、田原氏のプロの定義には「食える、食えない」の基準がありませんでした。たとえ500円であっても100円であっても、お金の流れが逆になれば、それはプロと考えていい。彼の言葉をそのように都合よく解釈しました。
私が20代の頃は「プロとはそれで食える人」というなんとなくの不文律があって、「専従でなくてはならない」みたいな空気が支配的でした。でも、「いきなり好きなことで生活費を稼げる状態になるって結構なジャンプだよな」と思っていたので、彼の言葉は救いになりました。
それから20年以上が経過し、「働き方改革」「副業OK」「好きなことで生きていく」といった言葉がメディアを賑わすようになりました。好きなことを徹底追究し、みんなにわかりやすく、楽しく伝える「さかなクン的才能」がどんどん世間に認められました。そしてタレントや芸人さんたちの「こだわりの趣味」とプロとして磨いた「話術や表現力」が見事に掛け合わされ、コンテンツとして価値をもつようになりました。企業に勤める人が、複数の収入源をもって生きるのも特別なことではなくなってきました。時代は、田原氏の言葉の方向に進んでいったのです。
みっつ目は、「言葉の再定義」は積極的にやっていいという肯定です。自分のための言葉は、どんどん意味を考えたり、新しい視点を足したり、余計なものを引いたり、思い切って更新したりして構わない。私たちは「言葉を再定義する自由」さえ手にしていることに気がつきました。
たとえば「時間だけは皆に平等に与えられている」とよく言われます。日本においては明治6年1月1日からグレゴリオ暦が導入されました。「約束事としての24時間」はたしかにその通りです。約束事としては平等ですが、これが個人レベルの「時間」となると、全く様相が変わってきます。そこでこのように再定義してみました。
時間とは何か?時間は「命」を分割したもの。90年生きれば1年は「1/90の命」3カ月は「1/360の命」。時間の使い方=命の使い方。この意識を強くもつと、時間を大切にするようになる。自分の時間も他の人の時間も。平気で時間を奪いに来る人たちから命を守ろう。憂いなく動ける時間は案外短い。
「時間」という無限に続くであろうものを、時限爆弾を抱えた「自分の寿命」と関連付けて考えた場合、時間の与えられ方は全く平等ではないことに気づかざるを得なくなります。1年の意味、1カ月の意味さえ、誰ひとり同じではない。時間の使い方が「その人のライフ」になる。「時間」を自分なりに定義したことで「意義のあることにライフを使おう」「今鍛えておけば、動ける時間を長くできる」「関わってくれる人たちの時間を無駄にしないようにしよう」など、自分を方向付けるパワーが生じたのです。
私たちは「言葉を変える自由」を手にしています。せっかく未来が変わるギアを手にしているのに、その自由を駆使しないのはあまりにも勿体ないと思うのです。自分らしくない言葉、腑に落ちない言葉、お仕着せの言葉、何も動かない言葉、思考停止を導く言葉をそのままにしておくことはありません。どんどん現実が動き出す言葉に変換して構わないのです。