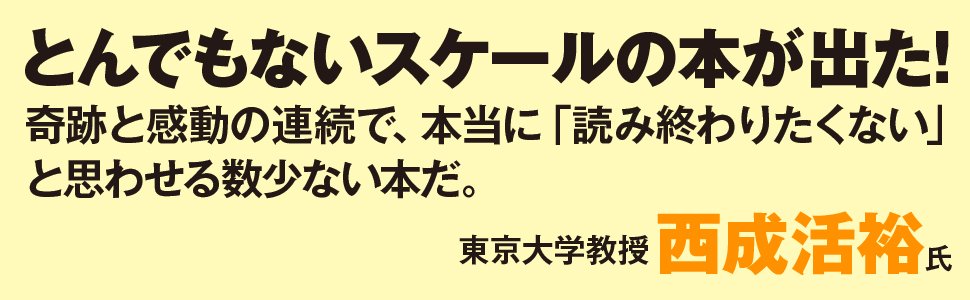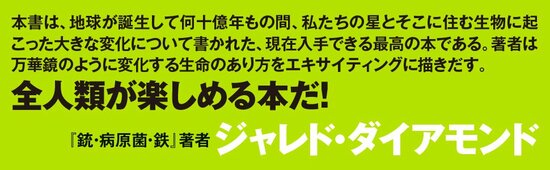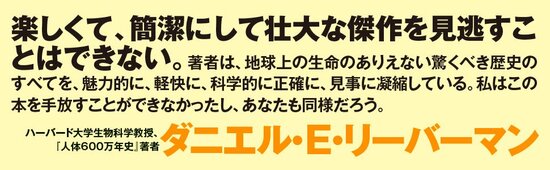「この成功法則の通りにやれば、うまくいきます」。この世には、そんな「ハウツー」や「メソッド」があふれている。それらを習得することは、仕事や人生をうまくいかせる上で、ある程度は有効だ。しかし、次に何が起こるか予測不可能な今の社会では、「成功パターン」に頼りすぎることはむしろリスキーだと、サイエンス作家・竹内薫さんは語る。
今回は、「地球の誕生」から「サピエンスの絶滅、生命の絶滅」まで全歴史を一冊に凝縮した『超圧縮 地球生物全史』(王立協会科学図書賞[royal society science book prize 2022]受賞作)の翻訳を手がけた竹内薫さんに、ビジネスパーソンが抱く悩みを、生物学的視点から紐解いてもらうことにした。
生命38億年の歴史を超圧縮したサイエンス書として、ジャレド・ダイアモンド氏(『銃・病原菌・鉄』著者)にも「著者は万華鏡のように変化する生命のあり方をエキサイティングに描きだす。全人類が楽しめる本だ!」と言わしめた本書を読み解きながら、人間の悩みの本質を深掘りしていく。あらゆる困難に直面しながら絶滅と進化を繰り返してきた生命たちの奇跡の物語は、私たちに新たな視点を与えてくれるはずだ。本稿では、「人間のメンタルが折れやすい理由とは?」をテーマに、お話を伺った。(取材・文/川代紗生)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「不安」の根源は「死後の世界」への恐怖
――メンタルが弱く、まわりにどう思われているか気にしすぎてしまう……と、悩んでいる人も多いと思います。そもそも、「不安」や「恐怖」という感情はなぜ生まれたのでしょうか?
竹内薫(以下、竹内):人間に、不安や恐怖が生まれたのは、「死後の世界」の概念ができたからだと思います。
――「死後の世界」ですか。
竹内:はい。僕たち人間は、「死後の世界」があることを前提に行動しているため、やたらと「死ぬのが怖い」「死んだらどうなってしまうんだろう」と想像を膨らませてしまいます。
これが、人間が持っている不安の根源だと思います。
僕たちは当たり前のように「死」を認識していますが、動物たちには「死」の概念がありません。
同じヒト族でも、「死」の概念を持たない種もいました。
たとえば、50万年ほど前、ヒト族の一種ホモ・エレクトゥスがあらわれました。彼らは背筋を伸ばして二足歩行をしており、現在の僕たちとよく似た姿をしていますが、現代人と比較すると非人間的なところがあった、と『超圧縮 地球生物全史』には書かれています。
ほとんどのほ乳類は、生まれてから急速に成長し、できるだけ早く繁殖し、繁殖能力を使い果たすとすぐに死んでしまう。ホモ・エレクトゥスも同じだった。子どもは、人間の特徴である長い幼児期がなく、幼少期から成熟期へと急速に成長する。死んだら、死体は顧みられず、腐敗するままに捨て置かれた。ホモ・エレクトゥスには死後の世界という概念がなかった。天国を想像することもなかった。地獄を恐れることもなかった。(P.223)
――死体は腐敗するままに捨て置かれた……というのは、たしかにあまり人間らしくないですね。そうか、ホモ・エレクトゥスには、「今」をどう生きるか、という考えしかなかったわけですね。
竹内:現代人、つまり、ホモ・サピエンスが、どの段階で「死後の世界」に気が付いたのかについてはさまざまな説があります。
「死後の世界」への不安があることが、いい影響をもたらしたのか、悪い影響をもたらしたのかはわかりませんが、いずれにせよ、「死」を認識していることが、ホモ・サピエンスの特徴の一つと言えるでしょう。
「メンタルが超強い人」でなければ無宗教は難しい
――「周りの目を気にしてしまう」「他人にどう思われているか気になる」という気持ちも、結局は、「嫌われて、集団から排除されて、生きていけなくなったらどうしよう」という、死への恐怖に行き着きますね。
竹内:そういった不安を取り除くために、古くから、「宗教」を仕事にする人たちが登場しました。彼ら宗教家の役割は、死後への恐怖を取り除くことですよね。
「死後の世界はこうなっています。今、こうして善い行いをしていれば、死後も生まれ変わって天国に行くことができます」というストーリーを作ってあげることで、信者を安心させる役割を担ってきました。
ところが、現代社会では、その既存宗教の力が弱まってきました。両親はカトリックだが、自分はもう教会には行かないなど、特定の宗教を持たない人も増えてきました。
となると、宗教を持たない人たちは、自分の力でその不安を乗り越えなくてはならなくなります。
僕は正直に言って、宗教を持たずに自分一人で恐怖心と戦うのは、相当メンタルが強くないと難しいと思っています。
死ぬとはどういうことか、現代科学における「死」の定義とは何か……。
突き詰めて考えていっても、「心臓が停止し、脳波が消えた瞬間に、自分というものは無くなる。それで終わりだ」という結論に辿り着く。
はたして、それを受け入れることができるか? と考えると……難しいですよね。
――言われてみれば……。科学的な説明では納得できないからこそ、ぐるぐると考え続けてしまうわけですもんね。それに、誰も「死後の世界」に行ったことがないから、たしかめようがないという怖さもあります。
竹内:あるいは、哲学者の話をたくさん読み、古今東西の哲学者たちがどのように死と向き合ってきたのかを知り、自分なりに死への心構えを作っていく、ということもできるでしょう。
ただ、個人でやるには、結構骨の折れる作業ですよね。だから、無宗教でいるというのは、僕たちが思っている以上に、心の体力を使うものなんだと思います。
つかみどころのない「死」というものへの恐怖と、一人で対峙しなければならないわけですから。
「理不尽な死」への恐怖にどう立ち向かう?
――死への恐怖と向き合うために、竹内さんが個人的にされていることはありますか?
竹内:僕は、猫が大好きで、昨年、猫を4匹飼っていたんです。そのうちの1匹が死んでしまったとき、僕はすごく悲しかったのですが、他の猫3匹は、普段通りでした。
僕たち人間はわんわん泣いて、遺体を箱に入れたり、お花を飾ってあげたりと、「死後の世界」へ送り出す儀式のようなものをしていたわけですが、猫たちは、普通に「ごはんちょうだい」といつも通りにやってくるんです。
仲良くしていたし、一緒に寝ていた1匹が、なんとなく弱って、小さくなって、あまり動かなくなって、彼らの社会から消えてしまった。
でも、それに対して、他の猫たちは、特に何も考えていない様子に見えました。「今の世界」にその猫はいなくなった。それだけ。だから、過去のことを思い出してくよくよしたりしない。
そういう彼らの様子を見ていて、学ぶべき点があるな、と思いました。
一緒にいた時間はとても楽しかった。いい家族だった。それはもう終わったこと。
だから、「今」を生きよう、と。そういう割り切り方もあるのかなと思うんです。
――そうですよね。『超圧縮 地球生物全史』を読んでいても、予告なく、理不尽に死がやってくるんだな、と痛感しました。いろいろな生き物が生きて、死んでいく。その繰り返しで、自分はあくまでも、その世界の一部でしかないんだな、と。
竹内:否応なく死んでしまう状況が当たり前だという事実が、この本には書かれていますよね。
たとえば、恐竜の世界は、約6600万年前の小惑星の衝突で、一夜にして終わりを告げました。『超圧縮 地球生物全史』には、恐竜たちが一瞬で絶滅したときのことについて、こんな描写がされています。
目がくらむような閃光につづいて、想像を絶する騒音をともなった時速1000キロメートルの疾風が、カリブ海地域と北米のあらゆる生命体を破壊し、その後、熱風にのって全世界に「焼夷弾」が降り注ぎ、木々は松明と化した。津波がメキシコ湾中の海水を引きずり出し、戻る波が、高さ50メートルの高さで海岸に打ち寄せ、100キロメートル以上も内陸に達した。(P.162)
――すごい描写ですよね。まるでその場にいるかのような臨場感のある描写で、ぐんぐん引き込まれます。地球全体を舞台にした壮大な物語を読んでいるようで、本当にワクワクしました。
竹内:我々が今、いかに稀有な状態で生きているのか、本書を読むとよくわかりますよね。奇跡に近いぐらい、実は幸せな環境で生きているということが、実感できるのではないでしょうか。
環境の変化が来て、必死にそれに抗ったとしても、数世代のうちに滅んでしまう。それが当たり前のことなんだと知るだけでも、自分の人生の見方が、多少変わってくるかもしれません。
何が起こるかわからない不安定な世の中だからこそ、絶滅を繰り返してきた地球の歴史に耳を傾けてみてほしいな、と思います。
まるで、タイムマシンで46億年を一気に駆け抜けたような感動と驚きを、ぜひ、味わってほしいですね。
1960年東京生まれ。理学博士、サイエンス作家。東京大学教養学部、理学部卒業、カナダ・マギル大学大学院博士課程修了。小説、エッセイ、翻訳など幅広い分野で活躍している。主な訳書に『宇宙の始まりと終わりはなぜ同じなのか』(ロジャー・ペンローズ著、新潮社)、『WHOLE BRAIN 心が軽くなる「脳」の動かし方』(ジル・ボルト・テイラー著、NHK出版)、『WHAT IS LIFE? 生命とは何か』(ポール・ナース著、ダイヤモンド社)、『超圧縮 地球生物全史』(ダイヤモンド社)などがある。