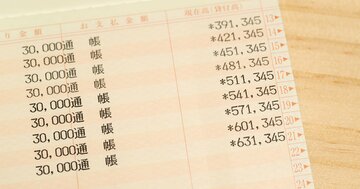人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
認知症になったら、相続は超大変です
遺言書は大きく分けて、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。
遺言書がない場合、相続人全員の同意がなければ、遺産の分け方を決めることができません。「それでは遺族の間で相続争いが起こってしまう可能性が高いし、調停や審判となるといろいろ面倒……」ということで、ほとんどの家庭では本人自身が自筆する自筆証書遺言をつくるのですが、これでも万全とはいえません。自筆証書遺言には、紛失や破棄といった保管上のリスクが常に生じます。誤った書き方をしているために無効になるおそれもあります。
加えて、とくにトラブルが起きやすいのは、本人が認知症だった場合です。認知症になった人は法律上「意思能力のない人」と扱われる可能性があり、実際、認知症発症後につくられた自筆証書遺言が裁判によって無効とされたケースも多数あるのです。
「ならば」と、プロを頼って公正証書遺言を作成しようとする家庭も多くいますが、認知症が進んでしまうと、それすらも困難になってきます。本人に認知症の兆候が見られたら、一刻も早く相続対策を行うに越したことはありません。
事例紹介
知り合いの税理士からこんな話を聞きました。
Aさんという女性が相談に訪れます。Aさんのお父さんはすでに他界していて、Aさんはお母さんと2人暮らしです。Aさんはお母さんの介護をひとりで担っていました。
Aさんには妹がいますが、その妹は遠方に嫁いでおり、介護はAさんに任せっきり。Aさんはそのことに腹を据えかねており、「母の遺産は、私が妹より多く相続できなければ納得できない。母にもそのように遺言書を書いてもらう」という意思を持っていました。ただ、お母さんには痴呆の症状が見え隠れしていたそうです。
今の状態で、Aさんが妹より多くの遺産を相続する旨の自筆証書遺言をつくったところで、のちのち、遺言書の有効性を巡ってAさんと妹の間で争いが起きることは目に見えています。そこでAさんに、自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言をつくるよう勧めたそうです。
公証人も「お手上げ」になってしまう場合もある
公正証書遺言は、公証役場で、公証人という法律のスペシャリストが本人の意向を確認して作成します。費用は5万~15万円ほどかかりますが、遺言書を公証役場で預かってもらえるために紛失や破棄等の危険性がなく、書き方の誤りで無効な遺言になる可能性もないのが大きなメリットです。
公正証書遺言の作成サポートを専門家に依頼した場合の作成順序としては、まず、本人やその家族から相談を受けた弁護士や税理士、行政書士、司法書士が、どのような内容の遺言書をつくりたいかを依頼人から聞き取り、公証役場に伝えます。
すると公証役場が遺言書の原案作成にかかります。原案ができ上がったら、本人を含む依頼人と弁護士や税理士、行政書士、司法書士が一緒に公証役場に出向き、読み合わせをして、問題がなければ本人が印鑑を押し、遺言書の完成となります。
Aさんの場合も、原案(Aさんが妹より多くの遺産を相続する旨の遺言書)の作成まではすんなりと進みました。しかし、読み合わせと押印の当日に、事件は起きてしまいました。
公証人が遺言書の原案を提示し、「この内容で間違いはないですか?」と問いかけたところ、お母さんは「これ、誰の遺言書?」と話したそうです。お母さんの痴呆は、想像以上に進んでしまっていたのです。慌てたのはAさんです。
公正証書遺言をつくるときのルールとして、「家族は、公正証書遺言をつくる場にいてはいけない」というものがあります。しかし中には、パーティションで仕切られているだけで、本人とご家族は同じ部屋内にいて、声が筒抜けになることもあります。このときも声が筒抜けになっていたので、動転したAさんは席を立ってお母さんの元に駆け寄り、「お母さんしっかりしてよ!」と詰問したといいます。
公証人は「このような状態では、私たちは遺言書をつくれません」と、遺言書の作成を辞退。Aさんは「自筆証書遺言をつくる方向で考えます」と言い、帰宅していきました。その後の顛末はわからないそうです。認知症が進んでしまった場合の相続対策がいかに難しいかを痛感させられるエピソードです。
実際には、「認知症が進んでしまっていたとしても、医師2人の立ち会いがあれば、遺言書はつくっていい」と法律で定められています。
しかし現実問題として、そこまで協力してくれる医師がいるかどうかは疑問です。言うまでもなく、医師は通常の医療業務で忙しいですし、何より「のちのち揉めそうなことには関わりたくない」「遺言によって不利な状況に置かれる家族から恨みは買いたくない」と考えるのもまた自然なことだからです。やはり「認知症の兆候が見られたら、一刻も早く相続対策をする」のが、最善の対策であるといえます。
(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋・追加加筆したものです)