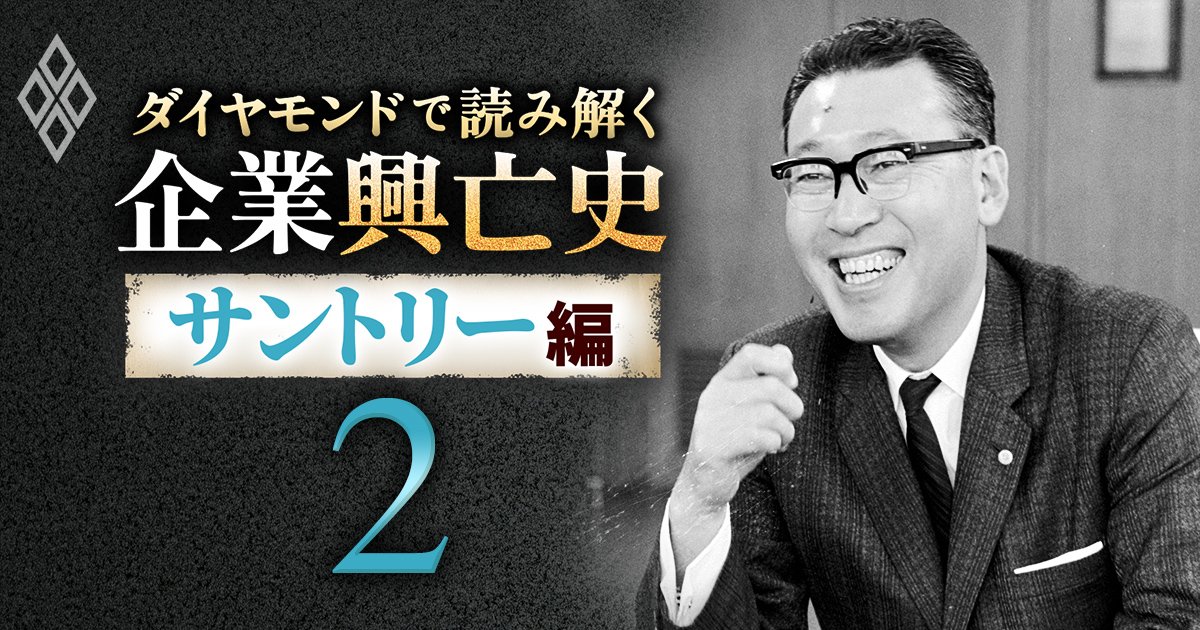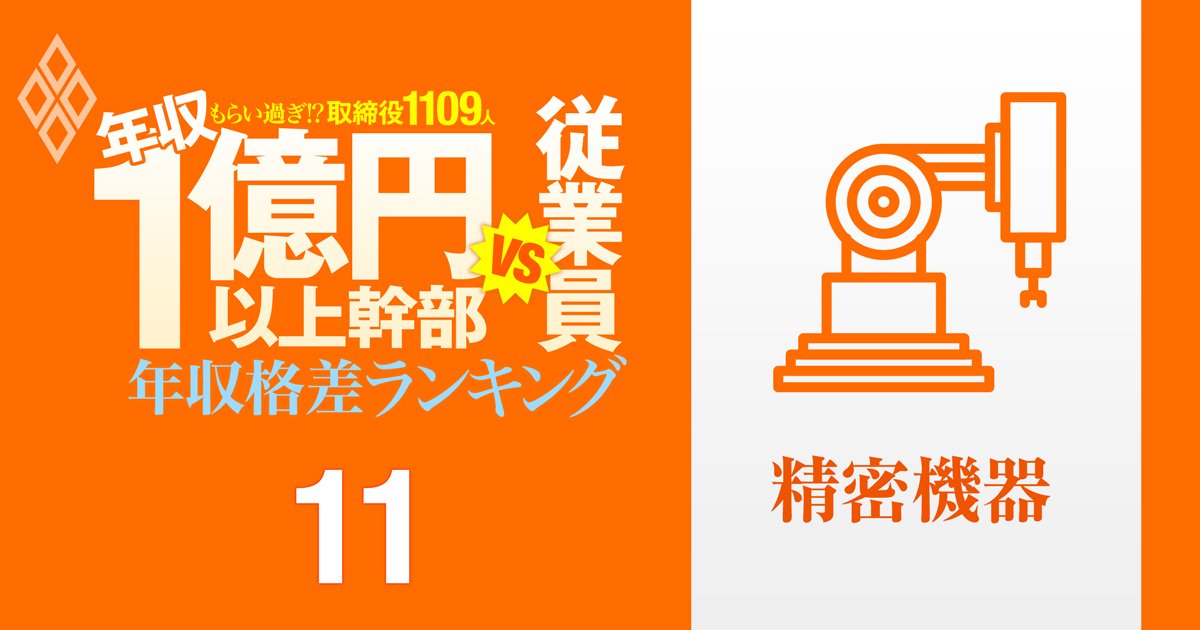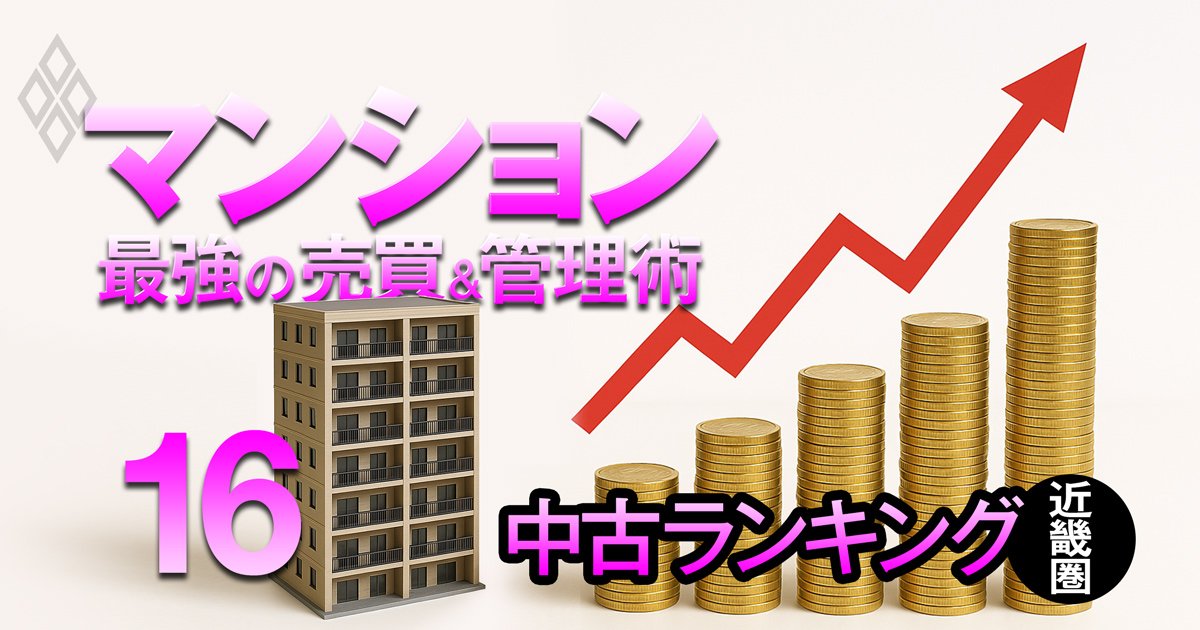そこで、余剰資金である138万6000円のうち、約半分の68万円を貯蓄に追加することにしましょう。保険金やつみたてNISAといった「今後の備え」への拠出額は、前述の通り年間102万円ですが、これに68万円をプラスして170万円にする前提で試算を進めます。
そうすると、Oさんは現在50歳ですから、60歳で定年退職を迎えるまでの10年間で1700万円を現在の金融資産に上乗せすることができます。
※今回の試算では、試算対象の年齢になった誕生日から、次の誕生日までの期間を「1年」として計算しています。
Oさんは現在、金融資産として普通預金・つみたてNISA・個人年金など計3630万円を保有しているほか、娘さん用に養老保険1000万円を確保しています。
今回の試算では、娘さん向けの養老保険は資産に組み入れず、上記の3630万円のみをOさんの資産として考えます。また、個人年金は本来、分割された金額を老後に受け取りますが、今回は便宜上、積み立て済みの金額を「現在の資産」に織り込みます。
試算に話を戻します。Oさんは60歳で定年退職を迎えた段階で、前述の1700万円と、相談文に記載のある1600万円の退職金を受け取れるので、合計で6930万円(3630万円+1700万円+1600万円)の金融資産を保有しているはずです。
Oさんの金融資産は
目標の「100歳」まで持つ?
それでは、この資産額で100歳まで持ちこたえられるのかを試算してみましょう。
まずは定年退職後の一時的な費用を差し引くことにします。Oさんが考えている定年退職後の一時的な支出は、自動車の買い替え(300万円×2回程度)、家電の買い替え(最低3回)、そして家のリフォームです。
家電の買い替えは「金額」、家のリフォームは「金額と回数」の記載がないため、前者は1回当たり100万円、後者は1000万円×1回としておきます。
ただし、家電の買い替えは「最低3回」と記載があるので、今回は多めに見積もって4回としておきます。