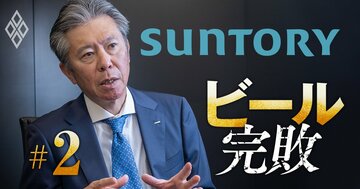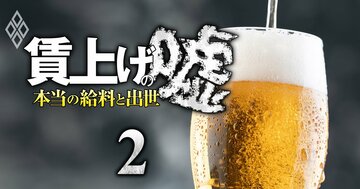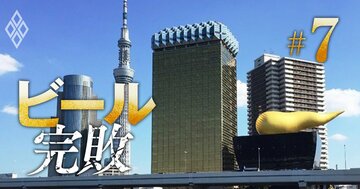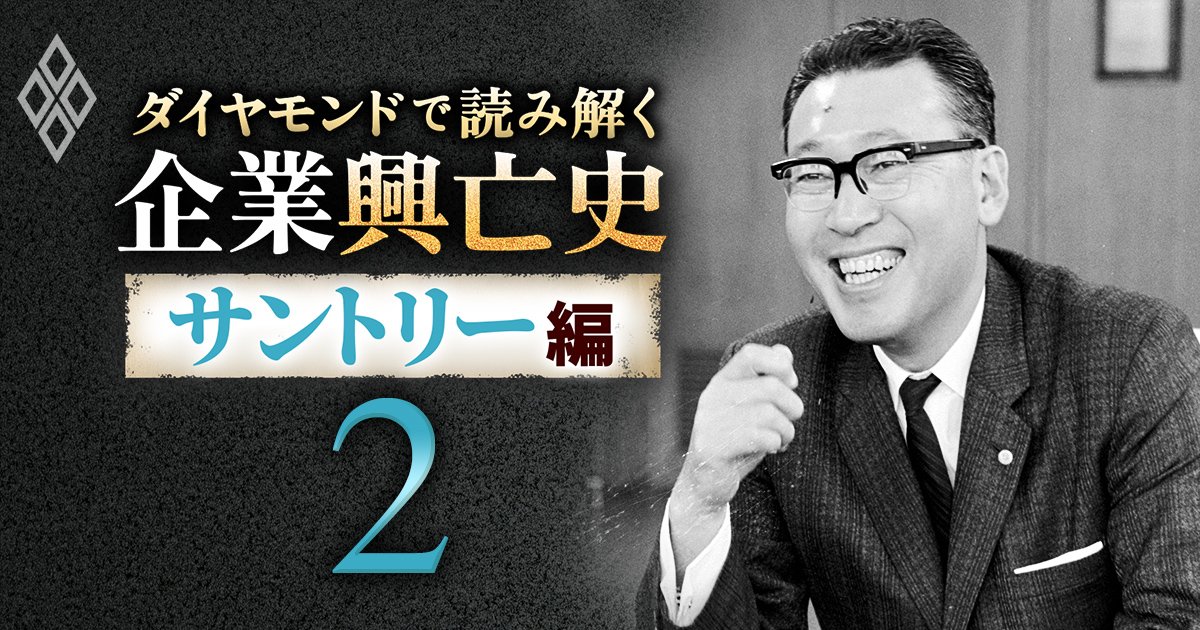 写真:毎日新聞社/アフロ
写真:毎日新聞社/アフロ
今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。1899年に「鳥井商店」として産声を上げ、創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡を「ダイヤモンド」の厳選記事を基にひもといていく。1963年4月、創業者である鳥井信治郎の次男で2代目社長の佐治敬三がビール事業に参入する。ただ、ビール事業はその後、長く苦闘が続き、「やってみなはれ」のチャレンジ精神の象徴の一つともなる。連載『ダイヤモンドで読み解く企業興亡史【サントリー編】』の本稿では、ビール事業への参入からわずか半年後の「ダイヤモンド」1963年9月10日号に掲載された、佐治のビールへの強い思いと覚悟を語った記事を紹介する。「念願はビールの一本立ち」と題する記事の中で、佐治はビール事業を「父子二代の執念」と形容した上で、シェアトップだったキリンビール打倒へ不退転の決意を示している。また、好調だった大黒柱のウイスキー事業については、北米市場の開拓計画も明かしている。(ダイヤモンド編集部)
3社寡占のビール市場にサントリーが参入
「あえてわれわれは困難な道を選んだ」
いま、私の頭の中にあるものは、サントリービールを、一日も早く一人前にすることだ。ビール全体の伸びは、予想以上に早いが、全需要の1割をサントリービールで占めたいと念願している。全需要が1000万石なら100万石を……、1500万石なら150万石を……。
いま、日本のビール界は、キリン(現キリンビール)の独走に任せている。これは正常な姿ではない。米国にはたくさんのビール会社があり、欧州に至っては論外で、ドイツには3000種類ものビールがある。
日本は戦後、キリン、アサヒ、サッポロの3社が独占してきたがタカラに続いて、サントリーが出たわけで、5社のビールがそれぞれ違った味を持ち、それぞれのファンを持つというのが本当の姿だと思う。
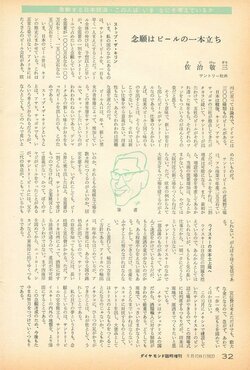 「ダイヤモンド」1963年9月10日号より
「ダイヤモンド」1963年9月10日号より
そういう意味で、新しい形を打ち出したビールがサントリービールなのである。仕事の上からいえば、従来のビールと同じ味のものを出すことは、そう難しいことでない。しかし、それでは新しい仕事をやる意義がない。将来性もない。あえてわれわれは困難な道を選んだのだ。