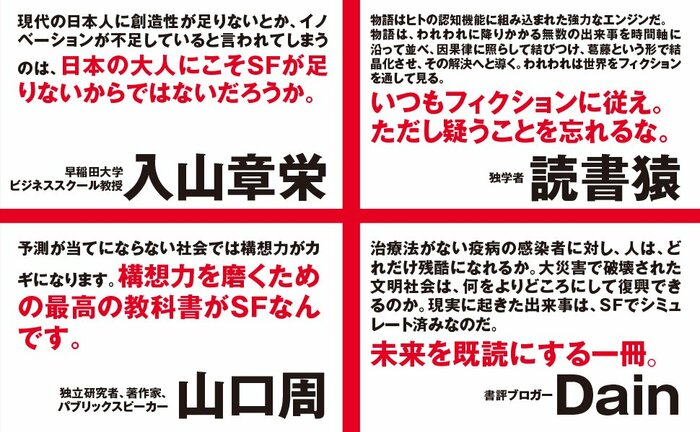『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』著者の冬木糸一さんは、SF、つまり物語を現実が追い越した状況を「現実はSF化した」と表現し、すべての人にSFが必要だと述べている。
なぜ今、私たちはSFを読むべきなのか。そして、どの作品から読んだらいいのか。この連載では、本書を特別に抜粋しながら紹介していく(※一部、ネタバレを含みます)。
『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』の著者の冬木糸一です。エンジニアとして働きながら、ブログ「基本読書」などにSFやらノンフィクションについての記事を、15年くらい書き続けています。
僕はSFを「現代を生きるサバイバル本」と位置付けています。理由は、イーロン・マスクを代表とする起業家たちのインスピレーションの源が、SFだからです。彼らは文字通り、今ビジネス、そして世界を動かしています。頭のいい人ほど、フィクションから発想を得ていると考えることもできます。
今回は本書のなかから「人工知能・ロボット」関連の本を紹介します。
どんな作品か:「アンドロイドの殺害」を請け負った賞金稼ぎの苦悩
『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』
─人間とアンドロイドの違いは何か? 人間とは何か?

没後40年を経て忘れ去られるどころか、ますます作品の現代性が際立つフィリップ・K・ディック。『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』は、彼の代表作であり、映画『ブレードランナー』(リドリー・スコット監督、1982)の原作として、後世のSF作品のヴィジュアルに圧倒的な影響を与えた長編小説だ。
舞台は、〈最終世界大戦〉が起こり、放射性降下物(核兵器や原子力事故などで生じた放射性物質を含んだ塵)が充満したサンフランシスコ。灰色の天気が続き、多くの人間は貧困に苦しんでいる。さらには自然環境が壊滅しているせいで、天然の動物がほぼ存在しなくなっている。人類も死の灰による汚染を受け、一定期間ごとの検査に合格しなければ、法律で生殖すら許されない。遺伝的安全性を確保するために、人類には地球外のコロニーへの移住が推奨されている。
そんな世界では、羊やカエルなど、天然の動物を飼うことがある種のステータスになっている。それを持てないものは馬鹿にされ、下に見られる。しかし、本物の数は少なく、電気仕掛けの模造品で我慢する人たちもいる。
本作の主人公にして、賞金稼ぎであるリック・デッカードもその一人。もともと本物の羊を飼っていたのだが、その羊が破傷風にかかって死んでしまい、その後は〈電気羊〉を飼っている。デッカードはせめてうさぎでもいいから本物の動物が欲しいと願っているが、それすらとても手に届く金額ではない。
そんなある日、金に困っているデッカードのもとに賞金稼ぎの依頼が舞い込む。火星から逃亡してきた8体の奴隷アンドロイドを始末してほしいという仕事だ。この8体は〈ネクサス6型〉と呼ばれるハイエンドなアンドロイドで、一見したところ人間と見分けがつかないうえ、通常の人間をも超える知能を持つ。
人間と見分けがつかないアンドロイドを、どうやって見つけ出せばよいのか? そこで登場するのが〈フォークト=カンプフ検査〉という技術だ。単純な質問を重ねて、その反応を見ることで対象の〈感情移入度〉を測定し、人間かアンドロイドかを判定することができる。デッカードはこの技術を用いて、6体ものアンドロイド(抹殺対象の8体のうち2体は、すでに別の賞金稼ぎによって始末済み)を処理しなくてはならない。
しかしデッカードは、アンドロイドの殺害を重ねるうちに、彼らに対して感情移入するようになる。アンドロイドの中には、人間社会に自然と溶け込み、評価されていたものもいた。やがて相手がアンドロイドか否かだけではなく、自分が人間かどうかさえもが曖昧になっていく。
どこがスゴいのか:人間と機械を「二項対立」で考えるべきではない
本作を名作たらしめているのは、この「アンドロイドと人間を判別する」プロセスを通して、はたして両者にどれほどの違いがあるのかを問いかけてくるところにある。その先にあるのは「人間とは何か」という問いだ。
アンドロイドの中には、偽の記憶を埋め込まれ、自分がアンドロイドであることを自覚していないものもいる。彼らは検査を受けてアンドロイドだと判明すると、自分の世界が崩壊したように恐怖する。だが、そうした特別な検査を経なければわからないような─場合によっては検査を経てもわからない─アンドロイドと人間に、何の違いがあるというのだろう? 本作は、まさしくこうした「人間と非人間の境界線」をゆるがしている。
ディックは、「人間とアンドロイドと機械」と題したスピーチ原稿の中で、次のように述べている。
最近この世界に起きている最大の変化は、おそらく、生あるものが物体化へと向かい、逆に機械的なものが活性化へと向かう趨勢ではないでしょうか。生あるものと生なきもののあいだに、いまのわれわれはなんの区分法も持っていません。(中略)いつの日か、われわれは、二つの世界に片足ずつを踏まえた雑種の存在を、何百万も持つことになるでしょう。彼らを“人間”対“機械”として定義するのは、言葉の謎々をもてあそぶことになるだけです。
(フィリップ・K・ディック著、大森望編集・訳、浅倉久志訳
『アジャストメント ディック短篇傑作選』/早川書房 p407)
さらに続けて、ディックはこう言い切る─われわれは人や人間といった概念を、その起源や本体論に基づいてではなく、この世界での存在のありかたに基づいて適用すべきだと。人間が体の一部をサイボーグ化する一方で、アンドロイドや機械がその構造に純生物学的な要素を取り込んでいくようになれば、両者の成り立ちに差はほとんどなくなっていく。そのとき、人間性の本質とは、いかに「人間的なふるまい」をしたかどうか(たとえば他人に対して親切に接する、など)によって決められるべきだというのである。
「人間とアンドロイドと機械」の原稿は1975年に書かれたものだが、1972年にブリティッシュコロンビア大学で行われたスピーチ(The Android and the Human)でも、すでに同様の主張が見られる。
こうしたディックの指摘には、先見性があったというべきだろう。2020年代のいま、われわれはもはや、チャットやSNS上のやりとりだけでは相手が人工知能なのか人間なのかにわかには判断できなくなっている。1960年代には絵空ごとでしかなかった問いかけが、急速に大きな意味を持ちつつあるのだ。
一方で、人工知能による発言やアカウントを検出できるように、機械学習を利用してBOTを検出するツールも登場している(インディアナ大学ソーシャルメディア観測所が作成)。ディープフェイクと呼ばれる、ディープラーニング技術を用いた合成メディアは時に嫌がらせや政治的妨害に使われることがあるが(たとえば、オバマ前大統領夫人がストリップをしている映像を作成するなど)、こうした合成画像や映像をAIが作成したものだと見抜く技術もまた存在する。
フェイクをつくり出すAIと、それを検知する技術のせめぎあいは、『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』で描かれた、進歩を続けるアンドロイドと感情移入度検査の関係性を思わせる。いまはまだ、人間と見分けがつかないほど高度なアンドロイドは存在していないが、われわれはその前夜にいる。ディック作品が長く評価され、何度となく映像化され続けているのは、まさに将来の論点になるテーマに真っ向から挑んでいたからなのだ。
フィリップ・K・ディック
1929年、米イリノイ州生まれ。代表作に『高い城の男』『流れよわが涙、と警官は言った』『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』など。
※この記事は『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』からの抜粋です。