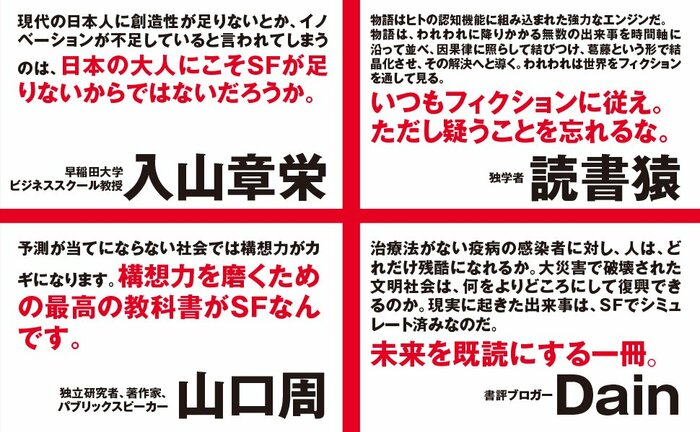『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』著者の冬木糸一さんは、SF、つまり物語を現実が追い越した状況を「現実はSF化した」と表現し、すべての人にSFが必要だと述べている。
なぜ今、私たちはSFを読むべきなのか。そして、どの作品から読んだらいいのか。この連載では、本書を特別に抜粋しながら紹介していく(※一部、ネタバレを含みます)。
『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』の著者の冬木糸一です。エンジニアとして働きながら、ブログ「基本読書」などにSFやらノンフィクションについての記事を、15年くらい書き続けています。
僕はSFを「現代を生きるサバイバル本」と位置付けています。理由は、イーロン・マスクを代表とする起業家たちのインスピレーションの源が、SFだからです。彼らは文字通り、今ビジネス、そして世界を動かしています。頭のいい人ほど、フィクションから発想を得ていると考えることもできます。
今回は本書のなかから「戦争」関連の本を紹介します。僕が最初にSFにハマった一冊です。
どんな作品か:未知なる異星人に対峙する特殊戦隊の活躍
『戦闘妖精・雪風<改>』
─戦うべき相手との「決死のコミュニケーション」
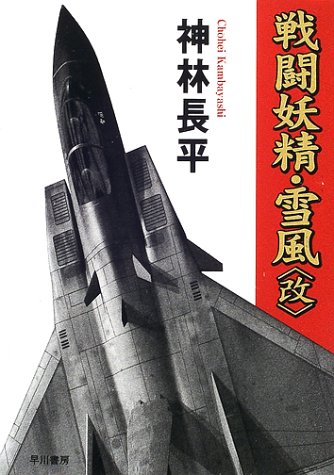 神林長平著/早川書房、2002年、シリーズ4巻、1984年〜
神林長平著/早川書房、2002年、シリーズ4巻、1984年〜
「戦闘妖精・雪風」は、日本を代表するSF作家、神林長平によるシリーズ作品だ。デビュー初期の1984年に第一作『戦闘妖精・雪風』が刊行され(2002年に『戦闘妖精・雪風〈改〉』として再刊)、続いて第二作『グッドラック』(1999)、『アンブロークン アロー』(2009)、『アグレッサーズ』(2022)と、著者の長いキャリアを通じて巻を重ねてきた。著者がその時々で追求していたテーマや思索が各作品に盛り込まれた、まさにライフワークというべきシリーズである。
本シリーズが描き出すのは、戦争といっても、人間の存在を認識しているのかどうかさえわからぬ異星体〈ジャム〉との戦いだ。したがって、まず「相手が何を考えているのか」を知ることが戦略の要となる。つまり、ジャムとの戦闘もさることながら、彼らとのコミュニケーションがメインテーマになっているのだ。
物語の舞台は、南極に出現した〈通路〉から地球に異星体ジャムが侵攻してきた世界。地球防衛軍がジャムに反撃すべく通路に踏み込んでいくと、その先には未知の惑星〈フェアリイ〉が存在していた。対ジャム戦における主力となったフェアリイ空軍(FAF)は、フェアリイ星側にある通路の入口を取り囲むように基地を建設し、ジャムの侵攻が地球に及ばないよう食い止めている。
フェアリイ空軍の主戦力は、〈シルフィード〉と呼ばれる大型戦闘機だ。なかでも〈スーパーシルフ〉と呼ばれる改良機は、人類と同等の知的生命体とみなしても差し支えないほど高度な人工知能を有している。
スーパーシルフが配属されているのは、「情報収集のために味方を見殺しにしたとしても必ず還れ」を至上命令とする偵察部隊〈特殊戦〉だ。この部隊では、隊員にも「他者に関心を持たない」排他的な人格が求められる。いわば「なにかの手違いで人間になってしまった機械」のような人材だ。そんな〈特殊戦〉隊員の資質を体現しているかのようなパイロット、深井零を中心にストーリーは進行していく。
どこがスゴいのか:「戦う意味」を根本からゆさぶり、問い直す
本シリーズを駆動するのは、多くの軍事SFが紙面を割く「戦況の分析」や「手に汗握るドッグファイト」などではなく、哲学的な問答だ。そのひとつに「戦争に人間は必要なのか?」という問いかけがある。
この世界では、高度に発達したAIが戦闘機をコントロールするのみならず、軍そのものの運営のかなりの部分を担っている。人間が戦闘機に乗っている限り、生命維持関連の限界が生まれ、本来機体が発揮できる性能は大幅に制限される。ならば、この戦争に人間など必要ないのではないか、というのはもっともな問いかけだ。機械が勝手にジャムと戦えばいいのだから。
深井零は、自身が搭乗する戦闘機〈雪風〉と深く繋がった存在であり、人間が戦場に出ることの意味を疑ってはいない。しかし、その理由まではわかっていない。彼は、上司であるブッカー少佐に理由を問いかけ、次のような返答を得る。
「人間に仕掛けられた戦争だからな。すべてを機械に代理させるわけにはいかんだろうさ」(p97)
なるほど、人間に仕掛けられた戦争であるならば、人間が応じるのは当然といえる。しかし─ジャムは先にも書いたように正体不明の異星体だ。突如地球を攻めてきた目的が何なのか、実際のところは誰にもわからない。
彼らの技術力からすれば、人間をとっくに支配できていてもおかしくなさそうなのに、そうはなっていない。ここで零は、ある可能性に思い至って愕然とする。ジャムは異星体だ。彼らが、地球の支配者は人間ではなく「機械」だと考えたとしても不思議ではない。人間は自分たちが戦争を仕掛けられたと思っているが、実際にはジャムが戦っているのは、人間が使役している(と自分たちでは思いこんでいる)機械のほうかもしれないのだ。だとすれば、人間が戦っている意味は根本から覆される。
はたして、これは人間が立ち向かうべき戦争なのか? それとも、実は機械に仕掛けられた戦争であって、人間はそれをはたから見ているだけなのが正解なのか?
それを知るためには、人類とはまったく異なる意識を持つはずのジャムの意図を知らなければならない。本シリーズを通して描かれるのは、この戦争における人間の存在意義を求め、ジャムの真意をはかるための決死のコミュニケーションなのだ。
無意識の思考の流れであっても、人間は「言葉」を用いることで強引にその意味を浮上させることができる。それは、機械にはない人間の強みだ。
第二作『グッドラック』では、人間には理解できない異質な知性・意識に対して、「言葉」を用いて自分たちの存在を認めさせようとする人間の苦闘が描かれる。これに並行して、雪風と零(機械と人間)の、単なるパートナーシップを超えた、お互いがお互いの一部でありながら異なる情報処理システムで世界を認識しているという、新たな関係性の構築が描かれていく。
第三作『アンブロークン アロー』では、零と特殊戦の面々は、雪風ら機械知性やジャムが見ている世界に入り込む。それは、人間の現実認識が通用しない領域だ。
たとえば、人間は特定の光の波長に色を感じるなど、自分なりの「認識」を通して世界を見ている。作中では、そうした解釈が入る前のむき出しの世界が〈リアルな世界〉と表現され、そこには時間もなければ、自分と他人の区別も、人と物体の区別もない、ただ〈可能性〉のみが存在する場所だと説明される。
ジャムや機械知性たちが認識している世界とは、そんな〈リアルな世界〉に近いものなのではないか。『アンブロークン アロー』では、そこでの体験を意識化&言語化することを通して、人間がジャムへの存在へとかつてなく近づいていく。
続く第四作『アグレッサーズ』では、ジャムが地球から去った(かのように見える)ことを受けて、代わりに特殊戦がジャムに「なりすます」作戦が浮上する。ジャムの真意がわからない以上、戦いは終結したとはいえず、防衛を解くわけにはいかない。しかし、フェアリイ空軍による長い平和で、ジャムの実体すら疑い始めた人々を納得させるためには、ジャムからの攻撃を演出し続ける必要があるというわけだ。ここに至って、これまでフェアリイ空軍とジャムの闘争(コミュニケーション)を中心に展開していた物語が、人類社会全体を巻き込んだ哲学的闘争へと発展していく。
人間とはまるで異なる異質な知性、そうした、人間の概念、言葉ではどうしたって表現できない〈何か〉を、なんとかして言葉ですくい取ろうとする姿勢。機械がいくら高度な機能を有しようが、人間の存在する意味を問い続ける過程。それが雪風がこれまで描いてきたものである。他では体験できない問いが、ここにはあるのだ。
1953年、新潟県生まれ。「創造」「言語」「意識」をテーマにした数々の作品で知られる。1995年、『言壺』で第16回日本SF大賞を受賞。