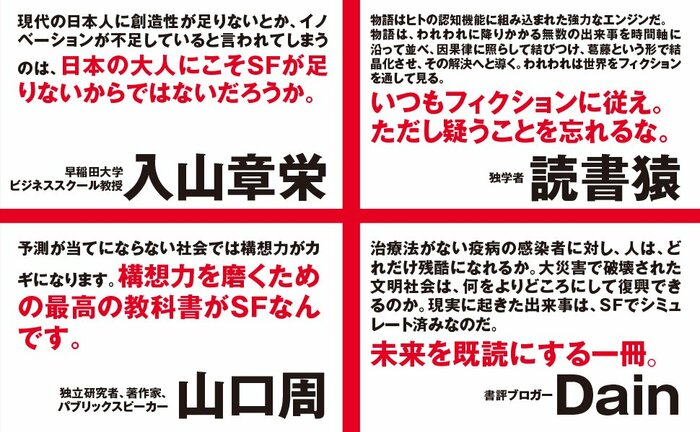『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』著者の冬木糸一さんは、SF、つまり物語を現実が追い越した状況を「現実はSF化した」と表現し、すべての人にSFが必要だと述べている。
なぜ今、私たちはSFを読むべきなのか。そして、どの作品から読んだらいいのか。この連載では、本書を特別に抜粋しながら紹介していく(※一部、ネタバレを含みます)。
『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』の著者の冬木糸一です。エンジニアとして働きながら、ブログ「基本読書」などにSFやらノンフィクションについての記事を、15年くらい書き続けています。
僕はSFを「現代を生きるサバイバル本」と位置付けています。理由は、イーロン・マスクを代表とする起業家たちのインスピレーションの源が、SFだからです。彼らは文字通り、今ビジネス、そして世界を動かしています。頭のいい人ほど、フィクションから発想を得ていると考えることもできます。
今回は本書のなかから「はじめて読むS F」としておすすめの一冊を紹介します。
どんな作品か:太陽の出力が激減し、存亡の危機に瀕した地球
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』
─「科学」で結びつく人類と地球外生命体
火星にたった一人残された男がサヴァイヴする過程を、とことん科学的に正確に描写した宇宙開発SFの傑作『火星の人』(2011)。同作でデビューしたアンディ・ウィアーの『アルテミス』(2017)に続く長編第三作が、この『プロジェクト・ヘイル・メアリー』である。バラク・オバマ元大統領やビル・ゲイツが2021年のおすすめ本として挙げるなど、各方面で評価の高い本作は、まったく異なる文化と身体構造を持つ地球外生命体と人類が、科学を通してコミュニケーションできる可能性を示してみせた、宇宙生物学&ファーストコンタクトものの傑作だ。
本作は、昏睡状態から目覚めた男が、自分の名前すら思い出せない状況の中で、目の前の問題に対処していく「現在」パートと、その現在に至るまでに何が起こったのかを描く「過去」パートが交互に繰り返される構成になっている。最初は語り手が人間で、生物学的に男性であることしかわからないが、過去が明らかになるたびにそういうことなのか!と驚きが積み重なっていく。
名前さえ思い出せないとはいえ、主人公の中には一般的な記憶が残っており、AIと対話しながら周囲を動き回るうちに、その知識量から本人の正体が少しずつ判明していく。
部屋に置かれた機材─8000倍顕微鏡、高圧蒸気減菌機、レーザー干渉計など─の名前と用途がわかるということは、科学者かそれに類する職種の人間だということだ。さらに、持ち前の観察力と実験力を駆使してさまざまな検証を繰り返したのち、主人公は自分が存在している空間が地球ではないということを突き止める。
しかし、それが宇宙ステーションのような場所なのか、はたまた航行中の宇宙船内なのかまではわからず、「現在」パートではそうした細部が徐々に解き明かされていく。
では、なぜ主人公はこのような状況に置かれているのか? その謎にせまる「過去」パートでは、太陽の出力が急速に落ちていて、地球がこのままでは氷河期に突入してしまう危機的状況が描かれる。なんの手も打たなければ、約20年で人類の半分が飢餓で死亡するというのだ。この異変を引き起こした原因として浮上するのが、太陽と金星をつなぐように存在する〈ペドロヴァ・ライン〉と呼ばれる特殊な現象だ。太陽の出力が落ちるのと同じ割合で、このペドロヴァ・ラインの光の出力が増しているのである。
人類が無人の探査船を送り込み、ペトロヴァ・ラインの構成物質を採取、調査したところ、その正体は単細胞の生命体であることが判明する。後に〈アストロファージ〉と命名されるその生命体は、太陽の表面もしくはその近くに陣取り、太陽からの出力を養分として繁殖しているらしい。その変換効率が凄まじいからこそ、太陽はまるで食い殺されるようにその出力を落としているのだ。地球の研究者は総力を挙げて、アストロファージの生態を研究し、対処法を突き止めようと奔走する。
地球の命運をかけたこの一大プロジェクトに、中心人物として関わっていたのが本作の主人公だ。物語の序盤では中学校の教師として登場するが、彼はもともと研究者で、『水基盤説の分析と進化モデル期待論の再検討』という、水を生命の基盤としない生命についての仮説を追究していた。そんな仮説はありえないと猛反発をくらって一度は研究の世界を去っている。ところが「太陽近郊で活動できる生命体がいるとすれば、超高温に耐えられるのだから、水を基盤としない生命なのではないか」という推論が出てきたことにより、ふたたび研究の世界に戻ることになったのだ。
緊急的に招集された主人公が、アストロファージに対してX線分光計にかけたり、数千度まで加熱してみたり、冷やしてみたり─こうした手順を一個一個踏みながら、これがどのような生物なのかを確かめていく。地球外生命体の性質を、科学的な過程をたどりつつしっかりと描き出している点が、本作を宇宙生物学SFとして特別なものとしている。
どこがスゴいのか:ひとつの危機に対して、異星人と「共闘」する
物語が進む中で、「現在」の主人公は〈恒星タウ・セチ〉を目指していることがわかる。実は、太陽系以外の恒星系でもアストロファージの侵食が起きているのだが、なぜかタウ・セチだけはその被害を免れている。その秘密にこそ、地球を救う手がかりがあるかもしれないからだ。
その道中で、主人公はアストロファージとはまた別の地球外生命、それもちゃんと独自の言語を持ち、コミュニケーションができる存在との遭遇を果たす。最初は、その相手こそがアストロファージをばら撒いたか、収穫にきた存在なのではないか─と様々な仮説を検討するが、次第に相手もアストロファージによって恒星の出力を落とされ、存亡の危機に陥った異星の種族であることが明らかになる。そして両種族は共闘し、この未曽有の事態に対応していくことになる。
なぜこのタイミングで、人類が異星種族と出くわすことができるのか? まったく別の場所(主人公が出会った種族は〈エリダニ40星系〉の生まれ。実在しており、太陽から16光年ほどの場所にある)で進化したはずの両者が、ほぼ同程度の科学水準(宇宙船を飛ばせるほどには技術があるが、ただちにアストロファージを駆逐できるほどには技術がない)にあるのはなぜか? つまり、物語的に都合がよすぎないか? という疑問が湧いてくるわけだが、本作のファーストコンタクトものとしての面白さは、そうした無数の疑問点に科学的に「答え」を用意している点にある。
本作をファーストコンタクトものとして傑作たらしめているもうひとつのポイントは、体のつくりも、生活環境も何もかもが異なる2つの種族が、科学を用いることで、流暢にコミュニケーションできることを描き出している点にある。
エリディアン(エリダニ星系生まれなので、主人公がそう命名)は目や顔のない、ラブラドール犬ぐらいの大きさの蜘蛛のような生物であると描写される。さらに、彼らは物を知覚するのに光ではなく音を使う。コウモリやイルカが音の反響で空間を把握するように、エリディアンも音波によって周囲の環境を分析する。言葉も当然、最初は一切通じない。
それでも、両者の「科学」は共通している。エリディアンは最初、主人公にボールを渡してくるが、その中には短い糸でつながった8つの数珠玉が入っており、それが原子と陽子の表現であることに主人公は気づく。数珠玉は陽子で、数珠の輪っかは原子、短いつなぎ糸は化学結合を表していた。陽子8つは酸素で、それが2セット入っているので、O2。つまり相手は、人類の生存に必要な酸素分子を、模型で表現してみせたのだ。
同じやり方で、エリディアンらの生存に必要なものはアンモニアであることが表現される。このようにして、ほとんど共通点を持たない、言葉も通じないはずの二種族は、科学を共通言語として、お互いのコミュニケーションを進展させていく。人と地球外生命体が争うSFは多いが、本作のように協調の可能性を示してみせるのもまた、SFならではの着眼点といえよう。
ちなみに、SFに初めてチャレンジしたいという人から、「最初に読むならどれ?」と聞かれたら、筆者は本作をおすすめする。SFの王道といえる地球外生命体とファーストコンタクトの物語であり、文章は本書で取り上げたすべての作品の中でも群を抜いて読みやすい。何より、科学の本質的な魅力に気づかせてくれる作品だからだ。
アンディ・ウィアー
1972年、米カリフォルニア州生まれ。コンピュータ・サイエンティストとして働く傍ら、Kindleで出版した『火星の人』で一躍ブレイクした。
※この記事は『「これから何が起こるのか」を知るための教養 SF超入門』からの抜粋です。