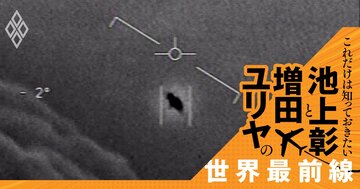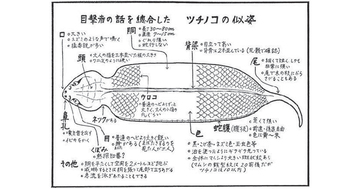世界中で目撃される
ドッペルゲンガー
ドッペルゲンガー(Doppelganger)はドイツ語。doppelはdouble’ gangerはwalkerで、直訳すると「動きまわる、もう一人の自分」。何やらぞくぞく感が迫る。最初の使用例とされるのは、ドイツ人作家ジャン・パウルが18世紀末に発表した長編小説『ジーベンケース』で、平凡な弁護士ジーベンと、彼に生き写しの友人の物語だ。
必ずしも本人が自分のドッペルゲンガーを見るとは限らず、他人から別の場所で自分を見たと言われることもある。この現象は世界中の言い伝えに残されており、一般的に肉体と霊魂が分離したものと考えられている。自分で見た場合は死の予兆との迷信も根強い。
ドッペルゲンガーの日本語訳は「分身」、「生き写し」、「自己像幻視」、時に「生霊」と、微妙に意味が違う。
「分身」はまさに「身が分かれる」ので、もう一人の自分という存在を強く想起させる。「生き写し」だと、単に似ているだけ、双子の可能性も否めない。
「自己像幻視」に至っては、精神的な病との決めつけを感じる。実際、哲学者ヤスパースは、ドッペルゲンガーを意識の病態と捉えた。この世は全ては科学的に説明できると信じる者にとっては、何が起ころうと、「幽霊の正体見たり、枯れ尾花」となる。もっとも、自分がもう一人の自分を見たと証言する人たちの中には「病態」例も確実にあるだろう。面白いのは、二重人格者は女性に多いが、ドッペルゲンガーを主張する患者は男性に多い、という近代の研究結果だ。仮にこれが正しいとするなら、自己認識には男女差があるのかもしれない。
「生霊」は、生者の魂が体外へ抜け出ることを言う。多くは死に瀕した者がそうなると伝えられ、ここからもう一人の自分を見ると死が間近だと考えられるようになったのだろう。
欧米におけるドッペルゲンガーについての記録は、19世紀半ば以降著しく増えている。それはオカルトや降霊術の大流行と重なり、またスティーヴンソンの『ジキル博士とハイド氏』を筆頭に、ドストエフスキー、ロレンス、ポー、ワイルドなどが小説に取り上げることで、ブームはいっそう盛り上がったのかもしれない。
著名人の例をいくつかあげよう。
イギリスの詩人パーシー・ビッシュ・シェリー1792~1822)は、自分のドッペルゲンガーが妻メアリ(『フランケンシュタイン』の原作者)を絞め殺そうとするのを目撃した。それからしばらくして、ドッペルゲンガーはまた現れ、「いつまでこんなことをしているんだ」と怒鳴ったという。パーシーの死はその2週間後。ボートの転覆事故による溺死であった。
フランスの作家ギ・ド・モーパッサン(1850~1893)のドッペルゲンガーは、彼が小説を執筆しているところへ突然入ってきて、続きを口述して消えたという。ただしこの頃のモーパッサンは先天性梅毒が悪化し、痛み止めに多量の麻薬を摂取していたから、幻覚だった可能性が高い。
アメリカの第16代大統領エイブラハム・リンカーン(1809~1865)は最初の大統領選挙戦の時、鏡の中に2人の自分を見たという。
イギリスの戦艦ヴィクトリア号の司令長官サー・ジョージ・トライオン海軍中将(1832~1893)は、シリア沖での艦隊訓練中の衝突事故により、戦艦と乗組員357名とともに海の藻屑となった。ちょうどその頃ロンドンでは彼の妻が邸でパーティを催しており、複数の招待客から、軍服姿の彼を今さっき見かけたと言われたという。もちろんその時には、事故を知る者は誰もいなかった。
先述の例は、ほとんど伝聞である。シェリーがこう言っていた、リンカーンから聞いた、というような。またトライオン提督の場合は単なる幽霊譚とみなしてもいい。
本人が書き残しているものでないと信じられない? ではその例を引こう。
若きゲーテが目撃した
自分のドッペルゲンガー
 『新版 中野京子の西洋奇譚』(中央公論新社)
『新版 中野京子の西洋奇譚』(中央公論新社)中野京子 著
ドイツの作家ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(1749~1832)が自伝『詩と真実』に記しているドッペルゲンガー目撃譚だ。
若きゲーテは恋人のもとへ馬を走らせていた。すると向こうから明るいグレーの服を着たドッペルゲンガーが馬に乗やって来るではないか。驚いたが、やがてそのことは忘れてしまう。8年後、ゲーテはまた同じ道を、今度は逆方向に馬を走らせていたが、その時忽然と思い出したのは、今の自分があの時のあのドッペルゲンガーと同じ明るいグレーの服を着ていたということだった。
数々のドッペルゲンガー譚。しかし実際には、幽霊譚と比べてはるかにその数は少ない。なぜだろう? 自分が自分を見る――その衝撃は幽霊を見るのと比べものにならぬほど大きいからではないか。幽霊などよりずっとずっと怖いからではないか……。