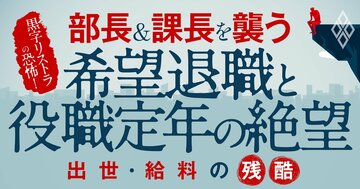浮舟はさすがに泣き伏してしまうものの、最後まで「まるで身に覚えがない」「今日はやはりお持ち帰りになって。宛先違いでしたら、決まりが悪いでしょうし」と、突っぱねます。
薫は「今か今か」と待っていたのに、小君がこうも収穫もなく戻ったことに、興ざめになって、
「なまじ使いなどやるのではなかった」
と、思うところはさまざまで、
「ほかの男が隠して囲っているのだろうか」
と勘ぐります。
それを物語は、
“わが御心の、思ひ寄らぬ隈なく落しおきたまへりしならひにとぞ、本にはべめる”という一文で、締めくくります。
「薫自身のお心に照らし、かつて浮舟を宇治に捨て置いていたご経験から、あらゆる可能性を思い巡らして……と、もとの本にはございますようで」
の意で、さいごの“本にはべめる”は、この『源氏物語』の原本を書写した人が付け加えた一文ですが、物語の語り手が話を締めくくる一手法という説もあります。
はかなく無常なラストは
未完か?完結か?
いかがでしょうか。
この終わり方が尻切れトンボだというので、中世以降、続篇を綴る者も現れましたが、このラストを超えるものはありません。
『源氏物語』を全訳した時、「ひかりナビ」と称する解説でも書いたのですが、人生なんて、皆、尻切れトンボで幕を閉じるものです。『源氏物語』のラストはそんな人生にも似て、はかなく、無常です。自分の意志とは関係なくこの世に投げ出され、不意に退場させられる生き物の悲哀が、にじみ出て、永遠の余韻とも言うべきものを感じさせてくれます。
私は『源氏物語』は完結していると考えています。
それは、浮舟の出家姿を描いた箇所が、フィナーレ感に満ちているからでもあります。
浮舟の存在が薫に知られる前のこと。
僧都の妹尼の亡き娘の婿だった中将と呼ばれる男が、浮舟に接近したがっていたんですが、彼女の出家を知ると、
「せめて尼になった姿なりとも、少しでも見させてほしい」