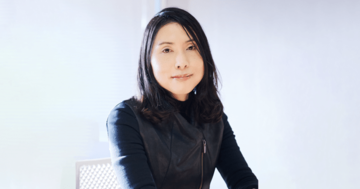古代ローマ皇帝の悩みも現代に通ず
「人類の知の結節点」としての古典
――まさに、堀内さんの「人生を変えた読書」ですね。そうした壮絶な体験の記述がある前の章、第1章では、「読書とは何か」「読書の良さ」について書かれています。
読書の良さについては、 いろいろなポイントを本書に書きました。例えば、本に詰まっている内容量というのは圧倒的です。中身が圧縮されていて、書き手の経験の追体験や知識習得において他のメディアよりもはるかに優れている。
また、本には著者の人間性が表出されていて、その著者と「対話」ができる。例えば、マイクロソフトの創業者のビル・ゲイツというのはすごい人だな、どんなことを考えているのかなと思っても、実際に会って話をすることはまずできません。けれど、ゲイツが書いた本を読めば、彼の考えがわかる。当人も本を書く際には真剣に読者に向き合っている。もし仮にリアルに会えたとしても、例えば講演を聞いて、その場で彼をつかまえて直接会話ができたとしても、話だけだとその場限りの会話になってしまいがちです。でも、本を書くとなれば、誰でもきちんと書く。まとまった考えを、丁寧に説明してくれるのです。
さらには、今この世にいない、亡くなっている人とも対話できるし、翻訳を通して言語が違う人とも話せます。
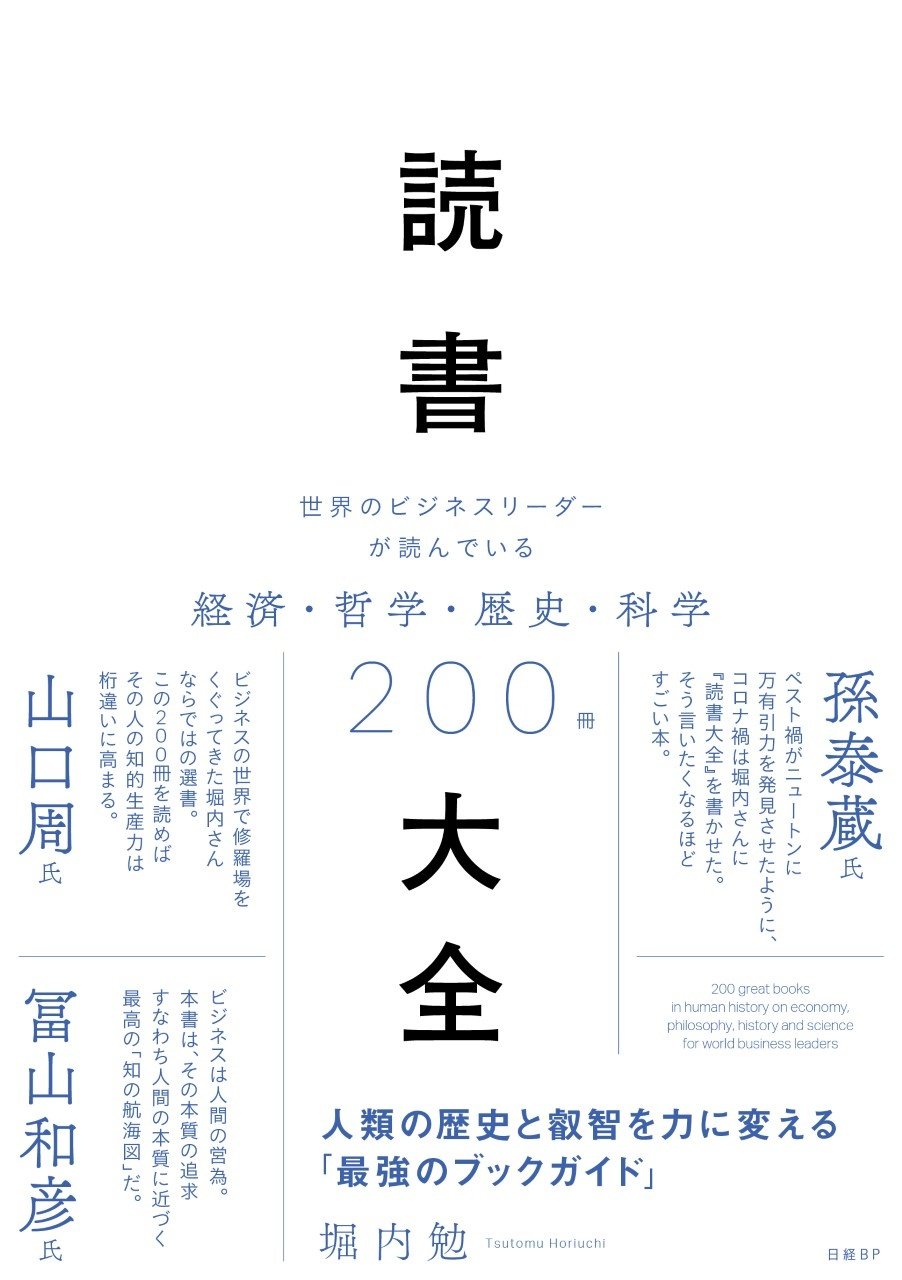
――古代ローマの「哲人皇帝」、マルクス・アウレリウスの『自省論』についても本書では熱く書かれています。
マルクス・アウレリウスは西暦160年に、古代ローマ帝国の16代皇帝に就きます。『自省録』は彼の日記なのですが、 そのような1800年以上前のローマ皇帝が何を考えて生きていたかというのは、この本がなかったら絶対にわからない。
文字自体は6000年ほどの歴史があるといわれていますが、 今日まできちんと読み継がれている本はなかなかありません。『自省録』が歳月の風雪に耐えて、生き残っていることには、それなりの意味があるのです。1800年の間にこの本を読んだ人の数はものすごく多いだろうと思います。それは、中身が濃くて、他の人に読み継がれていってほしいと思われたからです。どういう形で感化を受けるかは別として、時を超えて世界中の人たちがその本に何か感化を受けてきた。これはすごいことです。古典と呼ばれるものは皆そうですね。
東京工業大学名誉教授の橋爪大三郎さんの『正しい本の読み方』(講談社現代新書)の言葉を、本の中で引用しましたが、古典というのは「人類の知の結節点」になっている。人間の頭で言えば神経細胞の結節点みたいなものです。それがクモの巣のように、歴史的にも地理的にも人類の間に張り巡らされていて、その中心にあるのが古典です。
だから、そこを介していろいろなものが相互に影響し合っている、人間の思考の中心点です。そういうものを読んでいくと、人類がどういう知の歴史をたどってきたのかがわかります。
古典は、無数に発行される本の中で、長い年月を超えて生き残った作品です。古典が絶対に良いというつもりはありませんが、 古典を読むことが良書に当たる可能性を高めてくれます。
――本書の一節にある「『考える』ための灯火としての読書」という論も説得力があります。
マルクス・アウレリウスの『自省録』を読む時、1800年以上昔の皇帝も、こんなことに悩んでいたのだと思うと、親近感が湧いてきます。共感を覚える。案外、人間は変わってないんだなと思います。
古代の皇帝も現代の自分も、似たようなことに悩み、考え、同じような道筋をたどって解決策を探している。例えば山の頂上に至る登山道は何十通りかあると思いますが、多くの人は先人が歩んだ道をトレースして頂上に向かっていくのと同じで、読んでいると人間の思考にはそのようなパターンがあることに気づきます。古典は、先生のようなものですよ。とはいえ、単に踏襲するだけだったら、他の人が考えてきたことをうのみにするという話になってしまうので、自分なりの考えは持つように意識しなければなりません。
まず人類が作ってきた「考える道筋」を、 それこそ人間の「思考の枠組み」を認識して、それに自分の経験を積み重ね、自分を作っていくということですね。
――同じ本でも、自分が置かれている環境で読み取れるものが変わってくるということもありますね。
自分の心持ちの問題です。本において、与える側と受け入れる側のうまいマッチングがないと、いい出会いにはなりません。恋愛と同じだと思います。私はあなたが好きですといくら言ってみたところで、あなたが私のことをどう思っているかを無視して、ただ好きだと言っても意味がない。相手に受け入れてくれる土壌があると、こちらが好きだと言った時に恋愛が成立する。人間関係は皆そうだと思います。そして、本との出会いも、読み手に、本に合った土壌が備わっているかが大切です。タイミングの良しあしはありますね。
ただし、人との出会いを再現したりやり直したりするのはなかなか難しいけれど、本棚にある本はいつでも再読できます。
若い頃は本を読み返すことはあまりなかったのですが、一定の年齢を過ぎたら、変わりました。苦しい時とかつらい時とかに、もう一度読んでみようと思うようになりました。自分のことを考え、書かれた言葉を反芻(はんすう)しながら、本の著者と対話する。自分の心を整えるというか、心のざわつきを抑えるというか、そういうことが多くなりました。
自分を相対化できるということもあるかもしれない。自分の苦しみとか悩みとかは、世界で自分一人だけのものと、子供の頃は思っていましたが、ある程度、年を取ってくると、自分だけがそんなにつらい目に遭っているわけではないことがわかるし、『夜と霧』で書かれているように、つらい状況というのも自分の人生の一部だというふうに思えるようになってくる。
――『夜と霧』についても再読で、最初に大学生の時に読んだ時は全然違う感想を持っていたと、本書では書かれています。
大学時代に『夜と霧』を読んだ時は、強制収容所の写真を見るのがつらくて、自分はこんな時代に生きてなくてよかったぐらいにしか思っていなかったのですが、それが37歳の苦悩していた時に再読したら、自分のこととして感じられるようになりました。もちろん、過酷の度合いは全然違うのですが。
理解力の問題なのかなと思います。人生の経験を重ねることで、心の中に入ってくるという感じですね。共感力というのは、もちろん子供でも持っているけれど、経験を重ねてくると、自分と著者の感情がシンクロしていくことが多くなります。著者はこういう局面でこういう風に考えたのかみたいなことが、深く理解できるようになっていく。