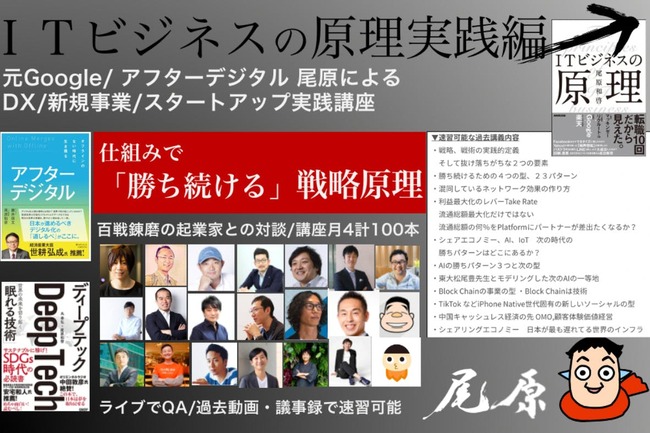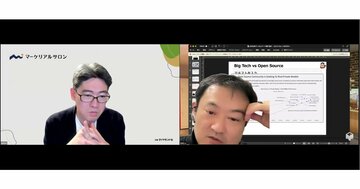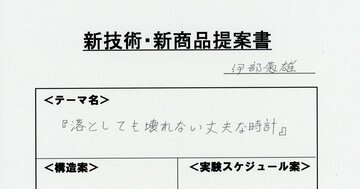マーケティングにまつわる2024年の展望について、IT批評家の尾原和啓さんとインサイトフォース取締役の山口義宏さんが語り合います。生成AIの進展で注視しておきたい点や、ポストデザイン思考の動きとして捉えておくべき点など、押さえておきたい問題を一気にチェックしましょう。
*本対談は、尾原さんのオンライン講座「ITビジネスの原理実践編」×山口さんをファシリテーターとしてマーケティングの本質を学ぶコミュニティ「マーケリアルサロン」共催で2023年12月に開催したイベント内容のダイジェスト記事です。
GPTの凄みはどこにあるのか
 尾原和啓(おばら・かずひろ)さん
尾原和啓(おばら・かずひろ)さんIT批評家
1970年生まれ。京都大学大学院工学研究科応用システム専攻人工知能論講座修了。マッキンゼー・アンド・カンパニーにてキャリアをスタートし、NTTドコモのiモード事業立ち上げ支援、リクルート、ケイ・ラボラトリー(現:KLab、取締役)、コーポレートディレクション、サイバード、電子金券開発、リクルート(2回目)、オプト、Google、楽天(執行役員)の事業企画、投資、新規事業に従事。内閣府新AI戦略検討、経産省 対外通商政策委員等を歴任。NHK「令和ネット論」にて「DX」「メタバース・NFT」[Web3」を解説。現職は13職目 シンガポール・バリ島をベースに人・事業を紡ぐカタリスト。ボランティアで「TEDカンファレンス」の日本オーディション、「Burning Japan」に従事するなど、西海岸文化事情にも詳しい。新刊『プロセスエコノミー』は「ビジネス書グランプリ2021」にてイノベーション部門受賞 共著書『アフターデジタル』(日経BP)は経済産業大臣 世耕氏より推挙、10万部超え、製作協力の國光著「メタバースとWeb3」は半年で7刷と好調。『モチベーション革命』(幻冬舎Newspicks books)は 2018年Amazon Kindleで最もダウンロードされた本に。中国・韓国・台湾で翻訳。『ITビジネスの原理』(NHK出版)は2014年、2015年連続Top10のロングセラー(2014年7位、2015年8位)。韓国、中国に翻訳。
山口義宏さん(以下、山口) 尾原和啓さんをお迎えして2023年のマーケティングトピックを振り返ってきましたが(関連記事はこちら)、ここからは2024年にマーケティング界隈で何が起こるのか、展望を語り合っていきます。尾原さんから一つ目に挙げていただいたポイントは、「生成AIはすべてのUXに埋め込まれる」ですね。
尾原和啓さん(以下、尾原) 生成AIは、あらゆるUXに埋め込まれて、ユーザーがいちいちインプットする必要がなくなる前提で考えなければならなくなります。
山口 自分の周りでは、ソフトウェアだけでなくハードウェアとAIを組み合わせた商品企画がすごく増えている実感があり、ロボットブームとは違いますが、2024年以降はハードウェアにAIを溶け込ませた商品サービスが劇的に増えそうです。
尾原 たしかに。それと、GPTのトランスフォーマーモデルというのは、「なんでも質問に答えてくれる」と捉えがちですが、実は「複数の絡み合った文脈の中から、要望に近い文脈の重要な点を拾い上げて答えをつくる」というアテンションをとる強さに凄みがあります。結果としてアンストラクチャード(非構造化)データが得意で、前の文脈を要件化してくれて、正解と思われる解を出すことよりインサイトを出すことに強かったりする。
たとえばマイクロソフトのTeamsでビデオ会議をすると、決定事項がアウトルックのスケジューラーにTODOとして「〇〇というクライアントに△△の方向性で提案する」と自動入力される。それをクリックすると、過去の提案資料とその方向性に基づいた要約と資料がまとめて見られるうえ、さらに「こういう新しいニュースも踏まえて提案資料のひな型を作って」と指示すれば作ってくれる。そういうことが可能になるわけです。
山口 それはすごいな。
IDEO日本事務所の閉鎖が意味するのは?
 山口義宏(やまぐち・よしひろ)さん
山口義宏(やまぐち・よしひろ)さんインサイトフォース取締役
ブランド・マーケティング領域の支援に特化した戦略コンサルティングファーム、インサイトフォース株式会社の取締役。ソニーグループ企業にて戦略コンサルティング事業の事業部長、リンクアンドモチベーションにてブランド・コンサルティングのデリバリー統括、PR~デジタル系広告代理店にて新規事業開発マネジャーを経て、2010年にインサイトフォース株式会社を設立。これまで100社を超える上場企業クライアントに対し、ブランド~マーケティング戦略策定、CI、商品・デザイン・広告施策の実行、グローバル市場戦略などの支援を提供している。著書『マーケティングの仕事と年収のリアル』(ダイヤモンド社)、『デジタル時代の基礎知識「ブランディング」 「顧客体験」で差がつく時代の新しいルール』(翔泳社)他、最新刊は『マーケティング思考』(翔泳社)。
山口 2024年展望の2つ目のポイントは「デザイン思考の終焉」ということですが。
尾原 23年にデザインコンサルティング会社IDEOの日本オフィスが閉鎖されました。それは何を意味しているのか。デザイン思考がダメになったわけではないと思うんです。ただ、誰もがデザイン思考を装着できるようになって、競争力にならなくなったと考えるべきでは? みんなが急激におしゃれになり、それも簡単にマネできるので、「おしゃれじゃないものがなくなる時代」になった、ということだと思います。言い方を変えれば、外から観察するアウトサイド・インのアプローチより、人の内側に立ち上がるものを外に出していくインサイド・アウトのデザインアプローチをとる流れが強くなるのでは?
山口 ロベルト・ベルガンディ氏が提唱する「意味のイノベーション」の流れに近いでしょうか。
尾原 そうですね。アウトサイド・インの発想は真似できるがゆえにコモディティ化して、すべてがおしゃれになって競争力をもたなくなる。一方で、一昨年から大流行している「鬼滅の刃」「呪術廻戦」「チェンソーマン」みたいに、一人の作家にしか見えない妄想妄念のようなインサイド・アウトの世界観は真似できないし希少化する。
そして、これまで妄想だけ持っていて形にできなかった人たちも、生成AIを使うことで具現化できるようになって、それをTikTokやInstagramにアップすれば、アルゴリズムがその妄想を好きだという人を選んで広げてくれるから、妄想を育てやすくなる、ともいえます。
フィリップ・コトラー氏が著書『マーケティング6.0』で「未来はイマーシブ(immersive:没入)だ」と言っていますが、キリスト教的な語源イマージョンは「洗礼」。まさに、そういうアプローチが、これからもっとやりやすくなる。このインサイド・アウトの力を持った人を、コマーシャリズムとどう相性のよい形にしていくかがメソッド化されてきています。それができる「偏愛ブリーダー」や「偏愛参謀」ともいえる人が国家のブランド産業力になるか、それをプラットフォーム化していく、ということが2024年に起こるのではないでしょうか。
山口 内側に秘めたパッションが、生成AIの力を借りてクリエイティブを生産したり、それをマネタイズできる機会が増えるということですよね。生成AIは生産力じゃなくて生産のスキルの民主化、といえそうです。
尾原 たとえば過去10年間、Instagramが普及したことで、一般の人たちの写真を撮るセンスが劇的に向上しました。次は、生成AIを通じて妄想のセンスが磨かれた人たちが成長してくるはずです。僕ら世代は、彼らにバトンタッチするために、いかに準備できるか、が今問われていると思います。
2025年問題に向けて、互助・共助を取り戻せるか
山口 さて、2024年の展望として、3つ目のポイントは「2025年問題にむけた歩み寄りな最適化」ですね。
尾原 物流破綻や社会保障費といった僕らの生活を支える公共インフラが、いよいよ2025年にはもたなくなってきます。団塊世代が後期高齢者に突入して、消費にも貢献できなくなる。そうした2025年問題への手当を始める必要があります。
日本では「自助」「互助」「共助」「公助」のうち、あきらかに公助に頼りすぎていて、都市化の反動で互助と共助がなくなってきています。もともと日本には「おたがいさま」という価値観があるので、互助と共助の精神はあるはずで、これらをどうプラットフォーム化していくかが課題です。
たとえば物流でいえば、共助スペースで受け取ることは無料だけど、個人宅まで配達してほしければお金を払う、という仕組みにする。物流以外にも、互助と共助でできることはたくさんあるはずです。たとえば伊バルセロナなどの(自動車空間を減らして住民が考える生活空間を創出する)「スーパーブロック」構想や、仏パリの(自宅から公共交通機関や徒歩で行ける範囲にすべてのアメニティが揃うことを目指した)「15-minute city」構想など、互助と共助が発生しやすくなる社会デザインがさまざまな都市で始まっていて、そういう取り組みを真剣に始める必要があります。
山口 日本にこれ以上の課題はないですね。
尾原 一方で、僕らみたいなデジタルノマドは社会インフラのフリーライダーだから、カーボンオフセットを個人でする流れが出始めました。自分が乗ったフライトと生活した国が出している化石燃料分をオフセットしています。ただし、住んでいる国に対してではなく、一番有効活用してくれそうなエコプレナー(エコ起業家)に渡す。カーボンオフセットのふるさと納税みたいなものです。
山口 そういう「ふるさと納税」もいいですね。
AIから公共サービスまで幅広い話題をありがとうございました。個人的には、AIによってマーケティングの業務やオペレーションが進化する部分への対応と同時に、それとは相反するようですがブランド固有の偏愛要素の見直しを両立することがポイントかと思いました。2024年のマーケティング界隈で何が起こるか、ますます楽しみです。