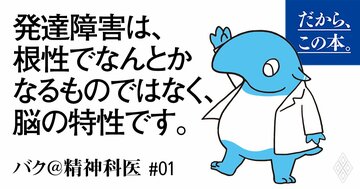これは私の体験談だが、総務部兼経理部で働いていた頃、ある日、社長に来客があったものの、あいにく社長は電話中で、しばらくお客様に待ってもらうこととなった。しかし15分以上経っても電話が終わらない。次第にお客様はそわそわし始め「今日のところは帰ります」と帰ってしまった。
後になって、上司から「あの会社の人が来られた場合、社長にメモを渡して電話を終わらせて商談に持っていかないといけません」と指導を受けたのであった。私には来客した会社の人と電話相手の会社の人のどちらを優先すればいいのか分かっていなかったのだ。
こうした取引先の優先順位は社内に暗黙知としてしばしば存在するが、具体的に仕事のマニュアルには書かれていない(しかしこれは裏を返すと、ASD傾向の強い人には細かいマニュアルを与えれば仕事をしやすくなるとも言える)。
立派な一流大学を出ているのに
どうしてアイツは使えないのか
発達障害者の多くは、ADHDの特性により落ち着きの無さや、ASD特有の視線の合わせ方が不自然な点が目立ったとしても、一見した限りでは発達障害かどうかわからない。筆者が取材した高学歴発達障害者の中には、ハキハキと話し頭の回転が早く、「一を聞いて十を知る」とでも言うような、こちらが聞いたこと以上の情報を話してくださる方もいた。
こんな人が、しかも高学歴ときたら、仕事でさぞかし優秀な成績を上げるに違いない。普通ならそう思うであろう。しかし現実は、ケアレスミスが多い、やたらと遅刻をする、メモが取れない、指示されたことをしていなかったり、優先順位の低い仕事をしている、仕事中デスクに座っていられない、といった散々な状態になる場合がある。
そうなると、障害者には見えない見た目、高い学歴、そして仕事のできなさに上司を始めとした周囲の健常者は戸惑いを抱えてしまう。中には怒鳴り散らされるようなパワハラを受ける当事者もいる。