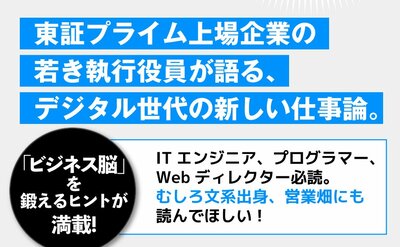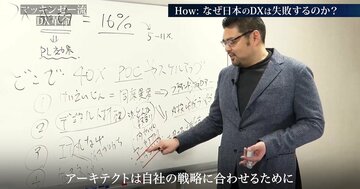30代で東証プライム上場企業の執行役員CDO(チーフ・デジタル・オフィサー)となった石戸亮氏が、初の著書『CDO思考 日本企業に革命を起こす行動と習慣』(ダイヤモンド社)で、デジタル人材の理想的なキャリアについて述べています。
デジタル人材は、ビジネスの現場でどのように求められているのか。
本当に需要のあるデジタル人材として成長するためには、どんなスキルを身につければいいのか。
デジタル人材を喉から手が出るほど欲している企業に迎え入れられ、そこで重用されるには、どんな行動を取ればいいのか。
本連載では、デジタル人材として成長するためのTo Doを紹介していきます。
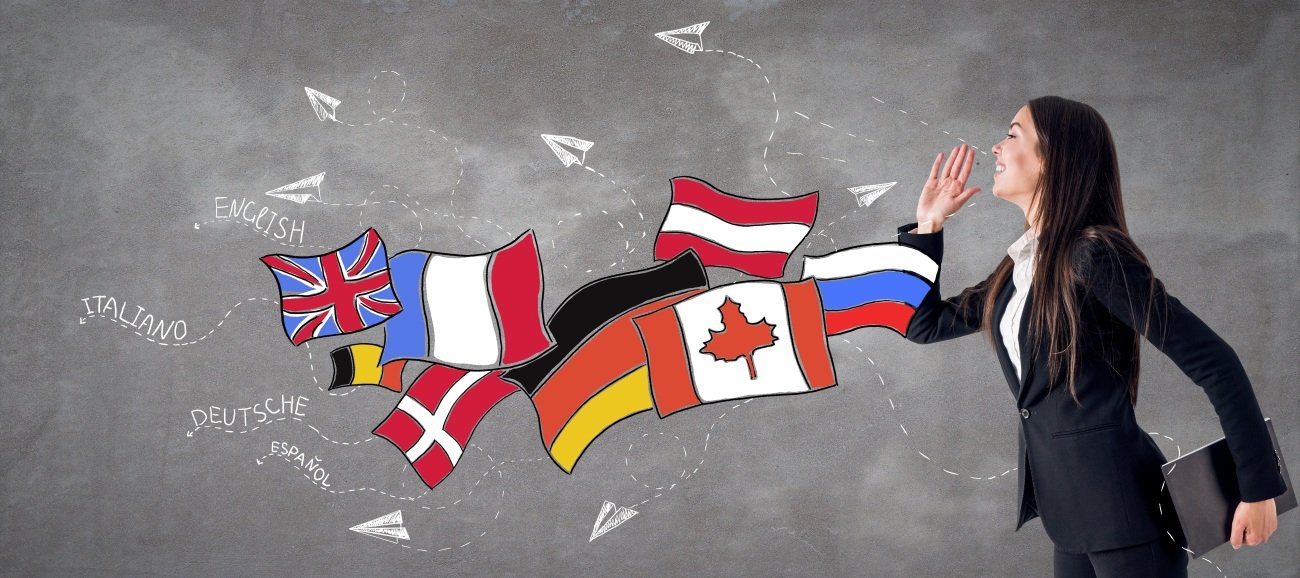 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
ビジネスの「通訳」のような存在
一般的な製造業を例に考えてみましょう。製造業は大抵、製造部門や営業部門の人員規模が大きく、大体はそれとは別にシステム部門があります。そして各部門からの要望をシステム部門が社内的な受託、あるいは下請けのように開発している会社が多いのが実情です。
すると、何が起きるか。
システムの構成も工数もあまりわからない事業部門が、「XXのシステムに、この機能のボタンを増やしてほしい」「このカラム(項目)、こういうふうに変えて」「この業務が困っているからこのシステム開発をしてほしい」などと言う。それでシステム部門は事業部門のために開発をする。でも「下請け」的な関係性が長く続いているからか、事業部門の意向にそって開発や改修をするので、ちょっとした変更やたいして業務効率に変化がない機能の追加に、依頼した部門が想像する以上の無駄なコストがかかってしまう。さらには生産性が上がるわけではなく、改修を重ねたシステムで生産性すら落としてしまっている。そのせいで、部署間が険悪になる。よく見る光景ですよね。
この下請けに流れるような作業的業種や結果的な生産性低下を防ぐためには、事業部門とシステム部門の「間に立つ人」が必要です。「事業・経営」と「IT」の両方の言葉を使い、事業部門からのリクエストを冷静に精査し、それは喫緊に必要なのか、中期的な解決で問題がないのかを判断・整理し、工数とともにシステムの要件に落とせるような人。優秀なコンサルタントのように交通整理が得意で、各部署に忖度なく配慮しながら判断し、それを双方の理解をしつつ、双方の言葉を使って、目的達成のために進めることができる人。
事業とIT、経営と現場、顧客・市場と会社、双方の言葉を使って、当たり前のようにデジタルな要素を頭に入れながら、目的達成のために物事を進める。いわばビジネスの「通訳」のような人材です。アナログ世代とデジタル世代、双方が理解しやすいように言語を「翻訳」できる人と言っていいかもしれません。
これが私の考える「デジタル人材」です。
※本稿は『CDO思考 日本企業に革命を起こす行動と習慣』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。