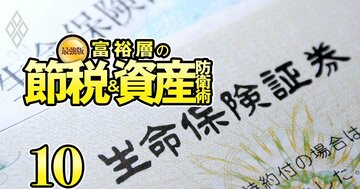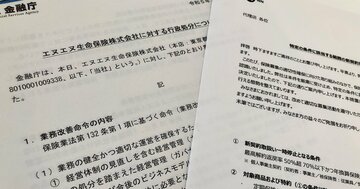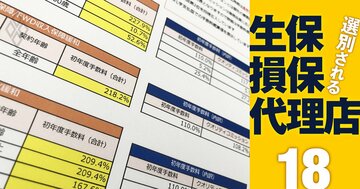Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
保険会社から支払われる代理店手数料の支払い方法を巡り、保険業法に抵触しかねないスキームが横行している。それが、別法人への手数料の支払いである。特集『生保・損保・代理店の正念場』(全31回)の#17では、乗り合い代理店業界でにわかに問題となっているこの問題について詳述する。(ダイヤモンド編集部編集委員 藤田章夫)
一部の乗り合い代理店で横行する
「別法人への手数料払い」
「御社(大型代理店)の傘下に入った場合、法人格を残した元の代理店に手数料の一部を支払ってもらえますか?」多くの代理店経営者は「最近、こう聞かれることが増えましたね」と、ため息をつく。
売り上げ規模が大きい代理店であればあるほど、保険会社が認定した代理店ランクが上がり、同じ保険を販売してももらえる手数料が増える。また、事業費を減らしたい保険会社にとって代理店の大型化は、少ない営業人員で効率的に営業活動ができるため、人件費の削減につながる。
こうした理由から、全国展開する広域代理店に地場の小規模代理店が吸収合併される事例が増えている。この場合、地場の小規模代理店は広域代理店の支店として、看板を書き換えるだけでそのまま営業を続けることが多い。
ところが、冒頭の会話のように、元の小規模代理店に手数料の一部を支払うケースが増えている。実は、これは保険業法に抵触する可能性を孕んでいるのだ。というのも、保険業法275条3項では、保険募集(販売)の「再委託」を禁じているからだ。
つまり、代理店は保険会社から直接委託を受けて保険募集を行うが、委託を受けた代理店がさらに別の代理店に販売を委託して保険を販売することは、法律上禁じられている。
なぜなら、委託する保険会社側は、委託される代理店側に対して教育・指導・管理の責任を負うが、再委託となれば適切な指導や管理ができなくなるため、保険契約者に迷惑を掛けてしまう可能性があるからだ。
こうした問題が取り沙汰されたのは、今から10年ほど前のことで、2016年5月末に施行された改正保険業法で再委託の適正化がなされ、代理店に所属する募集人は雇用・派遣・出向という3形態に集約されることになった。
ところが、改正保険業法を逆手に取るようなスキームが、一部の乗り合い代理店で横行しているのだ。それが、冒頭の「別法人への手数料払い」だ。次ページでは、そのスキームの中身に加え、法令違反となり得る点について詳述する。