船に使われた最古の例は
『義経記』の「月丸」
“マル”は、人名以外にも刀剣、楽器の名前に使われた例も見られます。
この太刀を抜丸(ぬきまる)と申ゆへは、
(現代語訳:この太刀を抜丸と呼ぶ理由は、)
(『平治物語』中・待賢門の軍(いくさ)の事)
上臈の宝ともおぼしめす、てひきまるといふ琴の上に倒れかゝりて、琴をば微塵にそこなひぬ
(現代語訳:高貴な婦人が宝ともお思いになっている、てひきまるという琴の上に倒れかかって、琴を粉々に壊してしまった)
(『御伽草子』物くさ太郎〈室町時代末〉)
さきに見たように“マル”の古い形“マロ”が動物の名前に用いられた例がありました。もともと“マロ”が人名以外にも用いられていた例があることから、“マル”も人名以外に用いられるようになったものと思われます。
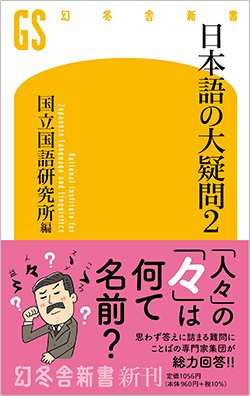 『日本語の大疑問2』(国立国語研究所編、幻冬舎新書)
『日本語の大疑問2』(国立国語研究所編、幻冬舎新書)市村太郎 著
ところで、問題の船の名前に用いた例ですが、もっとも早い例は、室町時代中期以前の成立とされる『義経記』にある、
西国に聞えたる月丸(つきまる)といふ大船に、五百人の勢を取乗せて、財宝を積み、二五疋の馬共立て、四国路を志す
(現代語訳:西国に広く名前が知られている月丸という大きな船に、500人の兵を乗せ、財宝を積み、25匹の馬を立たせ、四国を目指す)
(四・義経都落の事)
という例です。室町時代には、船の名前に“マル”を使うようになっていたと考えられます。
“マル”のおおよその歴史的な変化は、以上のとおりですが、人名に用いられていた“マル”が、なぜ、どのように武具や船などの名前に用いられるようになったのかは、現在のところ明らかになってはいません。語の歴史については、文献によって歴史を追うことはできても、変化の理由を明らかにすることが難しいばあいも多くあるのです。
【関連論文】
*新村出(1971)「船舶史考」『新村出全集』第10巻、筑摩書房。原典画像が国立国会図書館デジタルコレクションで公開されています。新村出(1943)『船舶史考』教育図書(https://dl.ndl.go.jp/pid/1229819/1/1)
*新村出(1971)「船舶史考」『新村出全集』第10巻、筑摩書房。原典画像が国立国会図書館デジタルコレクションで公開されています。新村出(1943)『船舶史考』教育図書(https://dl.ndl.go.jp/pid/1229819/1/1)







