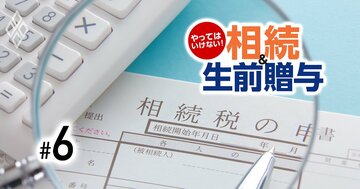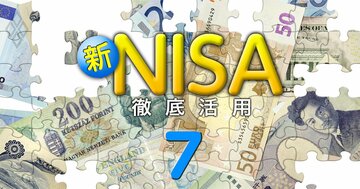写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
今年3月、一時的ではあるが日経平均株価が4万1000円台に乗せたことで、市場が大いに賑わった。しかし、記録的な円安が続いており、相変わらず日本経済の先行きは不透明だ。さらに4月末、自民党が医療・介護保険料を算出する根拠として、新たに「金融所得」を反映するという議論が報道された。新NISAが始まって間もないが、投資への努力が生活の足かせとなる可能性が出てきている。魅力的な新NISAには、知っておきたい「相続時のリアルな注意点」もある。今回は新NISAについて、口座相続時のリアルな注意点を解説する。(税理士・岡野相続税理士法人 代表社員 岡野雄志)
今さら聞けない?
新NISAの変更点とは
今年大きな変更があった新NISA(小額投資非課税制度)は、正式名称にあるとおり、非課税枠がある投資のため、個人投資家の拡大につながっている。ジュニアNISAは23年末に終わってしまったものの、将来に不安を抱えるZ世代も積極的に給料の一部を投資に活かしているとされる。しかし、「関心はあるが一歩踏み出せない」という方もいるだろう。そこで、まずは今さら聞きにくい新NISAの仕組みを紹介する。
新NISAの変更点は主に4つだ。
まず1つ目は、「金融商品から得た利益が非課税になる」点である。利益に課税がなされない以上、コツコツと長期間の投資を続けていきたい個人投資家にピッタリの運用である。新NISAは成長投資枠なら年間240万円まで、つみたて投資枠なら年間120万円まで非課税である。なお、非課税保有限度額の総額は1800万円まで(成長投資枠なら1200万円まで)が非課税となる。その他の投資や保険と組み合わせて、賢く運用していきたい。
2つ目は「非課税保有限度額が旧NISAより大幅アップ」した点だ。旧NISAにおいて、つみたてNISAは年間40万円×20年間=800万円、一般NISAでは年間120万円×5年間=600万円が非課税の保有限度額とされてきた。しかし、変更点の1つ目に触れたとおり新NISAでは1800万円となり、大幅アップだ。
3つ目の変更点は、「つみたて投資枠と成長投資枠が併用できる」点である。これまでのNISAはどちらか1つしか選べず、不満も大きかった。今後は併用できるため、自分にあった運用が模索できる。
最後に4つ目は、非課税保有期限が撤廃されたことだ。運用成績に一喜一憂せずに長期的な視点で投資ができることは、大きなメリットと言えるだろう。「老後2000万円問題」に立ち向かうために、新NISAを積極的に活用しようという動きは全国で広がっている。しかし、長期間所有する以上は、相続問題に直面する機会も増えると考えられる。