“犯人”が、手の込んだ状況を充分に揃えて(つまり、たとえば、キャッシュカードに絡めた詐欺の場合なら、警察官役の人物や銀行協会の職員役の人物など)、それぞれが真実味のある説明をしたとすれば、少なくとも狩猟採集時代(それがホモサピエンスの体の構造や脳の認知神経配線などが適応した本来の環境)のホモサピエンスであれば、信じることが脳の当然の動き方だ。
そもそも、狩猟採集時代にそんな手の込んだ嘘を設定するようなことはありえず、したがって、そんな環境に適応した脳の神経配線は、正しい重要な情報として認知し、それに対応すべく行動したほうが生存・繁殖には有利だっただろう。それを、「これは嘘かもしれない」と考え、疑って、直ぐに動かないような個体は生存・繁殖において大きな損害を被っていた可能性が高かった、ということだ。
思い込みを抑制するため
精緻な検証を心がける
さて、では、質問にあった、こういった脳の「思い込み」特性を抑えるにはどうしたらよいだろうか。
正直なところ、すべての「思い込み」に対処するというのは、なかなか難しいと思われる。
ゆっくり思考できるときであれば「この話、この考え、本当のことか?」と疑ってかかり、自分自身でゼロに近いところから理性的脳内配線を活動させて精緻に検証していくことはできる。しかし、精神的に、あるいは物理的に、ゆとりがないときは、「疑る」こと自体に思いが行かないのである。気づかないのである。
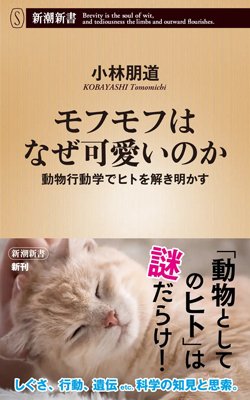 『モフモフはなぜ可愛いのか 動物行動学でヒトを解き明かす』(新潮社)
『モフモフはなぜ可愛いのか 動物行動学でヒトを解き明かす』(新潮社)小林朋道 著
「思い込み」神経配線が素早く作動してしまうのだ。脳がエネルギー不足のときは尚更そうである。“精緻な検証”が作動する方向へ神経の活動が移行するためにはエネルギーが必要なのだ。
まー、方法は、いろいろ考えられるが、今、ちょっとエネルギーが不足気味な私の脳内に浮かぶ方法は、“精緻な検証”が、無意識に立ち上がるくらい、それを習慣にする、ということだろうか。何度も何度も何度も繰り返して、意識して注意しなくてもそうなるような「習慣」のようにしてしまうのである。
繰り返す。現代社会では、「振り込め詐欺」に見られるような巧妙な偽装状況もつくり出すことができるし、さまざまな物事が自分の周囲で目まぐるしく動いていて、われわれは、「思い込み」神経配線のせいで、それらの動きを表面的に(!)結びつけて解釈し、誤った因果関係を思い込んでいる場合が多々あると思われる。







