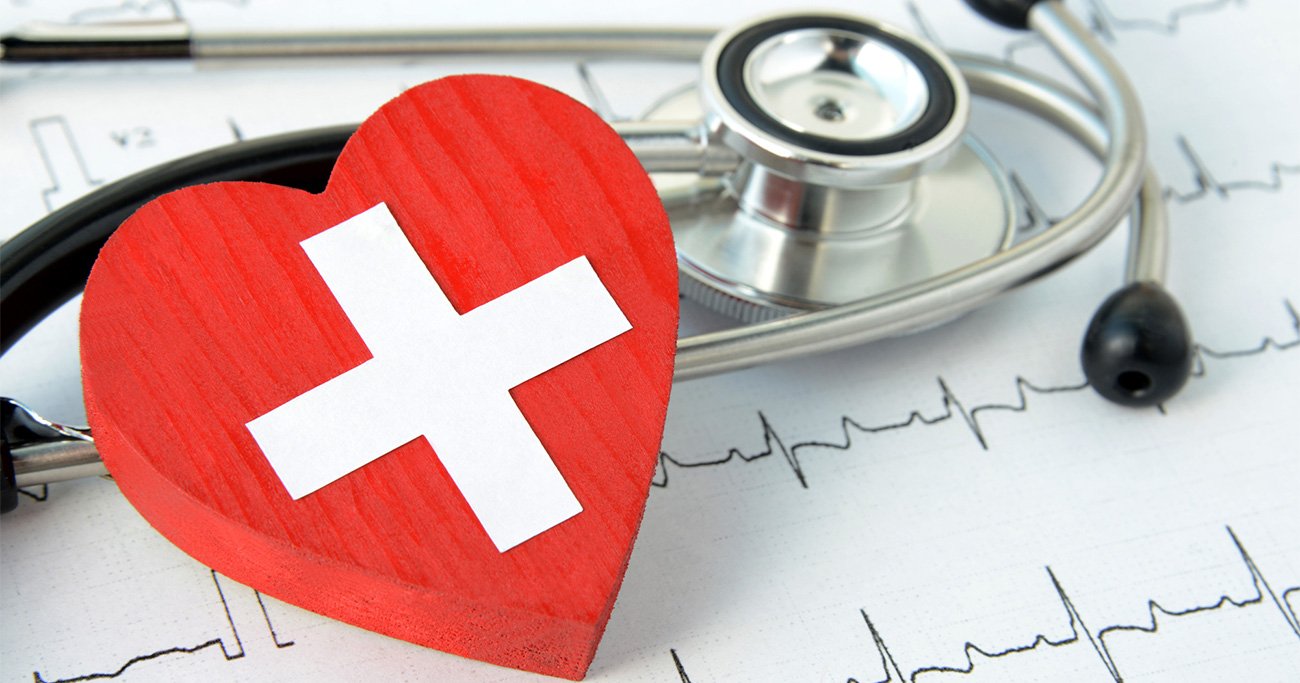 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
日本の臓器移植の希望者は1万6000人に上るが、亡くなった人からの年間臓器提供数は、その100分の1にも満たない。臓器提供の意思を医療機関がすくい取りきれておらず、手術可能な設備も整っていないのが現状だ。日本における臓器提供体制の課題や、臓器移植に関わるさまざまな立場の人々の経験を世に届けるべく、腎移植を受けた新聞記者が立ち上がる。※本稿は、『母からもらった腎臓 生体臓器移植を経験した記者が見たこと、考えたこと』(倉岡一樹、毎日新聞出版)の一部を抜粋・編集したものです。
あなたに腎臓をあげたおかげで
大腸ポリープが見つかった
移植手術から1年がたった2020年夏、母の大腸に複数のポリープが見つかり、内視鏡手術を受けた。
「がんなのではないか。私への腎臓移植で体に異変が生じたのではないだろうか……」。手術を受けるまでの日々は母を案じ、自分を責め、生きた心地がしなかった。
10月、手術は無事成功した。膝から崩れ落ちそうになるほど安堵すると、母はあっけらかんと言った。
「お医者さんが『がんの一歩手前』って言ってた。危なかったわ。やっぱり私は強運の持ち主だから大丈夫なのよ。こんな私の腎臓をもらえて一樹は幸運ね。あなたが死ぬまで機能し続けるから、安心していなさい」
やはり、そうだったか。私に腎臓を移植したばかりに――。背筋が凍り付き、母への申し訳なさで胸が締め付けられたのと同時に、「事なきを得てよかった。首の皮一枚つながった」との安堵感も入り交じった複雑な心境になった。勢いづく母が続ける。
「ポリープは移植の後に受けたドナーの健診で見つかったのよ。移植していなかったら手遅れになっていたから死んでいたわ。あなたに腎臓をあげてよかった。一樹のお陰ね」
移植後も母から腎臓を取り上げた罪悪感に苦しむ私にとって、この言葉は大きな救いとなった。「わずかだが役に立てたのかもしれない」。母の優しさに、涙腺が緩んだ。
その後、母は「通常運転」に戻った。聖マリアンナ医科大学病院での半年から1年に1回のドナー健診で「数値がとてもよいですよ」と太鼓判をもらい、実家の小さな庭での“畑仕事”に精を出している。
時折、母の様子を見に行くと、収穫した野菜や果物、花をくれる。特に私が好きなレモンは風味が抜群によく、酢の替わりにキャベツにしぼるとその甘みが引き立つ。気の向くままに話すのも相変わらずで、私が母の話から耳をそらすと「手術で性格までは治せなかったわね」とまくし立てる。移植前と何も変わらず、ほっとする。
ドナーになってくれた母が元気でいてくれることほどありがたいことはない。私は一秒でも長く母の腎臓を守らねばならないと誓う。そして母には末永く元気で、笑顔でいてほしいと願う。







