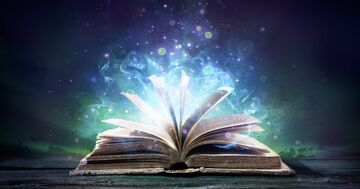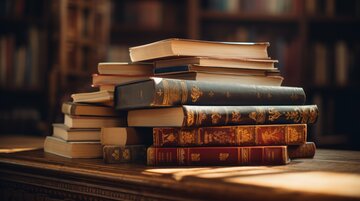「ハイデガーはなぜすごいのか?」思考の限界に挑んだ男
世界的名著『存在と時間』を著したマルティン・ハイデガーの哲学をストーリー仕立てで解説した『あした死ぬ幸福の王子』が発売されます。ハイデガーが唱える「死の先駆的覚悟(死を自覚したとき、はじめて人は自分の人生を生きることができる)」に焦点をあて、私たちに「人生とは何か?」を問いかけます。なぜ幸せを実感できないのか、なぜ不安に襲われるのか、なぜ生きる意味を見いだせないのか。本連載は、同書から抜粋する形で、ハイデガー哲学のエッセンスを紹介するものです。
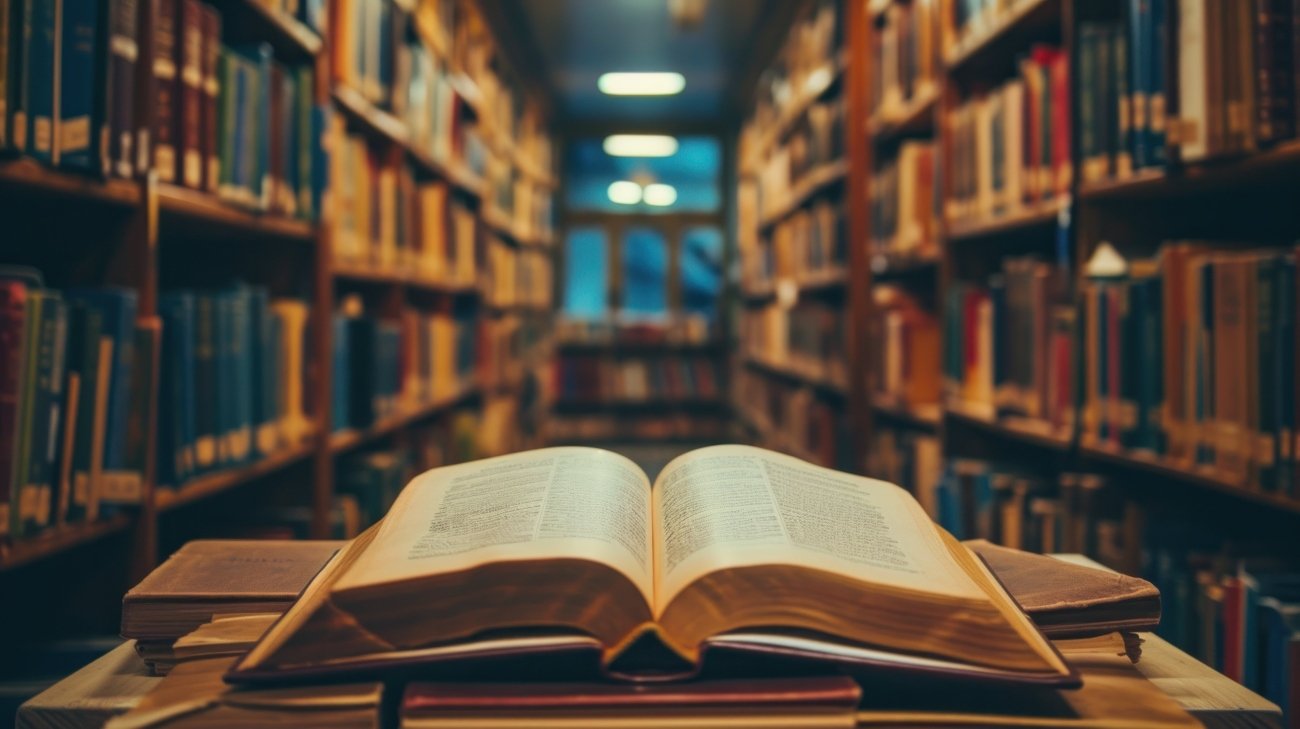 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
20世紀最大の哲学者、ハイデガーの挑戦
【あらすじ】
本書の舞台は中世ヨーロッパ。傲慢な王子は、ある日サソリに刺され、余命幾ばくかの身に。絶望した王子は死の恐怖に耐えられず、自ら命を絶とうとします。そこに謎の老人が現れ、こう告げます。
「自分の死期を知らされるなんて、おまえはとてつもなく幸福なやつだ」
ハイデガー哲学を学んだ王子は、「残された時間」をどう過ごすのでしょうか?
【本編】
「人間の思考にとって『存在』は大元の前提であり、建物の土台のようなものだ」
「土台?」
「そもそも不思議ではないだろうか? 人間はいくらでもどんなことでも考えることができる。すでに過ぎ去った過去の出来事から、まだ起きていない未来の出来事―はては現実に存在しない空想の出来事まで、あらゆることを考えることができる。
そんな万能ともいえる想像力を持った人間の思考が、なぜ『存在(ある)』についてだけ語ることができないのか。その理由は、思考において『存在』は土台のような位置づけのものであるからだ。土台から生み出された建物が、自らの土台を支えることはできない。当たり前の話だな。ほかに、もうひとつ例を出すとして、論理学というものを考えてみよう。といっても、難しい話ではない。
①人間は必ず死ぬ。
②ソクラテスは人間である。
③ゆえに、ソクラテスは必ず死ぬ。
といったぐらいの単純な論理の話でかまわない。さて、今述べたことは『論理的に正しい』わけだが、この『論理的に正しい』がどういうことなのか、同じように論理的に説明することは可能だろうか?」
「……うーん、直感的には無理のような気がします。うまく言えませんが、論理が自分の正しさを論理で語れるわけがないというか……」
「論理的に正しい」を説明できますか?
「おお、だいたいの核心はつかんでおるぞ。もう少し丁寧に言えばそれはこういうことだ。たとえば、『論理的に正しいとは何か』について、誰かが論理的に説明できたとしよう。さて、その説明が有効なものだとしたら、それは当然『論理的に正しい』ものでなくてはならない。おっと、また『論理的に正しい』がでてきてしまった」
「なるほど、『ある』の話と同じですね」
「そうだ、Aを説明したいのに、その説明の中にAが出てきてしまう例のやつだ。『論理的に正しい』すなわち『真』というのは、論理において土台、前提のようなものであり、論理が自らの土台であるところの『真』について語るのは原理的に不可能だと言える。そして、この構図は、人間の思考と存在についても同様に当てはまる」
「つまり、存在(ある)は人間の思考を成り立たせている土台であり、だから人間はそれを語れないのだ、と」
「そうだ。したがって『存在とは何か』というのは、『〇〇とは何か』という単なる問いのパターンのひとつではなく、人間においてまさに本質的な問いだということがわかる。そして、この問いの重要性に気づいている哲学者は、歴史上自分ただ一人だとハイデガーは豪語しているわけだな」
なるほど、そこがハイデガーの偉いところというわけか。たしかに「存在」が人間の思考において、そこまで重要だなんて考えたことも聞いたこともなかった。
(本原稿は『あした死ぬ幸福の王子ーーストーリーで学ぶ「ハイデガー哲学」』の第1章を抜粋・編集したものです)