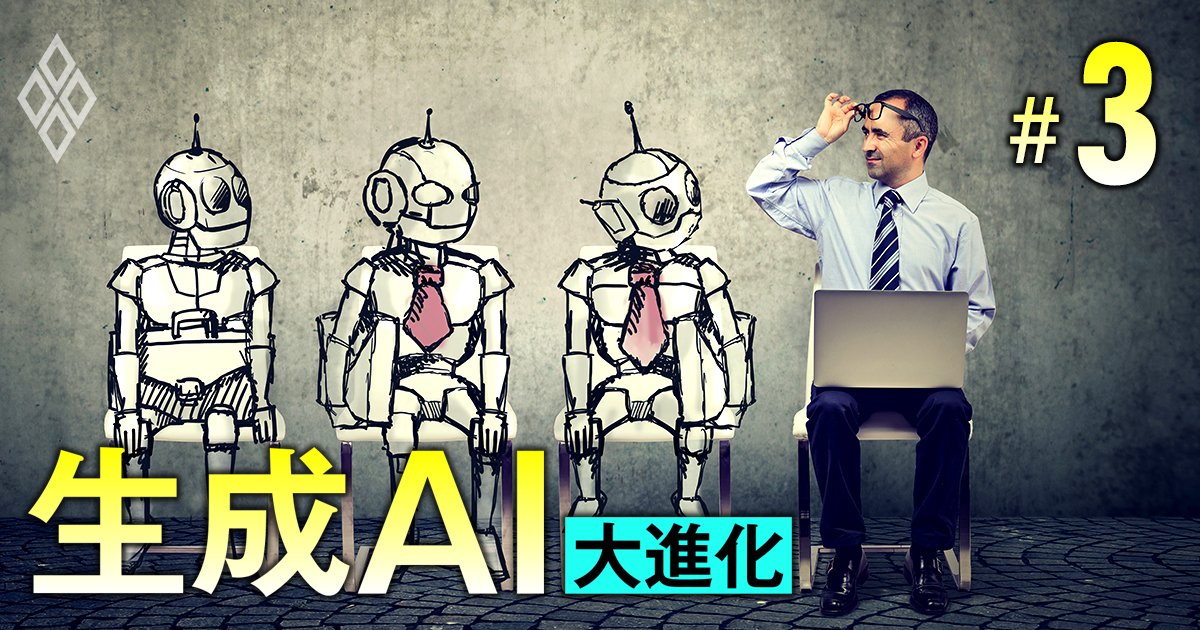管理栄養士の暗黙知をAIに教え込む「スーパー泥くさい」現場
勝美さんは、「未来献立」の開発過程を「スーパー泥くさい仕事」と振り返る。特に、AIに献立づくりのイロハを教え込む作業は、予想以上に難航したという。
まず、開発において最も重要だったのは、「食事を楽しんでほしい」という管理栄養士の定性的な思いを、AIに組み込むことだった。開発チームは管理栄養士たちにヒアリングを重ね、知見や経験をAIに反映させる方法を模索。専任の管理栄養士には開発会議にも参加してもらい、「汁物を含める」「主菜と副菜を提案する」などのルールを定義し、季節感や食べたいと思える献立の特徴といった暗黙知のデータ化に取り組んだ。
だが、食べたいと思える献立かどうかは人によるだろう。この主観的な概念を、どうやってAIに学習させていったのだろうか。Laboro.AIの広瀬圭太郎さんは、「AIが提案する献立のメニュー名と写真を献立ごとに吟味して良し悪しを判断し、地道なチューニング作業を重ねた」と語る。
 広瀬圭太郎さん Photo by M.S.
広瀬圭太郎さん Photo by M.S.
この過程で、味の素の豊富なレシピデータベースが大いに役立った。主要栄養素だけでなく、微量の栄養素、調理手順、調理時間など、詳細なデータを分析し、「食べたい」と思わせる要素を特定。特定した要素やパターンをもとに、AIが魅力的な献立を再現できるようチューニングを繰り返した。
ちなみに開発の初期段階では、8割が「これはダメだ」という献立だったという。中華にイタリアンなどジャンルが混在していたり、季節感が合わなかったり、アスリート向けの食べきれない量の品数が提案されることも。一言で言えば、「食べたい!」とは思えない提案だったという。