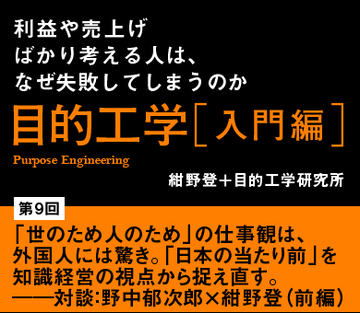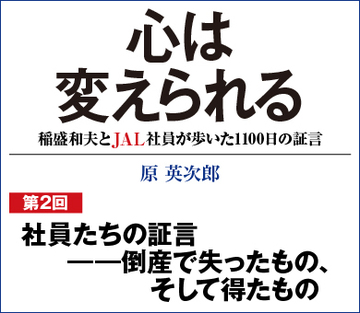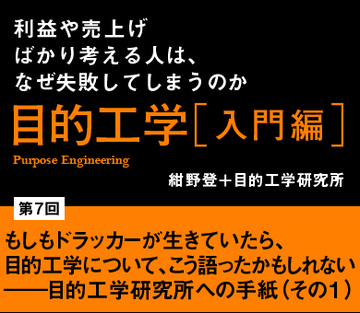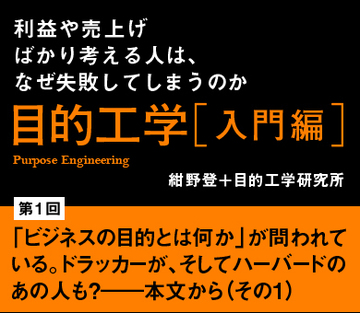最先端のマネジメント研究では、
理論と実践の行き来が重視される
紺野 同感です。もちろん、我々はサイエンスを否定している訳ではないのですが、その一方で「アート」も非常に重要だと考えている。
野中 そう、バランスを取れ、ということです。近代経営学で語られていることの多くは、言わば演繹法の世界なんです。トップが掲げる証明すべき命題(ビジョン)があって、それを論理的に説明できたらそれで良し、としてしまう。
要するに、「すべての人間は死ぬ」「ソクラテスは人間である」「ゆえにソクラテスは死ぬ」という単なる三段論法に過ぎない。しかし、これだけだと「だから何だ」ということになって、経営そのものに意味がなくなってしまう。
トップの意思決定がなにがしかの意味を持つためには文脈が必要であり、その文脈というのは個別具体的な事象を積み上げて行くことからしか生まれてこないのです。経営のおもしろさというのはこの意味を発見していくプロセスにこそある訳ですが、この部分はむしろ帰納法的なんです。
 紺野登(こんの・のぼる)
紺野登(こんの・のぼる) 多摩大学大学院教授、ならびにKIRO(知識イノベーション研究所)代表。京都工芸繊維大学新世代オフィス研究センター(NEO)特任教授、東京大学i.schoolエグゼクティブ・フェロー。その他大手設計事務所のアドバイザーなどをつとめる。早稲田大学理工学部建築学科卒業。博士(経営情報学)。組織や社会の知識生態学(ナレッジエコロジー)をテーマに、リーダーシップ教育、組織変革、研究所などのワークプレイス・デザイン、都市開発プロジェクトなどの実務にかかわる。
紺野 ただし、それは単なる現場主義に終わってしまうことも多いですね。
野中 そうです。どちらも、一長一短ある。そこで、アリストテレスの実践的三段論法が出てくる。
紺野 わかりやすく言い換えると、こういうことだと思います。現場の人たちが必死になって現実と向き合っていても、主観的な軸が明確でないと単にバタバタするだけで終わってしまう。
一方で、客観的ビジョンに基づき「ああしろ」「こうしろ」と命令されて動いていればバタバタしなくて済むんですが、そればかりを続けていると、今度は著しく人間性が阻害される。
ですから、現場にある「手段」からスタートすることはとても大事なんですが、ポイント、ポイントで「今していることの本当の意味はなにか?」と立ち返り、大目的を更新していく必要がある。その上で再び手段へと戻って行くのが一番強い。
野中 演繹法は命題から出発し、それを論理的に分解していって個別具体へと到達する。紺野さんが本の中で使っている言葉で言うと、「目的」と「手段」は常に目的が手段を支配する関係にあって、その逆はあり得ない訳です。
しかし、実践的三段論法ならば、目的が手段と合わない場合には手段の方からも問い直しが起こる。小目的から大目的へのフィードバックがある、というのが非常に重要な点だと思います。
紺野 そのフィードバックが幾重にも繰り返されて行くプロセスの中で新しい何かが創造されていく。これが、現実的なイノベーションの姿だと思いますね。
我々と非常に近い考え方を持っている経営学者で理論家のヘンリー・ミンツバーグが「マネジメントはアートである」と主張し、戦略はサイエンスではなく、クラフティングであるべきだ、と指摘した。
サイエンスは絶対知のみを追求しますが、クラフティングは実際に手を動かしながら理論と現実の間を何度も往還しないとできませんから、現実に根ざした実践知が求められる。